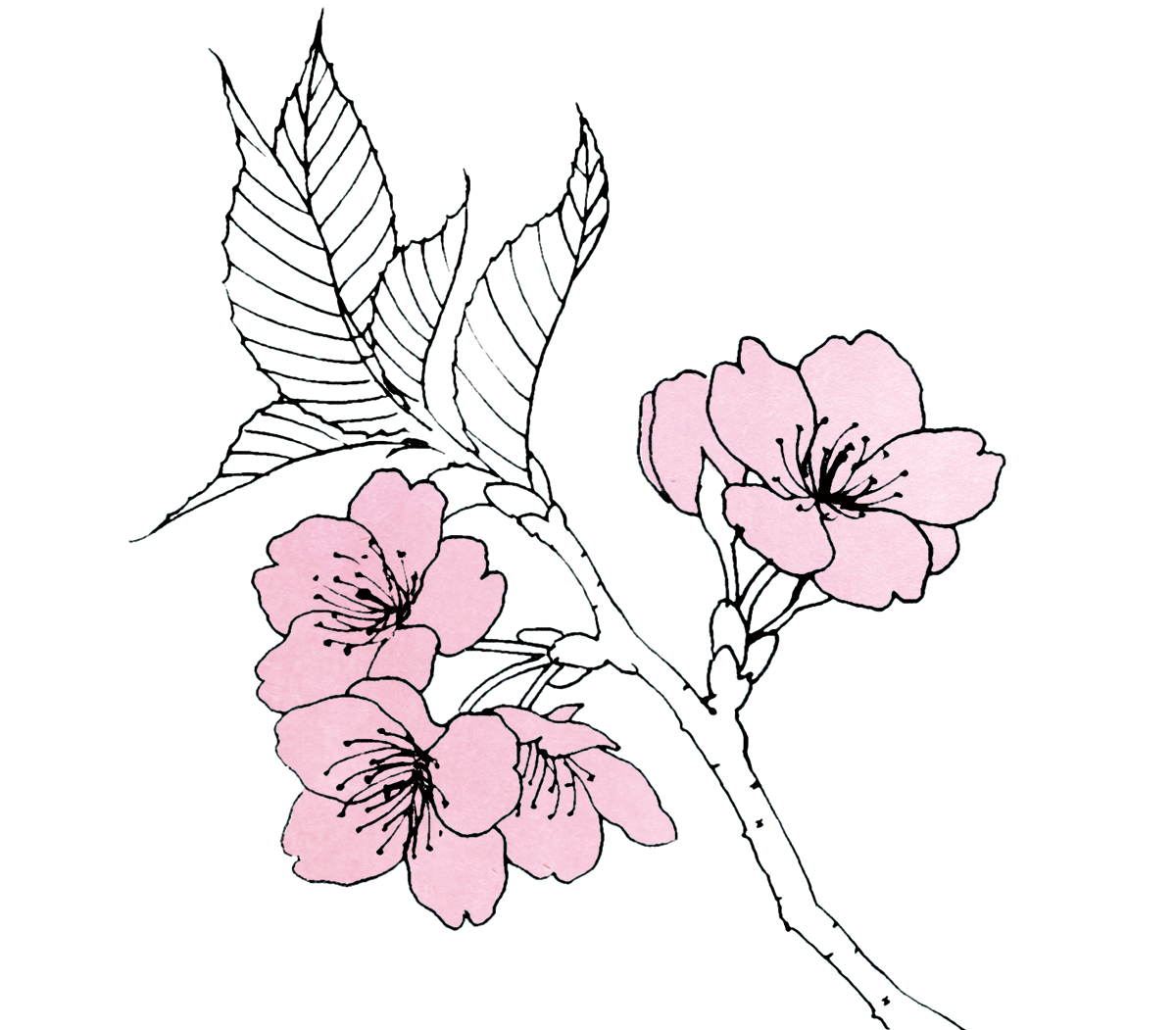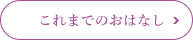月曜日の夜が更け、朝が近づいてきた。岡部はクーラーの効きすぎた事務所でひとり、サイン色紙を眺めていた。
庭の掃除に行かなくちゃ、と思ったとき、ほとんど無意識に、ゴミ箱へと手を動かしていた。口の大きなプラスチック製のゴミ箱に、色紙は、難なく落っこちた。
なかなか、うまく書けてると思わない?
電話越しの声が蘇ってきて、確かに、なかなか、うまい、と岡部は感心する。でも、もし自分がナビのサインを知らず、これを本物だと信じたら、そしたら、あの人、どうするつもりだったんだろう。いい大人が、そんな、つまらない嘘をついて。
色紙はゴミ箱に落としたまま、岡部は箒と塵取を手に裏口から庭――松濤園に出た。
時刻は午前六時を迎えたところだが、もう、かなり暑い。緑の匂いが空気にまで染み込んで、吸い込む味が濃く感じられる。空は青く澄んで、日中には七月と思えない気温にまであがるかもしれない。そんなことを考えていると、どこからか、泣き声が聞こえてきた。子供の声だ。どこだろう? 頭には前日からの宿泊客名簿が表示され、七歳の男の子が家族と滞在していたことを思い出す。朝の散歩にでも出て、そこで転んだのだろうか。考えを巡らせながら、岡部は声の出どころを探して視線をめぐらせた。あたりには、しかし、誰もいない。あてもなく足を進めていると、汗がにじんでくる。大広間の建物には、改修工事のための足場が組んであった。ああ、そうだ、工事、始まるんだ。そう思ったとき、建物の屋根よりもうえに、半ズボンの男の子がいるのを見つけた。
目を疑った。
なんだってそんなところに。
岡部は急いで建物のほうへと近づいていった。額に、手のひらに、汗がにじんでくる。
「だいじょうぶ?」
下から声をかけるが、男の子は鉄の棒を掴んだまま泣きじゃくってばかりで、岡部の呼びかけも届いておらず、えずくように咳きこみながらも、涙が止まらずに肩を震わせている。おーい、と箒を高くかかげて声をはりあげた。男の子が、ようやく、下を見てくれた。
「だいじょうぶ? 降りられなくなったの?」
やさしく、しかし焦りの混じった問いかけに、男の子は再び泣き出した。
高さにして、およそ六メートル、いや、もっと低いか。岡部は目で測る。同時に、建築途中の家屋のてっぺんから落下したときの記憶が蘇る。高校卒業後、建築関係の仕事に就いていたときの出来事だ。怪我は軽傷だったが、心は、回復しなかった。
どうしよう、どうしよう。
汗が頬をつたう。
「だいじょうぶ、だいじょうぶだから、いま、誰か呼んでくるから」
誰か呼んでくるって、ここを離れるのか? そのあいだになにかあったら? 汗が止まらなかった。なぜ箒と塵取なのか。せめて携帯を持っていれば。どうしよう。どうしよう。
身動きのとれない体の中で、慌てふためく気持ちが暴れている。
どさ、となにかが落ちる音が聞こえた。
びっくりして視線をあげるが、男の子は、まだ、上で泣いている。
岡部の横をなにかがとおりぬけていく。
人だ。
男の人だ。
ポロシャツにスラックスの男。背中を見て、あ、と思うが声が出ない。男は、なんの迷いもなく足場に手をかけ、もう何度ものぼっているのだと言わんばかりのなめらかさで上へ、上へとのぼっていった。賢一郎だった。温和な物腰からは想像もできないくらい、力強い動きだった。足場は本来、そんなふうに登るものではない。そうだ、どこかに登り降りのための階段が設えてあるはずなのだ。そんなことに、岡部はようやく思い至る。そんな登り方じゃ危ないですよ、落ちますよ、と賢一郎に声をかけてやりたくなるが、実際には眺めることしかできなかった。
足場の途中で、賢一郎が子供に声をかけた。
「おーい、上、上を見てごらん、ほら、空、晴れてるな、いい天気だ。いいや、下は見なくていい、だいじょうぶだから、空、空を見よう。あのさ、ここ、この建物さ、神様が守ってくれてるんだって。もうずっと守ってくれてる。だから、なんにも怖くないから」
また適当なこと言ってる。岡部は内心呆れるが、しかし、賢一郎の言葉を援護したくもなる。
そうだよ、だいじょうぶだよ、なんにも怖くないから。そう言ってあげたくなる。
ほどなく、賢一郎はてっぺんまで行き着いて、男の子を無事に保護した。岡部も階段を見つけ、そこから降りてくるよう指示を出した。
松濤館に戻った岡部は男の子の親を呼んだ。事情の説明は賢一郎が担当した。ひとしきり叱られたあと、両親にうながされた男の子は、賢一郎に「ありがとう」と頭をさげた。庭で見かけたクワガタを追いかけているうちに上までのぼったんだってさ、とフロントから一連の様子を眺めていた岡部に賢一郎が教えてくれた。
「だからって、いちばん上までのぼりますか」
苦笑しながら岡部は首を傾けた。
「ああ、そうだ、一昨日はごめん。サイン、なんとかしたかったんだけど、でも」
「いえ、いいんです。いつか、ひとりのファンとして会える機会を待ちます」
「ほんと? 怒ってない?」
岡部はすこし悩むようにまぶたを伏せてから、顔をあげ、賢一郎の頬を指さした。
「そこ、汚れてますよ」
え、と頬に触れてから、賢一郎はいそいそとトイレに向かった。
事務所に戻った岡部はゴミ箱から色紙を拾い上げ、しばし眺めたあとで、ひきだしにしまった。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。