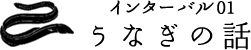
うなぎを食べたい、と言ったのは香織だった。
でも、まさか、柳川まで足をのばすことになるとは思わなかった。
私鉄の駅を出て、川下りの舟に乗った。
遠方からの旅行客にまじって、日帰りの自分たちが観光を楽しんでいるのは、思った以上に楽しい時間になった。あまりに楽しすぎて、うなぎという目的を忘れていた。
祐介は、天神で合流したときから表情が硬かった。前日にあまり眠れなかったという言葉から、また仕事だと香織は決めつけた。ジャケットにネクタイまでしめて、徹夜明けなのかもしれない。
そう理解して、電車の中でもそっとしておいた。
水とともに揺れながら見る、舟からの景色は、風の涼しさとあいまって、美しかった。
「楽しい?」
隣の祐介に聞いてみる。
「え? うん、ああ」
心ここにあらず、といった態度に、香織はごめんね、と言った。
「無理させて」
「大丈夫、がんばる」
たどりついた先は、立派な建物だった。
白い洋館があり、その隣には和風の建築物があって、歴史に関心を持たない香織も風格を感じた。祐介は「こっち」と左手の建物を指さした。松濤館と名付けられた宿泊施設の奥にレストランがあった。そこのせいろ蒸しが、その日のメインイベントであることを、入口に立て掛けられたおいしそうな写真で、香織も思い出した。
庭園の見渡せる窓辺の席へ案内された。
隣には四十歳くらいの夫婦が座っていて、白い服を着た料理人と会話をかわしていた。
祐介は席につくなり、水をひといきに飲んだ。香織はメニューを手に取ってひらいた。
「せいろ蒸しだよね。どれにする?」
「あ、うん、えっと」
「松、竹、梅、せっかくだから特上?」
冗談めかして尋ねるが、祐介の耳には入らなかったようで、彼は目を泳がせていた。隣の会話が、とつぜん、香織の耳にも飛び込んでくる。
「もう十年ですか」と料理人が言う。
「そう、ここで食事して、そのあとですよ」
「ええ、よくおぼえてます。スペシャルメニューを用意させていただいて」
「え、なに、そうなの?」と奥さんのほうが初耳だと驚いていた。料理人と旦那さんは旧友同士のように笑った。
「だから、今日もあのときとおなじスペシャルメニューを」
「なに、またプロポーズしてくれるの?」
奥さんの言葉に、香織はまばたきを繰り返した。
ちらりと祐介を見る。ネクタイ。ネクタイしめてる。なに、うなぎ食べるのにネクタイ。え。え?
隣の会話がおだやかな笑いでとじられると、祐介が立ち去る料理人を呼び止めた。
「あ、あの、こっちも、スペシャルメニューで」
隣の席の夫婦が聞いていないふりで、しかし耳をそばだてているのが香織にもわかる。
祐介の緊張が香織にも伝わる。
何度もリハーサルを重ねたみたいに、絶妙な間をおいてから、料理人が「かしこまりました」と請け合う。
香織はグラスに手をのばし、水を、ひといきに飲み干す。
祐介はネクタイをしきりにさわり、思い出したように、胸ポケットを上からおさえた。
グラスをまた口に持っていくが、水がもう入っていないことに、香織はしばらく気づけないでいる。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。

うなぎを食べたい、と言ったのは香織だった。
でも、まさか、柳川まで足をのばすことになるとは思わなかった。
私鉄の駅を出て、川下りの舟に乗った。
遠方からの旅行客にまじって、日帰りの自分たちが観光を楽しんでいるのは、思った以上に楽しい時間になった。あまりに楽しすぎて、うなぎという目的を忘れていた。
祐介は、天神で合流したときから表情が硬かった。前日にあまり眠れなかったという言葉から、また仕事だと香織は決めつけた。ジャケットにネクタイまでしめて、徹夜明けなのかもしれない。
そう理解して、電車の中でもそっとしておいた。
水とともに揺れながら見る、舟からの景色は、風の涼しさとあいまって、美しかった。
「楽しい?」
隣の祐介に聞いてみる。
「え? うん、ああ」
心ここにあらず、といった態度に、香織はごめんね、と言った。
「無理させて」
「大丈夫、がんばる」
たどりついた先は、立派な建物だった。
白い洋館があり、その隣には和風の建築物があって、歴史に関心を持たない香織も風格を感じた。祐介は「こっち」と左手の建物を指さした。松濤館と名付けられた宿泊施設の奥にレストランがあった。そこのせいろ蒸しが、その日のメインイベントであることを、入口に立て掛けられたおいしそうな写真で、香織も思い出した。
庭園の見渡せる窓辺の席へ案内された。
隣には四十歳くらいの夫婦が座っていて、白い服を着た料理人と会話をかわしていた。
祐介は席につくなり、水をひといきに飲んだ。香織はメニューを手に取ってひらいた。
「せいろ蒸しだよね。どれにする?」
「あ、うん、えっと」
「松、竹、梅、せっかくだから特上?」
冗談めかして尋ねるが、祐介の耳には入らなかったようで、彼は目を泳がせていた。隣の会話が、とつぜん、香織の耳にも飛び込んでくる。
「もう十年ですか」と料理人が言う。
「そう、ここで食事して、そのあとですよ」
「ええ、よくおぼえてます。スペシャルメニューを用意させていただいて」
「え、なに、そうなの?」と奥さんのほうが初耳だと驚いていた。料理人と旦那さんは旧友同士のように笑った。
「だから、今日もあのときとおなじスペシャルメニューを」
「なに、またプロポーズしてくれるの?」
奥さんの言葉に、香織はまばたきを繰り返した。
ちらりと祐介を見る。ネクタイ。ネクタイしめてる。なに、うなぎ食べるのにネクタイ。え。え?
隣の会話がおだやかな笑いでとじられると、祐介が立ち去る料理人を呼び止めた。
「あ、あの、こっちも、スペシャルメニューで」
隣の席の夫婦が聞いていないふりで、しかし耳をそばだてているのが香織にもわかる。
祐介の緊張が香織にも伝わる。
何度もリハーサルを重ねたみたいに、絶妙な間をおいてから、料理人が「かしこまりました」と請け合う。
香織はグラスに手をのばし、水を、ひといきに飲み干す。
祐介はネクタイをしきりにさわり、思い出したように、胸ポケットを上からおさえた。
グラスをまた口に持っていくが、水がもう入っていないことに、香織はしばらく気づけないでいる。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
