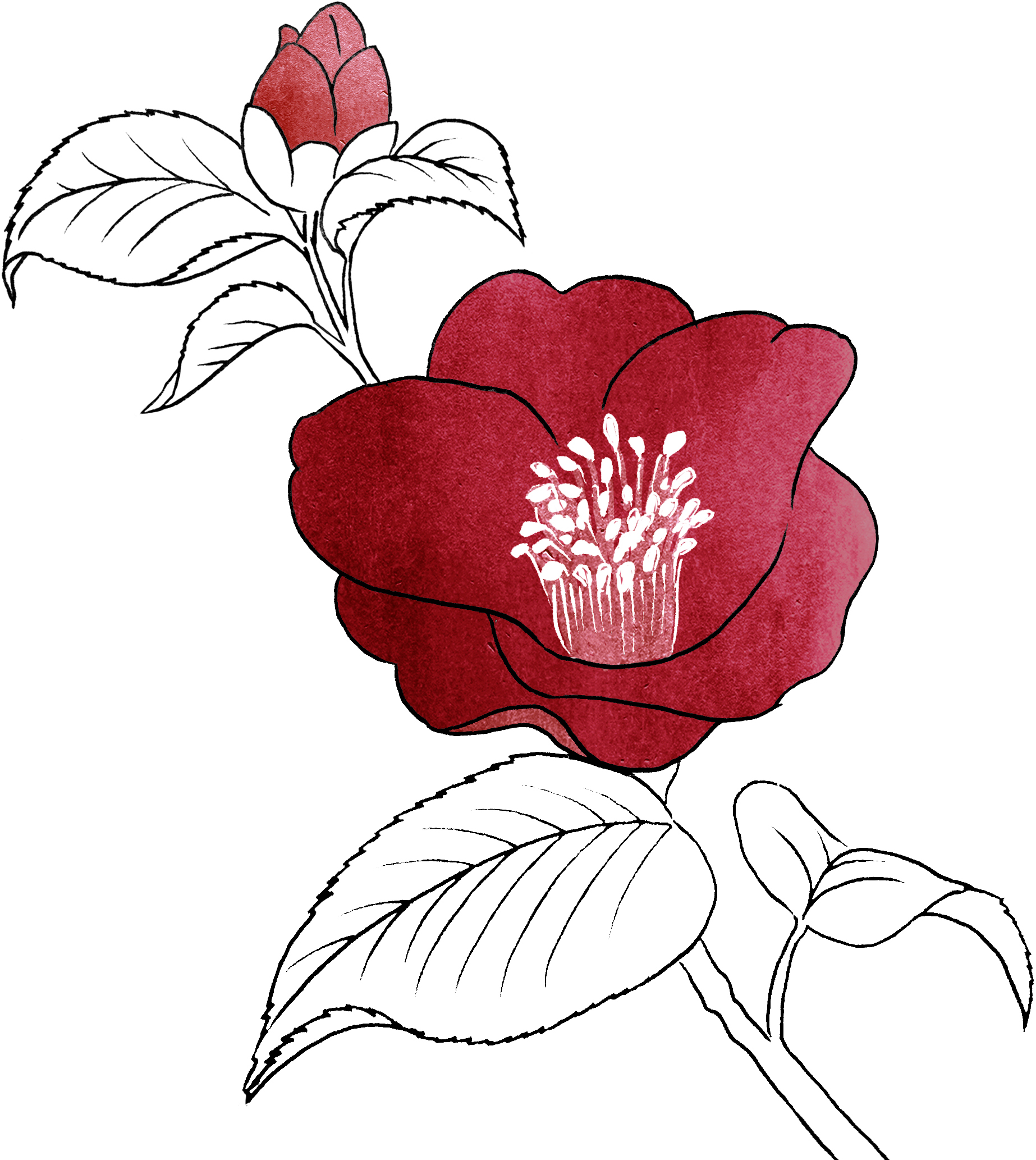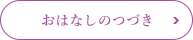「なあ、ウエディングプランナーやってるって言ってたよな」
不意に、太田が尋ねた。
「ああ」
「プロポーズの言葉でさ、多いのって、どういうのだ」
柳川で結婚する人物のドラマでも構想しているのだろうか。賢一郎は推測したが、そんなことを考えている素振りは見せずに「いろいろだな」と答えた。
「でもさ、みんな、それ以前のことのほうが大切みたいに言うんだよな。具体的にプロポーズされたときの言葉とかサプライズの仕立てとかよりも、結婚を意識した瞬間とかさ、同棲中に何度も結婚の話題が出ては冗談みたいに消えていったこととか」
「おまえは?」
突然、間合いを縮めてくるような迫力で、太田は聞いた。
「俺? 俺は、普通だよ、結婚しましょう、って」
「マジか」と太田は驚いた。「おまえ、練りに練ってたじゃないか、プロポーズの言葉」
「は?」
「結婚を決めたら『僕の人生の主人公になってください』って言うんだって」
賢一郎は目を見開き、あわせて口も大きく開いた。
「で、俺がツッコんだだろ、嫁さんがおまえの人生の主人公になったら、おまえはなんになるんだって」
「ええええ」
「マジで忘れてんのか。おまえな、小川、小川時代のおまえが言ったのは、『ダブル主演だ』って」
なんだそれ、と賢一郎はうなだれた。
「いや、もう、それは忘れてくれ」
「忘れられるか。俺、最高だと思うんだって、いまでも、その台詞」
「いやいやいやいや」
「まあ、忘れてたけどな」
太田のその一言で、賢一郎は顔をあげ、口をゆがませた。
「今日、おまえに会うまで忘れてた。でも、いい台詞って思うのは本心だ。だから思い出した」
「なんだよそれ」
寒気を感じたふうに肩をふるわせてから、賢一郎はまだ熱いコーヒーに口をつけた。
「俺、結婚、考えてるんだ」
溜め込んだ息を吐き出すように、太田が告げた。
「え、よかったじゃん」
「でもまだ求婚してない」
「しろよ、てか、よかったな」
「女優なんだ」
「は?」
太田の交際相手は賢一郎も知っている、福岡出身の女優だった。離婚歴があり、娘と息子がひとりずついる。子供たちも太田に懐いているらしく、結婚の話もちらほらと出てはいるが、相手は太田が初婚であることや、結婚となればいきなり二人の子持ちにさせてしまうことを気にしている、という話だった。
「俺もさ、彼女だけなら何がなんでもって言えるけど、子供たちの幸せまで支えられるかって自問すると、自信が持てなくてな。仕事でもそうだろ。信頼できる連中が集まってるから、任せるところは任せて進めていけるけど、自分でぜんぶやるってなったらとても無理だ」
「結婚は仕事じゃないだろ」
賢一郎の指摘に、太田はむしろ胸を張った。
「そうだよ、仕事なら、失敗したって責任のとりようはある。でも子供の人生だぞ。責任だの、撮り直しだの、できないだろ。向いてないんだよ、俺。脚本があって、絵コンテがあって、そういう、段取りのあるものなら得意だけどさ」
「ないよ、人生に段取りなんか。子供たちだって懐いてるんだろ? さっきさ、仕事と違うっていったけど、でも、おまえがおろおろしてたら仕事も駄目だろ。どんと構えてなきゃ、周りが不安になって、うまくいくもんもいかなくなるだろ? だからさ、おまえは彼女のことをまず第一に幸せにすることを考えて、同時に、自分も幸せだって顔して、そういうのだよ、そういうのが、子供たちにも伝わるんだから、あのさ、おまえ、ほんと、昔っからそうだったけど、おまえな、ちょっと、仕事できるからっていってな、なんでも自分でやろうとしすぎなんだよ。それで周りの人間も、同じくらいできてくれないと不機嫌になるだろ? あれな、よくないからな?」
「なんで今、そんなことでディスられなくちゃいけないんだよ」
太田は口をとがらせたあとでコーヒーを飲んだ。
「ディスってない、応援してんだ」
「聞こえねえよ、応援になんか」
「してんだよ、馬鹿、幸せになれよ、なれるだろ、おまえが笑って、彼女のこと笑わして、それでいいだろ。それに、あれだ、太田んとこはお兄さん家族もなんかにぎやかだっただろ」
「子供が六人もいるからな」
「六人? 増えたか?」
「ああ、ここ五年くらいで二人生まれたからな」
「んー、まあ、人数はいいや、いや、えーと、ほら、だから、おまえと彼女が結婚したらさ、従兄弟、従兄弟がどかんと増えるだろ、遊び相手にもなるかもしれないし、いいじゃんか、親族がいっぱい」
思いつきで言ってから、賢一郎は両手を広げてみせた。ミナミに教えてもらった話が重なり、ああ、ここにも縁があった、と嬉しくなった。
「太陽がいっぱいみたいに言うな」
突き放すように言う太田に、賢一郎は追い打ちをかけた。
「おまえが彼女たちの太陽になれ」
「決め台詞みたいに言うな」
愚痴っぽくつっこんでから、太田は笑った。賢一郎も笑った。
「まあ、あれだ、太田、抱えすぎるの悪いくせだ」
「おまえだって似たようなもんだったじゃないか」
「だからわかるんだ。ここで働くようになって、身をもって学んだ。いい意味で、適当にやるんだよ」
ふっ、と太田は鼻から息を吐いた。
「さっき、奥さんにも同じこと言って怒られてたじゃないか」
「いいんだよ、うちは、もう、ダブル主演だから。多少の摩擦がないとドラマにならない」
夜に飲みに行く約束を交わしてから、太田と別れた賢一郎は事務所へ歩きだした。途中、保育園から祖母とふたりで戻ってきた娘に会ったので、頭を撫でた。女優の子供たちが何歳くらいなのか、聞き忘れたていたことに気が付き、ほんと適当すぎ、と妻の声が耳に聞こえた気がした。
事務所に戻ると「GM、もうすぐですよ」と声をかけられた。福岡市の天神にあるラジオ局で、御花の社長として妻が登場する予定だった。女性の働き方について、というテーマで、福岡県内の女性社長を招いては意見をうかがう、という趣向らしく、スタッフたちといっしょに、事務所のスピーカーに耳を傾けた。社長は、いささか緊張しているふうに挨拶を述べたが、「緊張されてますか?」というパーソナリティの一言に笑ったあとで、普段の調子を取り戻した。
「もう、ほんと、緊張してて、だけど、うちのGM、あ、ゼネラルマネージャーっていう役職がですね、出掛けに、適当でいいよって声をかけてくれたんです。適当って、いいかげんって意味じゃないですよ。適材適所っていう言葉がありますよね。あれに近くて、力を入れるべきところは入れる、抜くべきところは抜く、適度な力加減というのを言ってるんです。そうやって、理屈として言われると、なんだか小難しくて駄目なんですけど、うちのGMが『適当に』っていうと、その響きっていうのかな、あ、適当でいいんだ! って、あの、いいかげんって意味じゃないですよ、そうじゃなくて、その匙加減が、いいんです。だからね、私、うちのスタッフにも、できるだけ気楽に、思っていることは話してほしいし、意見があれば言ってほしい。そこで緊張する必要ないんです。礼儀作法というのはあって然るべきだけど、自分を無理におさえつけるような力は、そこはね、違うから、力入れるところそこじゃありませんから」
事務所の面々の目がそれとなく自分に向けられていることを察知した賢一郎は、そっと、トイレに立った。個室に入って鍵をかけると、ヘナヘナと力が抜けていき、自分も緊張していたのだと思い知った。
——適当ってのも、難しいもんだな。
その言葉も、トイレを出たあとで、ノートにメモした。使わずじまいで忘れていたプロポーズの言葉も、ついでに書いてみた。文字になると、なおのこと恥ずかしかった。
「なんだよ、ダブル主演って」
旧友の太田がその言葉を使い、交際相手の女優がそれを笑って受けとめ、御花で挙式披露宴を行う未来を、この日の賢一郎は、まだ知らない。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。