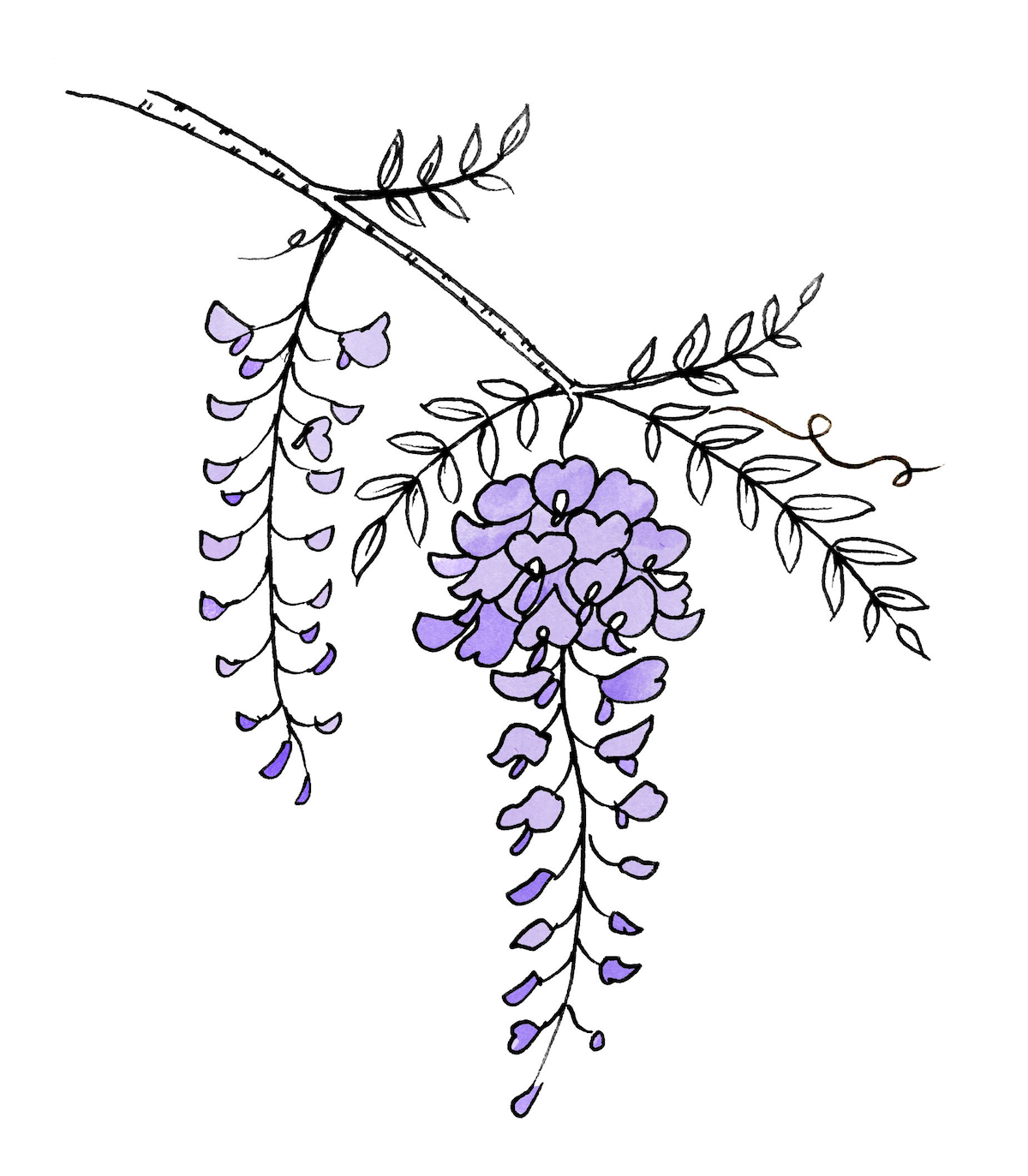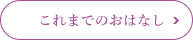会議のあと、河村は従業員用の休憩室に寄った。ドアを開けると数名のスタッフがいて、営業の波場が豪華な花束を持っているのが目に入った。
「どうしたの、なにかのお祝い?」
「あ、総料理長!」と波場が元気な声をあげる。「あ、これですか! これですね! お祝いっていうか、そうですね、まあ、ちょっとしたパーティーみたいなものですかね!」
「三崎さんのかい?」
三崎夫妻は、かつて御花で挙式を行ったご夫婦で、その晩の予約も、結婚記念日を祝う恒例の宴席だった。
「ああ、ちがいますちがいます、それとは別の、なあ」
力強く、周りのスタッフに同意を促して、波場は満面の笑みを浮べた。
「ほら、あれですよ、ぼくが、妻にですね、持って帰るんです。花束、妻に、これ、なあ」
もう一度、波場は周囲に確かめた。なにかあるな、と河村は疑ったものの、自分には関係のないことだと割り切って、コーヒーを一杯だけもらってから厨房に戻り、ディナーの準備に取り掛かった。
三崎夫妻は先代女将からの常連でもあり、河村も、その祝福には、腕によりをかけた。例年、「メニューはおまかせで」と注文をいただく。緊張もあるが、楽しみでもあり、夫妻のために考案した品が料亭のメニューに昇格したこともある。「すっぽん蒸し」も、そのひとつだ。
料理長の職を引き継いだ最初の秋、三崎夫妻をもてなす料理たちのなかにそれを入れた。女将が気に入ってくれた味なので、験担ぎのようなものだったが、コースの一品として提供すべく、鍋ではなく小鉢に、すっぽんと地の野菜を入れて出した。夫妻はこれを、とても気に入ってくれた。
翌年、すっぽん蒸しを用意していなかったことに、ひどく落胆された。あれからいくつかの店で食べたが、河村さんのが最高でした、と。その意見に、ほかのスタッフたちもそれを食べてみたいと言い出した。
和食メニューの一新というミッションに取り組むなかで、周囲との軋轢がなかったわけではないが、スタッフたちにすっぽん鍋を振る舞ったことが、人間関係に雪解けをもたらした。全員で新メニューを考える契機となり、土産物の開発まで楽しむ仲になった。夫妻への料理には、ゆえに、深い感謝の念も込められている。
その夜も、最後のデザートを出し終えた河村は、厨房に帽子を置いて、個室へ挨拶に向かった。外から声を掛け、ふすまを開けた彼が目にしたのは、意外な光景だった。
三崎婦人が花束を手に、立って待っていた。そればかりか、御花の現社長をはじめ、数名のスタッフが、お客様のための空間であるはずの個室に入っている。
「河村さん」と三崎婦人が言った。「おめでとうございます」
「おめでとうございます」と旦那様が続き、それからスタッフたちが「おめでとうございます」と声をそろえた。
背後で、ガタン、と音が聞こえた。廊下を振り返ると、料理を運ぶためのワゴンを岡部が押してくるところで、その上には「うむすび」のパッケージが山を模した形で積まれていた。周りには花飾りまで施されている。
「えー、このたび! 総料理長に監修いただきました『おはなのうむすび』が」と、波場はそこで言葉をためてから、つづけた。「柳川ブランドに認定されました!」
いよっ、と煽るような声を添えて波場は盛大な拍手を鳴らした。
「えー、柳川ブランドとは、これぞ柳川名物! と世界に高らかに宣言できる品だけに認められる、実に、実に厳しい審査を経て与えられる名誉! であります。御花といえば、せいろ蒸し、せいろ蒸しといえば、御花、というくらいですね、御花を代表する味を、お持ち帰り、さらには通販という形でお届けできるようになったのも、総料理長の尽力の賜物でありまして、おかげさまで発売以来、大好評なわけですが」
「長い!」と波場のスピーチを宗高社長が遮った。
その前日、ブランド認定の連絡をもらった直後に、三崎さんから社長に電話がかかってきた。「今年もおじゃまします」という挨拶の電話だったが、「うむすび」の吉報を社長はつい語ってしまい、すると三崎さんのほうから、そのお祝いもできませんか、と提案をいただいたのだという。
「じゃ、総料理長、一言!」
波場に促されて、河村は戸惑った。
「えー、あの、えー、ありがとうございます。うむすびは、えー、大勢の努力があって、私は、その、私のほうこそ、みんなに、ありがとうと言わなくてはならない、と、そう、思うのですが、えー、御花に来てから、十二年になりますが、その、みなさんに助けていただいてばかりで」
そこで、言葉に詰まった。
お客様のお祝いの席のはずなのに、どうして自分が祝福されているのか。
その戸惑いに、女将と会った晩の記憶が重なり、河村は、こう笑った。
「どうも、口が下手なもので」
みな、いっせいに笑った。
「じゃあ、記念撮影をしましょう」
岡部の言葉で、個室の窓側に、全員で並んだ。
三崎夫妻と宗高社長に挟まれる格好でまんなかに立ったとき、帽子を置いてきたことに気がついた河村は、花束を社長にあずけて厨房に急いだ。
従業員用通路を大股に進みながら、河村は、娘になんといって知らせようかと、たどたどしい言葉を頭の中で編みはじめていた。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。