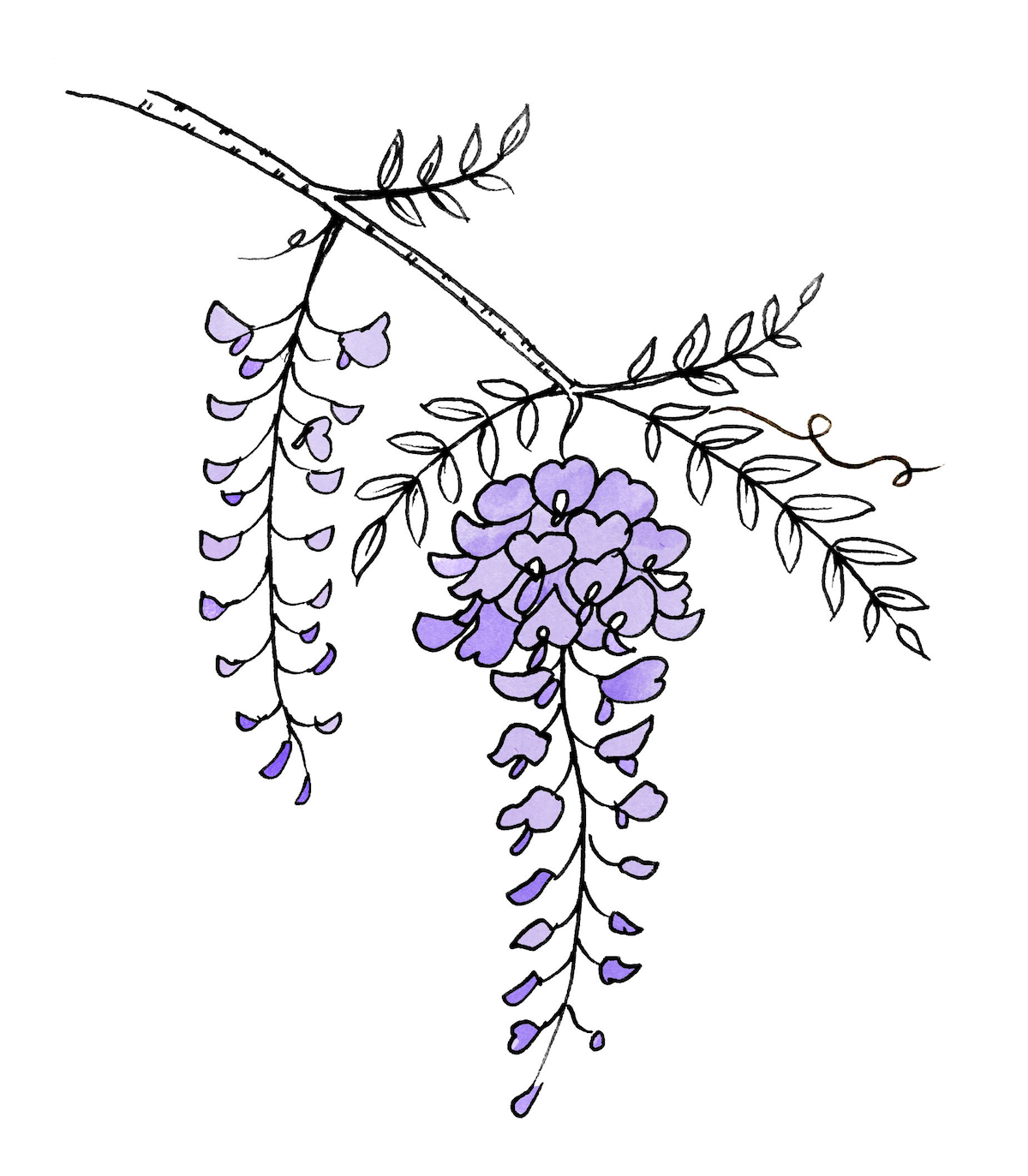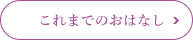「なに他人事みたいに言ってるんですか」
「えー、だって、そう思うもん。わたし、がんばらなくちゃ」
そのつぶやきに、喉元が熱くなりだした藤野は、自分が泣いてしまうのではないかと察知し、あわててさっきの紙を出した。
「そうだ、社長、これ、これを聞きたかったんですけど、この女の子、誰だかわかりませんか?」
「え? えー? いや、ごめん、わからないなー。なに、だれ、有名な子? わたしの知ってる子?」
「それがわからなくて。なんか、わたし、どこかで見た気がするんですけど、ひょっとして社長かなって。でも、あれですね、計算あわないですもんね」
「うーん、じゃあ妹かな」
社長が松濤館を振り返る。同じく御花で働く妹のことを思ってだろうと藤野は推測する。
「いやー、違うよねー。うちの妹、こんな顔じゃないもんなー。この服とか帽子も見たことないし。それに家族の写真だったら、そっちのアルバムには入らないと思うし。でもね、言われてみれば、確かに見たことある顔な気が、うーん。なんか思い出したら教えるね。ごめん、わたし、ちょっと急いでるから」
時計も見ずに社長はそう言って、正門から外へ出ていった。
思いがけず時間をとってしまったが、史料館のあとで対月館のテラスに立ってみようという初志を貫徹すべく、藤野も大股で歩き出した。
目的の場所に到着し、池庭を一望しながら、手元の写真と見比べてみる。しかし、頭は先刻の社長の言葉で埋め尽くされていた。「わたしたちも、もてなされてるみたい」という考えが、そこに立つと、ますます本当のこととして響いてきた。
ほんとうにそうだ、と藤野は目を細めて思う。
名も知らぬ紳士の言葉、カメラの構え方を褒めてもらえたこと、それに続く社長とのやりとり。
特別な予定などなかった一日だが、一連のできごとが、この先の自分に重要な意味を教えてくれるだろうことが予感された。
御花ってどんなところ?
ブログを書くときにたびたび頭をよぎる疑問。
思い出の生まれるところ、と藤野はいつからか定義している。
それが自分の指針だったが、しかし、お客様だけでなく、自分自身にも生まれるのだとは、考えていなかった。
午後は勤怠管理の取りまとめに集中し、そちらが片付くとお金の計算に移った。仕事でもっとも緊張する時間だ。計算が合わないと、ヒヤリとする。なるほど、確かに裏方もおもてなしの一部だ。
その日は午後六時きっかりに計算が終わり、金額は問題なく整合した。
「合いましたー」と向かいの細田に報告しながら両手をのばしていると、事務所のドアが開いて、社長が入ってきた。右手に季節はずれの麦わら帽子を持っている。
「藤野さん!」
なにやら必死な表情に気圧されながら、藤野は座ったまま「は、はい」と答える。
「笑って!」
言うやいなや、椅子に座ったままのけぞりそうな藤野の頭に、社長が麦わら帽子をかぶせた。
「え?」
「笑って! ほら、写真、さっきの写真!」
事態が飲み込めないまま、藤野はポケットの紙を取り出して社長に渡した。何事かという顔つきの細田が社長の隣にやってくる。
「ほら、早く、笑って!」
言われるまま、なんとか笑顔を作ろうとする。
「あ!」と細田が驚きの声をあげる。
「え、なんですか?」
顔をひきつらせながら藤野が尋ねる。
「ほら、藤野さん! 藤野さん!」
社長は印刷された写真を藤野に向けて訴えた。
細田が「これ、藤野さんの写真じゃないの? すごく、面影がある」と補足するように言った。
「え? え?」
「自分の子どものころの写真を間違って入れた、なんてことはないよね」
細田の台詞に社長が大笑いした。まさか、と藤野は思うが、言われてみれば自分の子どものころに、似ていなくもない。女の子が着ているワンピースにも、見覚えがあるような気がした。
社長に促されるまま実家に電話をかけると、定年退職して暇をしているという父が出た。
「優実か。元気か」
「うん、あのさ、わたしの勤務先だけど」
「ああ」
「ここ、もしかして、来たことある?」
「うん? ああ、家族で行っただろう」
今度は本当にのけぞった。その様子で、社長と細田は理解したのだろう。間近で「やっぱり!」と手を叩かれる。
父が言うには、藤野が三歳になるかならないかのころ、福岡の友人に招かれて家族旅行に出かけた折、御花にも立ち寄ったのだという。すごく良くしていただいたので、御礼の手紙とともに写真も送ったはずだ、と。
そこで勤めることは伝えていたのだから、そのときに思い出話のひとつでもしてくれてもよかったじゃないかと訴えたが、父はひとこと「覚えているかと思った」と言った。
デスクに置かれた、折り目のついた写真の中、テラスの椅子で大笑いする小さな子は、どこまでも幸せそうだった。
ふう、とひといき入れてから、藤野は頬をほころばせた。
「あのさ、父さん、もし暇だったらさ、こんど、こっちにおいでよ」と提案してみた。「わたしの職場、見てほしいしさ。ちゃんとおもてなしするから」
「御花か」と父が電話口でささやく。
相変わらず疲れた顔をしているのだろうか。それとも、仕事に追われる日々から抜けて、穏やかに過ごしているだろうか。久しく会えていない父を、自分の勤務先に招き、そこで写真に納める未来を想像した。
「どんなところだ?」と父が確かめるように訊いた。
答えは、決まっていた。
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。