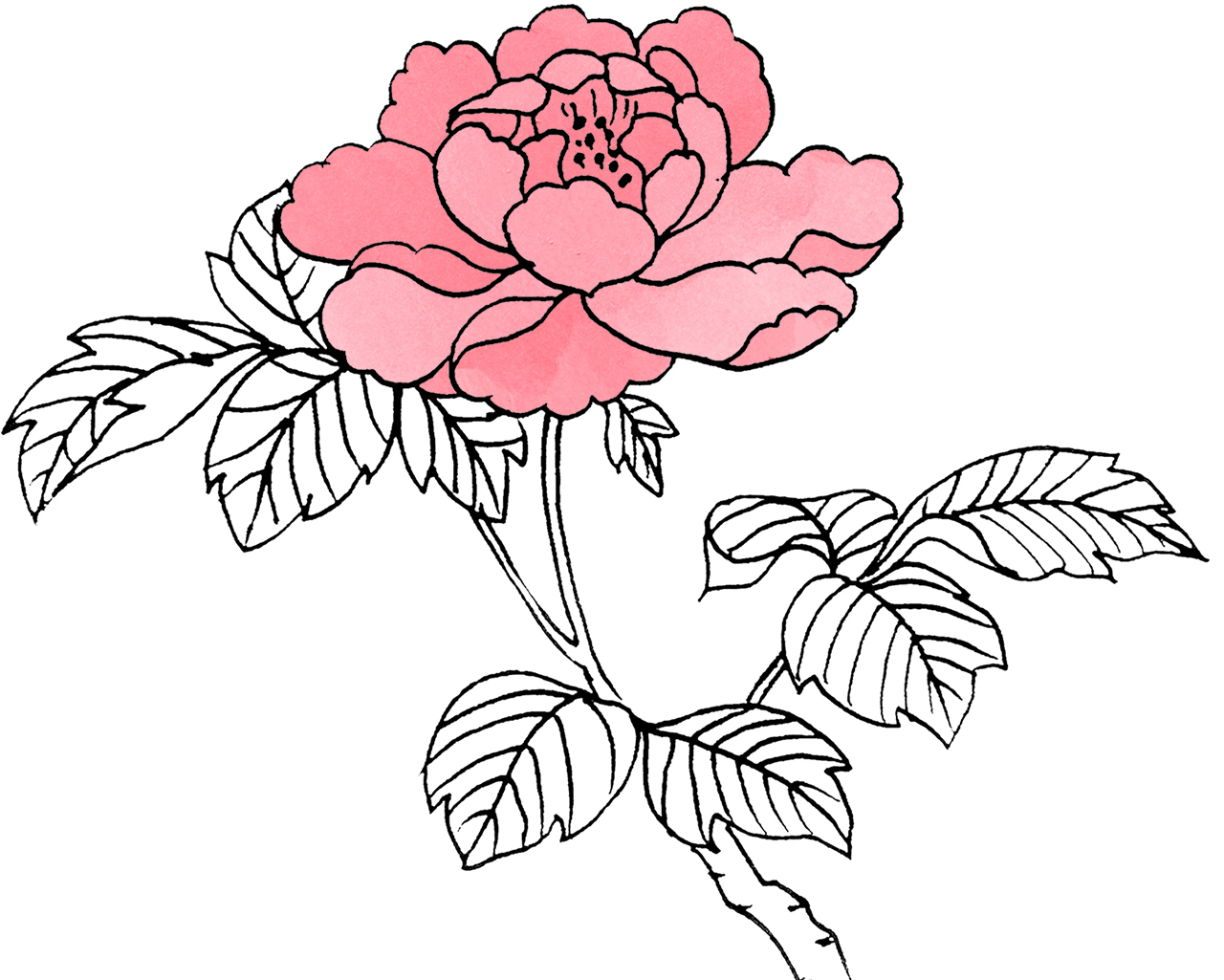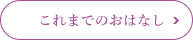「そんなんどうでもいいし、わたしの真似なんかしないで、さっさと自立してくれないとほんと困るし、ていうか、わたしもおねえちゃんほしかった」
しゃべるほど、一花の表情に幼さが透けてくるようで、結月はほっとした。
「いいじゃないの、妹さんいるだけで、わたしなんか一人っ子だよ」
やれやれ、といった調子で葵が言った。
「じゃあさ」と結月が提案した。「私がおねえちゃんってことで、どう?」
「は?」
「一花ちゃんのおねえちゃんで、東京から、福岡に就職してきてるって設定で」
「なにそれ。意味ないじゃん、すぐ帰るんだし」
「いいじゃない。離れても家族でしょ。私も妹ほしかったし。ね。家族で姉の働きぶりを確かめに、今日、ここに訪れてるってことにして。ランチの予約も入ってるんだし」
「ランチ?」
理解できない、という様子の一花を前に、葵が「そうだ! 一花ちゃんですね!」と声をあげた。
「そう。東京から来たって聞いて、今日のお客様のこと思い出したの」
結月のその言葉に確証を得た葵は、抑えきれないふうに口走った。
「一花ちゃんのパパとママね、ここでとっておきのランチを食べさせたいって、娘の誕生日だからって、電話で何度も打ち合わせしてて。あんまり言うとネタバレだけど、すっごいんだよ」
「葵ちゃん、しゃべりすぎ」
結月の指摘に葵は、すみません、と自分の手で口をふさいだ。
「だから、ほら、ご家族のところにもどらないと」
結月はテーブルの上で一花の手をにぎった。
さっきまでの鋭さとは打って変わって、一花は、うろたえるように言った。
「でもわたし、あんな派手に逃げ出してきて、謝るとか、できない」
「おねえちゃんがいっしょに謝ってあげようか」
「え、なんか楽しそうでずるいです。わたしも、わたしも妹ほしかったから、おねえちゃんになります!」
すべりこむように葵が宣言した。
「なあに、そしたら葵ちゃんも私の妹になるの?」
一拍おいて、三人は笑った。
御花を辞めることについて、その日、葵と話す機会はなかった。
休憩時間に姉の千鶴がハガキを一枚持ってきた。いまでは有名な写真家となった田尻からの、新年の挨拶で、それもまた、結月の記憶を蘇らせるきっかけとなった。
東京の料亭で働いていたとき、姉が訪ねてきたことがある。田尻の個展を見るため上京した、そのついでだと姉は言っていたが、結月の働きぶりを見て、すごいね、と褒めてくれた。こんなにたくさんの人を笑顔にしてるんだね、と。
翌日、結月と千鶴はふたりで銀座のギャラリーを訪ねた。壁に並んだ作品のひとつに、出逢い橋で撮られた結月の姿があった。
僕にとっては、結月さんが座敷わらしだったのかもしれないですね。白髪まじりになった田尻はおだやかに笑った。
「ですよね」と千鶴は臆面もなく同意した。
「この子、東京でもすごいがんばってて、どこに行ってもたくさんの人を笑顔にしてるんです。みんなの座敷わらしで、だけど私にとっては自慢の妹なんですよ」
ああ、そうか、とハガキを手に、結月は理解した。
葵を見送らなくてはならない、そのさみしさは、さみしさではなくて、誇らしさなのだ。
自慢の妹を送り出すような、心配だけど、期待のほうが、応援のほうが、勝ってしまう、そんな気持ちだ。
結月は立ち上がり、深く息を吸い込んでから、仕事に戻った。
葵と働く残り時間を悔いなく過ごそうと、心に決めながら。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。