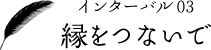
「なにか、書いて帰りませんか」
窓辺の椅子から外を眺めている夫に、節子は声をかけた。
朝の六時過ぎだが、節子も、善之も、自分の服に着替え、お茶を一杯ずつ飲み終えていた。先週までなら、ランチの仕込みに取り掛かる時間だった。
「ねえ、おとうさん」
善之は返事をかえさない。しかたないわね、という笑顔を浮かべて節子は、宿泊客が旅の思い出を書き残すためのノートに、視線をもどした。
——ずっと御花に来てみたくて、夢がかないました!
——息子が連れてきてくれました。おかげさまで、楽しい一日を過ごすことができました。
——二十年ぶりの宿泊、満喫させていただきました。
ノートには、感謝の言葉が多く並んでいる。押し花みたいに、いつまでも枯れない、喜びの文章。節子も似た感想を綴りたかったが、なにを、どう書けばいいか、考えはじめると、ペン先が行き場を見失った。誰の人生だって嬉しい瞬間ばかりじゃない。そんな拗ねた意見まで、頭に寄りかかってくる。七十年も生きれば、それくらいわかる。素晴らしい観光地、一流の宿でも、日常のすべてを忘れさせてはくれない。
——部屋から花火が見え、とても良い思い出になりました。
ページをめくるとそんな記述に出くわし、節子は窓の外に目をやった。三月早朝の空はうすく晴れているが、花火はもちろん、桜の花もまだ、季節ではない。旅の楽しさを噛みしめるほど、喜ばしいことが、この先、どれほどあるものか、つい、考えてしまう。ゆっくり過ごす朝に、慣れていないせいだ。
夫とふたりで三十五年、東京の片隅で切り盛りしてきた定食屋を、前の週にたたんだばかりだった。人生のきっかり半分を注いだ、人生そのものと呼べる店だった。
旅行らしい旅行に出かけることもなかった。一人娘には悪いことをしたと思う。勤め人とちがい、週末はおろか、盆暮れ正月にもろくに休まなかった。いつかわかってくれる。そう、善之は言っていた。
長じて娘は旅行代理店に就職し、子供時代への逆襲みたいに世界中を飛びまわるようになった。パスポートをスタンプで埋め尽くして、しまいには、フランスに嫁いでいった。
「フランスじゃ『嫁ぐ』なんて考え方、しないよ」と娘は笑った。よそがどうかは関係ない。そう夫が諭してくれたのが、節子にはありがたかった。
旅行は縁結び、とは娘の勤め先の社訓だったが、だからといって国際結婚とは。
およそ一年前、店を一週間休みにして、節子と善之もフランスへ渡った。不慣れな旅行、初めての海外では面食らうことばかりで、娘の流暢な案内に驚くあまり、我が子に敬語で感謝を述べる始末だった。結婚式も美術館も、とても現実と思えなかった。
善之は、店を休んだことをいつまでも気にかけていた。修行時代を含めれば五十年、料理ひとすじに生きてきた善之が、娘の結婚式のために初めて、長い休みを取った。あれが決定打になったのだと、節子は理解している。帰国して、店をたたむ話を夫婦で重ねるようになった。休んだことで気が抜けた、といえば、そうかもしれない。七十なら、キリもいい。娘が嫁いだことで、肩の荷がおりた気もしていた。とっくに独り立ちしていたものの、直行便で十三時間も離れたところへ行かれてしまっては、店を継ぐ可能性も消えた。最初から、ないも同然の可能性だったが、とうとう、飲み込めた。
「ちょっと、散歩してきます」
ノートをたたんだ節子は、洗面所で簡単な化粧をほどこしてから外に出た。メイクのあいだに夫の気がかわって、いっしょに歩くと言ってくれないかと想像してはみたが、そんな人でないのは百も承知だった。
エレベーターで一階に降り、若いスタッフと挨拶を交わして外に出た。寒さに、ダウンジャケットの前をとじた。
建物の裏側をまわって庭に出た。すこし歩いた先に見える橋が「出逢い橋」という名だと、前の日に散策しているときに、通りかかった男性スタッフが教えてくれた。四十半ばといった風貌で、ベテランホテルマンという印象を節子は持ったが、御花にきて五年に満たないという。
東京でマスコミ関係の仕事をしていて、こちらに嫁いできたのだと彼は笑った。「婿養子なんです」という話だった。ご旅行ですか、と問われて、娘からのプレゼントで、と節子は答えた。飲食店をたたみ、その労いとして、フランスに暮らす娘が予約してくれたのだと。
「海外からも予約できる時代なんですね」と節子はすこし悲しげに言った。
どんなお店をやっていたんですかと、スタッフの男は質問した。節子が店名と所在地を告げると、「うかがったことあります、アジフライ! 大好きだったなあ!」と感激した様子で握手を求めてきた。いえ、店主はあちらです。池を眺めていた夫を示すと、彼はそちらに歩み寄っていって、善之と力強い握手を交わしていた。
縁というのはどこまでもつながるものだと、前日のことを思い返しながら、節子は頬をほころばせた。
近隣からの客ばかりだった定食屋にも、ここ五、六年は海外からの客が増え、そういう時代ですかね、と夫婦で語り合っていたが、ひさしぶりに帰国した娘が、世界中で実家の宣伝をしているのだと打ち明けた。それならそうと言ってくれたらサービスするのにと残念がる母を、娘は「いいのいいの」と気にかけなかった。両親は忙しいし、外国の人にも馴れてないから、料理だけしっかり味わってきてね、と皆に言ってあるのだそうだ。
「ほら、私もさ、この店の一員でしょ」と照れるように言った娘の表情を思い返しながら、節子は背後の建物を振り返った。自分たちの泊まった部屋の窓に目をやるが、夫の姿は見当たらない。
店の一員と言いつつ、パリで仕事に就いた娘はろくに休みをとれなくなり、店の最後の営業日にも帰国できないと謝ってきて、罪滅ぼしのつもりか、柳川への旅行を手配してくれた。自分は行ったことがないが、海外の友人の熱烈な推薦だと。
——おとうさんと、おかあさんと、ふたりの営んだお店が、私を育ててくれました。ほんとうに、ありがとう。
チケットに添えられた手紙を、店の記録を綴ったノートの最後に節子はしまった。
旅行らしい旅行など、人生で初めてかもしれない。なにを持っていけばいいかもわからず、荷物がふくらんだ。娘が見れば呆れるに違いない。身近にいれば、プロの荷造り術を披露してくれただろう。「休みもとれない人生なんて意味ないじゃん」とかつて怒鳴り散らした娘が、いまや仕事漬けの人生を謳歌しているのが、おかしく思えることもある。
旅行は縁結び。
人のいない橋の上でお堀の水面を眺めながら節子は、その言葉を思い出した。人と人だけじゃなく、人と場所、人と時代、人と瞬間、そんなふうに誰かが何かとの縁を新たに結ぶこと。それが旅なのだと。
「定食屋だってそうだ」と善之が負けず嫌いを発揮した場面を思い出しても、節子は笑ってしまう。定食は縁結び、では様にならない。でも、あながち、まちがってもいない。昨日の男性とも、善之の料理がひとつの縁となったのだ。
ここも、そうなのだろう。ノートに書かれた沢山の言葉。そのすべてが、縁の賜物なのだ。
出逢い橋から節子は、もう一度、建物を振り返った。一晩を過ごしただけの場所が、もう、一生の思い出になりつつあることを感じた。窓からの景色、心のこもったもてなし。いつまでもおぼえておきたいことが、いくつも浮かんできた。前の晩にいただいた夕食も、そのひとつだ。おいしいものを、ただおいしく食べられることの喜びを、どれほど長いあいだ自分たち夫婦は封じ込めていたのか。ついそんなことを考え、せっかくの旅を素直に楽しめない自分を笑った。
でもこれで、と節子は顔をあげた。この場所と、縁がつながった。いつかまた、来るのもいいかもしれない。ノートにも、二度目、三度目の宿泊だと書いていた人が、たくさんいた。隠居生活にも慣れて、旅も上手になったら、こんどは娘もつれてこよう。
部屋に戻ると、善之は窓辺の椅子で静かに眠っていた。節子はボールペンのキャップをはずし、散歩で浮かんだ言葉を残していこうと、ノートをめくった。すると、さっきまでなかった文字が加わっていた。よく知っている、夫の筆跡で、こう書かれていた。
すばらしいお料理、行き届いた心配り、思いがけない再会を、ありがとうございました。
こんどは、娘夫婦といっしょにうかがいます。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。

「なにか、書いて帰りませんか」
窓辺の椅子から外を眺めている夫に、節子は声をかけた。
朝の六時過ぎだが、節子も、善之も、自分の服に着替え、お茶を一杯ずつ飲み終えていた。先週までなら、ランチの仕込みに取り掛かる時間だった。
「ねえ、おとうさん」
善之は返事をかえさない。しかたないわね、という笑顔を浮かべて節子は、宿泊客が旅の思い出を書き残すためのノートに、視線をもどした。
——ずっと御花に来てみたくて、夢がかないました!
——息子が連れてきてくれました。おかげさまで、楽しい一日を過ごすことができました。
——二十年ぶりの宿泊、満喫させていただきました。
ノートには、感謝の言葉が多く並んでいる。押し花みたいに、いつまでも枯れない、喜びの文章。節子も似た感想を綴りたかったが、なにを、どう書けばいいか、考えはじめると、ペン先が行き場を見失った。誰の人生だって嬉しい瞬間ばかりじゃない。そんな拗ねた意見まで、頭に寄りかかってくる。七十年も生きれば、それくらいわかる。素晴らしい観光地、一流の宿でも、日常のすべてを忘れさせてはくれない。
——部屋から花火が見え、とても良い思い出になりました。
ページをめくるとそんな記述に出くわし、節子は窓の外に目をやった。三月早朝の空はうすく晴れているが、花火はもちろん、桜の花もまだ、季節ではない。旅の楽しさを噛みしめるほど、喜ばしいことが、この先、どれほどあるものか、つい、考えてしまう。ゆっくり過ごす朝に、慣れていないせいだ。
夫とふたりで三十五年、東京の片隅で切り盛りしてきた定食屋を、前の週にたたんだばかりだった。人生のきっかり半分を注いだ、人生そのものと呼べる店だった。
旅行らしい旅行に出かけることもなかった。一人娘には悪いことをしたと思う。勤め人とちがい、週末はおろか、盆暮れ正月にもろくに休まなかった。いつかわかってくれる。そう、善之は言っていた。
長じて娘は旅行代理店に就職し、子供時代への逆襲みたいに世界中を飛びまわるようになった。パスポートをスタンプで埋め尽くして、しまいには、フランスに嫁いでいった。
「フランスじゃ『嫁ぐ』なんて考え方、しないよ」と娘は笑った。よそがどうかは関係ない。そう夫が諭してくれたのが、節子にはありがたかった。
旅行は縁結び、とは娘の勤め先の社訓だったが、だからといって国際結婚とは。
およそ一年前、店を一週間休みにして、節子と善之もフランスへ渡った。不慣れな旅行、初めての海外では面食らうことばかりで、娘の流暢な案内に驚くあまり、我が子に敬語で感謝を述べる始末だった。結婚式も美術館も、とても現実と思えなかった。
善之は、店を休んだことをいつまでも気にかけていた。修行時代を含めれば五十年、料理ひとすじに生きてきた善之が、娘の結婚式のために初めて、長い休みを取った。あれが決定打になったのだと、節子は理解している。帰国して、店をたたむ話を夫婦で重ねるようになった。休んだことで気が抜けた、といえば、そうかもしれない。七十なら、キリもいい。娘が嫁いだことで、肩の荷がおりた気もしていた。とっくに独り立ちしていたものの、直行便で十三時間も離れたところへ行かれてしまっては、店を継ぐ可能性も消えた。最初から、ないも同然の可能性だったが、とうとう、飲み込めた。
「ちょっと、散歩してきます」
ノートをたたんだ節子は、洗面所で簡単な化粧をほどこしてから外に出た。メイクのあいだに夫の気がかわって、いっしょに歩くと言ってくれないかと想像してはみたが、そんな人でないのは百も承知だった。
エレベーターで一階に降り、若いスタッフと挨拶を交わして外に出た。寒さに、ダウンジャケットの前をとじた。
建物の裏側をまわって庭に出た。すこし歩いた先に見える橋が「出逢い橋」という名だと、前の日に散策しているときに、通りかかった男性スタッフが教えてくれた。四十半ばといった風貌で、ベテランホテルマンという印象を節子は持ったが、御花にきて五年に満たないという。
東京でマスコミ関係の仕事をしていて、こちらに嫁いできたのだと彼は笑った。「婿養子なんです」という話だった。ご旅行ですか、と問われて、娘からのプレゼントで、と節子は答えた。飲食店をたたみ、その労いとして、フランスに暮らす娘が予約してくれたのだと。
「海外からも予約できる時代なんですね」と節子はすこし悲しげに言った。
どんなお店をやっていたんですかと、スタッフの男は質問した。節子が店名と所在地を告げると、「うかがったことあります、アジフライ! 大好きだったなあ!」と感激した様子で握手を求めてきた。いえ、店主はあちらです。池を眺めていた夫を示すと、彼はそちらに歩み寄っていって、善之と力強い握手を交わしていた。
縁というのはどこまでもつながるものだと、前日のことを思い返しながら、節子は頬をほころばせた。
近隣からの客ばかりだった定食屋にも、ここ五、六年は海外からの客が増え、そういう時代ですかね、と夫婦で語り合っていたが、ひさしぶりに帰国した娘が、世界中で実家の宣伝をしているのだと打ち明けた。それならそうと言ってくれたらサービスするのにと残念がる母を、娘は「いいのいいの」と気にかけなかった。両親は忙しいし、外国の人にも馴れてないから、料理だけしっかり味わってきてね、と皆に言ってあるのだそうだ。
「ほら、私もさ、この店の一員でしょ」と照れるように言った娘の表情を思い返しながら、節子は背後の建物を振り返った。自分たちの泊まった部屋の窓に目をやるが、夫の姿は見当たらない。
店の一員と言いつつ、パリで仕事に就いた娘はろくに休みをとれなくなり、店の最後の営業日にも帰国できないと謝ってきて、罪滅ぼしのつもりか、柳川への旅行を手配してくれた。自分は行ったことがないが、海外の友人の熱烈な推薦だと。
——おとうさんと、おかあさんと、ふたりの営んだお店が、私を育ててくれました。ほんとうに、ありがとう。
チケットに添えられた手紙を、店の記録を綴ったノートの最後に節子はしまった。
旅行らしい旅行など、人生で初めてかもしれない。なにを持っていけばいいかもわからず、荷物がふくらんだ。娘が見れば呆れるに違いない。身近にいれば、プロの荷造り術を披露してくれただろう。「休みもとれない人生なんて意味ないじゃん」とかつて怒鳴り散らした娘が、いまや仕事漬けの人生を謳歌しているのが、おかしく思えることもある。
旅行は縁結び。
人のいない橋の上でお堀の水面を眺めながら節子は、その言葉を思い出した。人と人だけじゃなく、人と場所、人と時代、人と瞬間、そんなふうに誰かが何かとの縁を新たに結ぶこと。それが旅なのだと。
「定食屋だってそうだ」と善之が負けず嫌いを発揮した場面を思い出しても、節子は笑ってしまう。定食は縁結び、では様にならない。でも、あながち、まちがってもいない。昨日の男性とも、善之の料理がひとつの縁となったのだ。
ここも、そうなのだろう。ノートに書かれた沢山の言葉。そのすべてが、縁の賜物なのだ。
出逢い橋から節子は、もう一度、建物を振り返った。一晩を過ごしただけの場所が、もう、一生の思い出になりつつあることを感じた。窓からの景色、心のこもったもてなし。いつまでもおぼえておきたいことが、いくつも浮かんできた。前の晩にいただいた夕食も、そのひとつだ。おいしいものを、ただおいしく食べられることの喜びを、どれほど長いあいだ自分たち夫婦は封じ込めていたのか。ついそんなことを考え、せっかくの旅を素直に楽しめない自分を笑った。
でもこれで、と節子は顔をあげた。この場所と、縁がつながった。いつかまた、来るのもいいかもしれない。ノートにも、二度目、三度目の宿泊だと書いていた人が、たくさんいた。隠居生活にも慣れて、旅も上手になったら、こんどは娘もつれてこよう。
部屋に戻ると、善之は窓辺の椅子で静かに眠っていた。節子はボールペンのキャップをはずし、散歩で浮かんだ言葉を残していこうと、ノートをめくった。すると、さっきまでなかった文字が加わっていた。よく知っている、夫の筆跡で、こう書かれていた。
すばらしいお料理、行き届いた心配り、思いがけない再会を、ありがとうございました。
こんどは、娘夫婦といっしょにうかがいます。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
