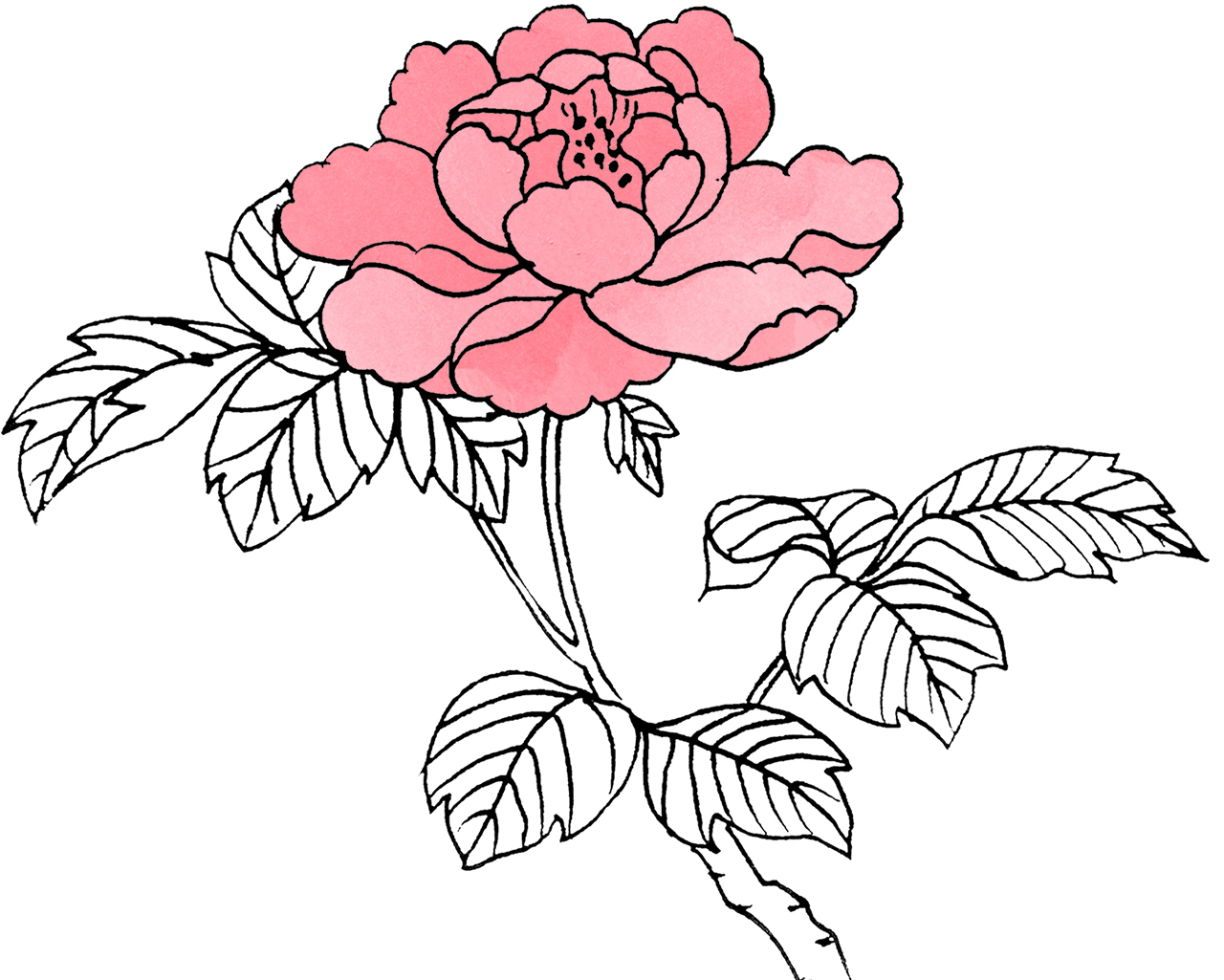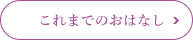「ああ、うん、それはどちらかというと、マルゲリータだね」
「あ、あれですね、花にありました。マルガリータ。えっと、ヒナギク」
「へえ、よく知ってるね」
「前に花屋でバイトしてて」
「そう、ヒナギク。だいたいどのカクテルにも物語があってね、マルガリータは、段取りを間違った結果、生まれたものなんだ」
「そうなんですか」
「もともとは、デイジーという名前のカクテルがあった」
「あ、デイジーもヒナギクですよ、たしか」
「そのとおり」
ふたりは同じタイミングでグラスを持ち上げ、それぞれに一口飲んだ。
デイジーは1870年代に誕生したと言われている、ウィスキーベースのカクテルだ。
時代がくだって1920年代のこと。メキシコにヘンリー・マッデンというバーテンダーがいた。ある日、客の一人がデイジーを注文した。ところが、忙しかったのか、なにか考え事でもしていたのか、バーテンとしてはあるまじきミスをおかした。
「ウィスキーとテキーラのボトルを間違って、手に持ってしまったんだって」
「マジすか」
「でも、できあがったカクテルを、客はたいそう喜んで、おかわりまで頼んだ。それがきっかけで、あっというまにその新カクテルはメキシコ全土に広まって、世界が知るところになった。ちなみに、スペイン語でヒナギクのことをマルガリータって言うらしい」
瀬ノ元の説明を聞いているのか、いないのか、鈴木はほとんどからになったグラスをじっと見つめていた。
「そうはいっても、これは割と新しい説でね、そもそもウィスキーとテキーラのボトルを間違うかなっていう疑問がある。もっと有名なのだと、1949年にロサンゼルスのバーテンダーが考案したっていうのもあって、コンテストで入選したことで広く知られるようになったって言われてるんだけど、この説だとバーテンダーの死んだ恋人の名前がマルガリータだった」
「どっちが本当か、わかんないんですか」
問われて瀬ノ元は、もったいつけるように、自分のグラスの残りを飲み干してから答えた。
「どっちが本当か、なんて気にしなくていいってことじゃないかな」
瀬ノ元の発言に、鈴木はまた、口をぽかんと開けた。
「カクテルの逸話は枚挙にいとまがない。嘘も本当もいろいろある。共通してるのは、その逸話よりずっとたくさんの失敗談が、あるはずだってことだと僕は思う」
カクテルグラスをテーブルに置いて、短く息を吐くあいだ、瀬ノ元は思った。記録にも、記憶にも残らない、無数の、ささやかな失敗のことを。そんな失敗たちをつないで行き着く先にしか、なしえないことが、あるのだろう。だとすれば、すべてのミスが、成功への段取りになる。
物思いにふけっていると、瀬ノ元のスマートフォンが着信音を鳴らした。ごめん、と鈴木に謝ってから電話に出た。
「あ、はい、申し訳ありません、いま、対月館のほうにいて、はい、いえ、あ、いや、そんな、え、はい、では、お待ちしております」
電話を切ると、鈴木が自信なさげに確かめてきた。
「さっきの話、失敗があるから、ってことですよね?」
「まあ、そうだね。僕もここで働きはじめたころは、毎日ぼろぼろだった。失敗もしたし、テーブルや椅子を運ぶのにへとへとにもなった。でも、失敗ってさ、ただ手順を教わるよりも、なんていうか、栄養価が高い気がするんだ」
言ってから、瀬ノ元はホールを見渡した。つられるように、鈴木もぐるりと首をめぐらせた。
「やあ、見つけたぞ」
堂々とした声がホールに響きわたった。瀬ノ元と鈴木が入口を向くと、そこに背の高い老人がひとり立っていた。仕立ての良いスーツを着て、左手には黒いコートを掛けている。綺麗な禿頭で、人懐っこい少年のような笑みをたたえたまま、瀬ノ元たちの方へ近づいてきた。
瀬ノ元が立ち上がりながら「高木さん、おまたせして申し訳ありません」と頭をさげた。
「いやいや、仕事だろう?」
「こちら、アルバイトの鈴木くんです」
「邪魔して申し訳ないね。教育の最中だったかな。それにしてはお酒を飲んでいる。私を抜きに始めてたわけか」
「いえ、そんな」と瀬ノ元がしどろもどろに説明を試みるが、老人はほがらかな笑いでそれを制した。
「冗談だよ。でもせっかくだから、私もマルガリータを頼めるかな」
かしこまりました、と応じて、瀬ノ元はバックヤードへ向かった。
新しいカクテルグラスを用意していると、高木が鈴木に話しかけている声が、ちいさく聞こえてきた。
——バイトはどれくらいですか。
——三日目です。
——まだ慣れないね。
——そうなんです、今日もミスして、それで瀬ノ元さんが気を使ってくれて。
はっはっは、という、高木の堂々とした声だ。
——私が初めて御花に来たとき、瀬ノ元くんがポカをやらかしてね。
——あ、高木さんってもしかして、あれですか、退職祝いの。
——そう。聞いたのか。
——つい、さっき。
——謝罪に来てくれたのだが、どうにも許せなくてね、しばらく門前払いを食らわせていた。しかしね、なにかの折に、ここへ来る用事ができた。そこでしっかりと働いている瀬ノ元くんの姿を見かけてね。芯の弱そうな青年に見えたから、辞めたんじゃないかと思っていた。でも、その点については私が間違っていたわけで、ほっとしたんだよ。
カクテルを作るはずの瀬ノ元の手は止まっていた。高木が「ほっとした」というのは、初耳だった。
——それでまあ、応援してやろうかと思ったわけだが、会うたびに小言をあれこれ言ってね。挨拶の声が小さいんじゃないのか、とか、そんなことを。それが、去年だったかな、私の後輩のパーティを仕切らせてみたら、難なくこなしてね。ちくしょう、私のパーティのときにそうであればよかったのに。まあ、しかし、済んだことだ。それから彼とふたりで飲むようになって、今日もこれから、一杯行く約束なんだ。
胸が熱くなるのを、瀬ノ元は感じた。その熱は、いまにも目元までこみあげてきそうだった。
いけない、早くカクテルを作ってもっていかなくては。
焦る気持ちで、棚のボトルに手をのばし、シェイカーに酒を注ごうとした。
見ると、手に持っているのはテキーラではなく、ウィスキーのボトルだった。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。