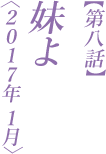
十年間、おつかれさまでした。
私が葵ちゃんと働けたのは三年と少しで、だけどもっと長い時間を、ともに過ごせた気がしています。
手紙なんて、ずいぶん長いこと書いていなくて、言いたいことがうまく書けるかどうか、自信がありません。
自信がない、といえば、御花で働くようになって、はじめて弱音を漏らした相手が、葵ちゃんでした。私のほうがずっと年上なのに、あのときは、話を聞いてくれて、ほんとうに――
そこまで書いてから、結月は机にペンを置いた。
ありがとう、と続けるつもりだったが、その言葉を文字にしてしまうと、たいせつにしていたものがほどけて、もとに戻らなくなる気がした。
親しくしていたスタッフが御花を去っていく。
それだって、初めての経験というわけではない。ないのだが、これまでに味わったことのないさみしさが、胸にわだかまっていた。別れの辛さともちがう、不穏さを帯びたさみしさだった。
葵に退職の意向を知らされたのは、前の晩のこと。帰り際に本人から呼び止められ、内緒話のように告げられた。辞める理由は前向きなものだった。とはいえ、あまりに予想外の話で、ほんとうはなにか問題や悩みがあるのではと、結月はしつこいくらいに質問した。帰宅したあとも、なかなか寝つけなかった。手紙を書けば落ち着くのではと、冬の長い夜が明けきらないうちにベッドを出て、ペンをとったが、うまくいかなかった。
書きかけの便箋をまるめて捨てた結月は、普段よりもずいぶん早くに自宅を出た。
御花に到着して仕事用の和服に着替えたが、始業時間まで三十分以上あった。厨房では仕込みが始まっていたものの、自分に手伝えることはなく、館内にごみが落ちていないか確かめようと考え、エレベーターで四階まであがった。宿泊のお客様のための部屋があるフロアだが、その日、だれも泊まっていないことはわかっていた。
エレベーターを降りて、長くはない廊下を行き止まりまで進んで気がついた。
ひとりになりたかったのだと。
ところが、静寂はすぐにやぶられた。
「おねえさん」
背後から声が響いてきた。振り返ると、少女がひとり、立っている。
背は低いものの、顔立ちは洗練されて大人っぽい。十五、六歳か。ブルーのニットキャップ。チョコレート色のダウンジャケットで、袖は指の中ほどまで覆っている。スキニータイプのジーンズに、ハイカットの白いスニーカー。
「どこか隠れられる場所ない?」
少女は、追手がこないか確かめるそぶりで廊下を振り返った。
「あの、見学のお客様でしょうか?」
平静を装って、確かめてみた。少女は結月に向き直った。ちいさな顔だが、目がするどくて、強い。ひとこと「ちがう」と答えるや、結月を見限るように彼女は踵を返した。しなやかに走って廊下を曲がって姿が見えなくなり、足音もすぐに消えた。あざやかな振る舞いは、現実のものと思えなかった。
座敷わらし。
ひさしぶりに、その名が頭に浮かぶと同時に、懐かしい記憶がよみがえってきた。
結月は宗高家の末っ子として生まれた。
男兄弟がおらず、いずれは姉が婿を迎えて後を継ぐのだというような話を、いつのころからか、自明のこととして受け入れていた。宗高家が由緒ある血筋であることも内外から聞かされて育ったが、自分がその一員だとは感じなかった。
小学生になり、二年生、三年生と学年をのぼっていくにつれ、どうやら面倒な立場にいるようだと自覚しはじめた。「宗高結月」である前に「御花の娘」としてあつかわれることが、少なくなかったためだ。外での振る舞いや言葉遣い、食事の作法など、特に祖母には厳しく躾けられた。給食の時間にパンをちぎって投げる男子や体育の時間に堂々とあぐらをかく女子を眺めながら、どこかで羨む気持ちを持っていた。
姉の千鶴は、中学生になると、和服を着て御花の手伝いに出るようになった。スタッフばかりか、お客様ともよくおしゃべりをしており、時代劇で見る若姫様といった印象が日に日に強まっていった。少し前までは姉妹で館内を駆けまわり、だれがいようとおかまいなしに鬼ごっこや隠れんぼで競っていたのに、姉にとって御花は「働く場所」になったようだった。
「結月もいっしょに、ここを、もっといい場所にしていこうよ」
遊ぼう、と誘ったのに、諭されるようなことが何度か続いて、結月は外の友達を頼るようになっていった。高校生になると、できるだけ早くここから出ていきたいと明言する友人が増えていった。
博多に。
東京に。
海外に。
みんな、柳川を愛していないわけではなかったものの、外へのあこがれは、おさえようもなく膨らんだ。
あとになってみれば、そうした記憶のどれもこれもに、青臭さが感じられる。はっきりとした目標を掲げる友人もいたが、結月のあこがれは、どこかへ行きたいという熱意より、ここを離れてみたいという気持ちに根を張っていた。それではどこにも行けないのだと、わかりはじめてもいた。自分なりの道を見つけないことには、どこにも。
転機は、高校二年の七月に訪れた。
東京からカメラマンが来ていると聞いた結月は、撮影や取材が楽しそうなら、そっちの道を歩んでみるのもいいかもしれないと考え、制服のまま大広間に向かった。若いカメラマンを見つけたが、姉もいっしょで、あれこれ質問できる雰囲気ではなかった。どうしたものかと思案していると、カメラマンのほうが質問してきた。
座敷わらしを見たことはあるか、と。
幼いころに着物で遊んでいて、座敷わらしみたいだと評されたことがあった。そのことではないかと結月は答えたものの、結局のところなんの話かわからず、その場をあとにした。
御花の近くに建てられた自宅へ戻ると、母におつかいを頼まれて、制服のまま外へ出た。お堀にかかった「出逢い橋」をわたっていると、さっきのカメラマンがやってくるところで、あちらから会釈された。田尻、と彼は名乗った。
「すみません、さきほどは、妙な質問をして」
「いえ、こちらこそ。お役に立てなくて」
結月も社交辞令とともに頭をさげた。すると田尻はなにか思いついた様子で、こう言った。
「じゃあ、役に立っていただけませんか?」
個人的な作品づくりを行っているので、ここで何枚か撮らせてもらえないか、という相談だった。
撮影時間は十五分足らずだった。田尻はカメラを構えてシャッターを切りながら、雑談をつづけた。いま携わっている仕事が一段落したら、半年ほどかけて、いくつかの国を渡り歩く予定なのだという。インド、アラスカ、バリ、地中海の国をふたつかみっつ。世界地図を思い描かずとも、めちゃくちゃな旅程であることはあきらかで、結月は笑った。
「行きたいところ選んだら、そうなるんです」と、田尻は当然のことのように言った。池に石を投げれば波紋ができるんです、とでもいうように。
そういう生き方もあるんだ。
柳川の高校生であり、御花の娘だった結月に、彼の人生観は強烈な一撃となった。

十年間、おつかれさまでした。
私が葵ちゃんと働けたのは三年と少しで、だけどもっと長い時間を、ともに過ごせた気がしています。
手紙なんて、ずいぶん長いこと書いていなくて、言いたいことがうまく書けるかどうか、自信がありません。
自信がない、といえば、御花で働くようになって、はじめて弱音を漏らした相手が、葵ちゃんでした。私のほうがずっと年上なのに、あのときは、話を聞いてくれて、ほんとうに――
そこまで書いてから、結月は机にペンを置いた。
ありがとう、と続けるつもりだったが、その言葉を文字にしてしまうと、たいせつにしていたものがほどけて、もとに戻らなくなる気がした。
親しくしていたスタッフが御花を去っていく。
それだって、初めての経験というわけではない。ないのだが、これまでに味わったことのないさみしさが、胸にわだかまっていた。別れの辛さともちがう、不穏さを帯びたさみしさだった。
葵に退職の意向を知らされたのは、前の晩のこと。帰り際に本人から呼び止められ、内緒話のように告げられた。辞める理由は前向きなものだった。とはいえ、あまりに予想外の話で、ほんとうはなにか問題や悩みがあるのではと、結月はしつこいくらいに質問した。帰宅したあとも、なかなか寝つけなかった。手紙を書けば落ち着くのではと、冬の長い夜が明けきらないうちにベッドを出て、ペンをとったが、うまくいかなかった。
書きかけの便箋をまるめて捨てた結月は、普段よりもずいぶん早くに自宅を出た。
御花に到着して仕事用の和服に着替えたが、始業時間まで三十分以上あった。厨房では仕込みが始まっていたものの、自分に手伝えることはなく、館内にごみが落ちていないか確かめようと考え、エレベーターで四階まであがった。宿泊のお客様のための部屋があるフロアだが、その日、だれも泊まっていないことはわかっていた。
エレベーターを降りて、長くはない廊下を行き止まりまで進んで気がついた。
ひとりになりたかったのだと。
ところが、静寂はすぐにやぶられた。
「おねえさん」
背後から声が響いてきた。振り返ると、少女がひとり、立っている。
背は低いものの、顔立ちは洗練されて大人っぽい。十五、六歳か。ブルーのニットキャップ。チョコレート色のダウンジャケットで、袖は指の中ほどまで覆っている。スキニータイプのジーンズに、ハイカットの白いスニーカー。
「どこか隠れられる場所ない?」
少女は、追手がこないか確かめるそぶりで廊下を振り返った。
「あの、見学のお客様でしょうか?」
平静を装って、確かめてみた。少女は結月に向き直った。ちいさな顔だが、目がするどくて、強い。ひとこと「ちがう」と答えるや、結月を見限るように彼女は踵を返した。しなやかに走って廊下を曲がって姿が見えなくなり、足音もすぐに消えた。あざやかな振る舞いは、現実のものと思えなかった。
座敷わらし。
ひさしぶりに、その名が頭に浮かぶと同時に、懐かしい記憶がよみがえってきた。
結月は宗高家の末っ子として生まれた。
男兄弟がおらず、いずれは姉が婿を迎えて後を継ぐのだというような話を、いつのころからか、自明のこととして受け入れていた。宗高家が由緒ある血筋であることも内外から聞かされて育ったが、自分がその一員だとは感じなかった。
小学生になり、二年生、三年生と学年をのぼっていくにつれ、どうやら面倒な立場にいるようだと自覚しはじめた。「宗高結月」である前に「御花の娘」としてあつかわれることが、少なくなかったためだ。外での振る舞いや言葉遣い、食事の作法など、特に祖母には厳しく躾けられた。給食の時間にパンをちぎって投げる男子や体育の時間に堂々とあぐらをかく女子を眺めながら、どこかで羨む気持ちを持っていた。
姉の千鶴は、中学生になると、和服を着て御花の手伝いに出るようになった。スタッフばかりか、お客様ともよくおしゃべりをしており、時代劇で見る若姫様といった印象が日に日に強まっていった。少し前までは姉妹で館内を駆けまわり、だれがいようとおかまいなしに鬼ごっこや隠れんぼで競っていたのに、姉にとって御花は「働く場所」になったようだった。
「結月もいっしょに、ここを、もっといい場所にしていこうよ」
遊ぼう、と誘ったのに、諭されるようなことが何度か続いて、結月は外の友達を頼るようになっていった。高校生になると、できるだけ早くここから出ていきたいと明言する友人が増えていった。
博多に。
東京に。
海外に。
みんな、柳川を愛していないわけではなかったものの、外へのあこがれは、おさえようもなく膨らんだ。
あとになってみれば、そうした記憶のどれもこれもに、青臭さが感じられる。はっきりとした目標を掲げる友人もいたが、結月のあこがれは、どこかへ行きたいという熱意より、ここを離れてみたいという気持ちに根を張っていた。それではどこにも行けないのだと、わかりはじめてもいた。自分なりの道を見つけないことには、どこにも。
転機は、高校二年の七月に訪れた。
東京からカメラマンが来ていると聞いた結月は、撮影や取材が楽しそうなら、そっちの道を歩んでみるのもいいかもしれないと考え、制服のまま大広間に向かった。若いカメラマンを見つけたが、姉もいっしょで、あれこれ質問できる雰囲気ではなかった。どうしたものかと思案していると、カメラマンのほうが質問してきた。
座敷わらしを見たことはあるか、と。
幼いころに着物で遊んでいて、座敷わらしみたいだと評されたことがあった。そのことではないかと結月は答えたものの、結局のところなんの話かわからず、その場をあとにした。
御花の近くに建てられた自宅へ戻ると、母におつかいを頼まれて、制服のまま外へ出た。お堀にかかった「出逢い橋」をわたっていると、さっきのカメラマンがやってくるところで、あちらから会釈された。田尻、と彼は名乗った。
「すみません、さきほどは、妙な質問をして」
「いえ、こちらこそ。お役に立てなくて」
結月も社交辞令とともに頭をさげた。すると田尻はなにか思いついた様子で、こう言った。
「じゃあ、役に立っていただけませんか?」
個人的な作品づくりを行っているので、ここで何枚か撮らせてもらえないか、という相談だった。
撮影時間は十五分足らずだった。田尻はカメラを構えてシャッターを切りながら、雑談をつづけた。いま携わっている仕事が一段落したら、半年ほどかけて、いくつかの国を渡り歩く予定なのだという。インド、アラスカ、バリ、地中海の国をふたつかみっつ。世界地図を思い描かずとも、めちゃくちゃな旅程であることはあきらかで、結月は笑った。
「行きたいところ選んだら、そうなるんです」と、田尻は当然のことのように言った。池に石を投げれば波紋ができるんです、とでもいうように。
そういう生き方もあるんだ。
柳川の高校生であり、御花の娘だった結月に、彼の人生観は強烈な一撃となった。
