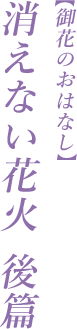
「すごい音」と芝生ガーデンのゴザに座っていた佐知子は、膨らんだお腹を守るようにさすって、空を見渡した。
ちょうど演舞を終えたところだった武将隊の面々も、ステージ上で空を見上げていたが、頭上はまだ水色だった。
「いやはや、大層な雷鳴だったのお」
「まこと、肝をつぶすとはこのことじゃ」
「なんじゃ、お主、雷が怖いのか。百戦錬磨の武将とは名ばかりじゃのう」
雷鳴まで演出のひとつだったかのように語る武将たちのおかげで、観客たちも安堵の笑い声をあげた。
「大丈夫ですか」と佐知子の隣に座っていた葵が声をかけた。
「はい。ちょっとびっくりして、お腹の中から蹴られました」
「元気だな」
佐知子の奥に並んで座る夫の啓太が笑った。
「じゃあ、葵さんも結婚式はここであげるんですか?」
お腹をさすりながら佐知子が質問した。
「え、私ですか? いや、まだそういう予定はないんですけど」
「いいですよ、絶対。って、差し出がましいこと言ってすみません。御花のことなら葵さんのほうが知ってますよね」
自嘲する佐知子に、葵は否定の言葉を返した。
「それがそうでもないんですよ。外で働いたら、御花のことわかってなかったなって思うことも多くて」
「なんかそれ、わかります」と啓太がうなずいた。「実家出てしばらくしたら、自分の家族とか違って見えますもんね」
「え、今のってそういう話?」
疑問を口にした佐知子の頬に、雨粒がひとつ、落ちてきた。
近くで誰かが、あめ、と声に出した。
佐知子は口を開けたまま空を見た。
灰色の雲が領土をひろげていた。真上はまだ明るいのに、それがほどなく終わることを予言するように、またひとつ、雨粒が落ちてきた。
「雨だ」
呑気なトーンで啓太が言った。
「雨も降ってきたのお」武将のひとりがつぶやいた。「皆の衆、くれぐれも風邪など召されぬようにな。ご老人やお子様方は日傘をさすなり、屋根のあるところへ避難されるなり」
そのとき、空が無音で明滅した。あ、という声がいくつかあがり、すこしの空白を挟んでから、雷鳴が鳴り響いた。強烈な鞭が振り下ろされたように、鋭くて、力強い音だった。
「佐知子さん、建物の中に行きましょうか」
葵が促し、啓太に支えられながら佐知子は立ち上がった。
空は早送りの映像みたいに雲に埋められていき、夕暮れ時の景色が不吉な色に染められていくなか、雨は着実に数を増していった。それでもまだ数十名の人々がどうすべきか戸惑うように、腰をあげられずにいた。
「中にお入りください!」
ひときわ大きな声が、屋台側から飛んできた。
波場だった。
メガホンがわりに手を口に添え、おなじ言葉を叫んだ。
「中にお入りください! 雷は危険です! 中にお入りください!」
さっと世界が白くなり、直後、稲光が空を裂いて、波場の避難勧告もあっけなく潰された。
「皆の者、建物へ避難されよ!」
武将のひとりが、マイク越しに伝えた。
スピーカーからの伝達が緊急性まで増幅させたのか、くつろいでいた人々も慌てて靴やサンダルを履いては、荷物を手に移動を開始した。さらに、どこからか聞こえてくる救急車のサイレンが、人々の避難行動に拍車をかけた。
いちはやく立ち上がった佐知子だったが、スニーカーを履く途中で腹部に違和感をおぼえ、その場にしゃがみこんでいた。小雨とはいえ、雨に濡れるのが妊婦にいいはずもなく、啓太は妻を抱きかかえて運ぶべきか思案顔になった。
「花澤! 傘!」
背後からの声に葵が振り返ると、ビニール傘をひろげた波場が立っていた。
「ありがとうございます」と葵がそれを受け取って、原田夫妻の上に持っていった。ビニール傘を叩く雨音が、まだまばらなくせに、いまいましく、立てずにいる佐知子の姿はもどかしかった。
そこへ、建物側から神谷が駆け寄ってきた。
「原田さん、大丈夫ですか」
空が光り、すこしの間をおいて、雷がまた鳴った。
佐知子の右側を啓太が、左側を神谷が支える格好で歩き出した。神谷の丸眼鏡は雨滴で濡れていたが、拭いている余裕もなく、葵はとにかく佐知子が濡れないよう傘を高く持ち上げた。
![]() 到着した花火師たちを控室に案内したところだった女将の宗高結月は、雷鳴を聞いて、松濤館裏口の通用口から外の状況をうかがおうとした。ドアを開けるや、お客様の列が雨の中、細い道を逃げ急いでいる光景が目に飛び込んできた。なにが起きているか把握できなかったものの、結月はすぐさま「こちらからどうぞ」と呼びかけた。
到着した花火師たちを控室に案内したところだった女将の宗高結月は、雷鳴を聞いて、松濤館裏口の通用口から外の状況をうかがおうとした。ドアを開けるや、お客様の列が雨の中、細い道を逃げ急いでいる光景が目に飛び込んできた。なにが起きているか把握できなかったものの、結月はすぐさま「こちらからどうぞ」と呼びかけた。
厨房前を通る職員用通路に逃げ込んだ人々の顔に安堵が浮かぶのが見てとれた。しかし、あとにまだ多くの人が続いているので、仕事着でもある和服が濡れるのも構わず、結月は重い扉を背中でおさえながら誘導の言葉を発した。
「先へお進みください。ロビーのほうまで、まっすぐ行って右へ曲がってください。先へお進みください」
わずかなあいだにも雨脚は強まり、小雨程度だったものがクレッシェンドの指示を受けたかのようにボリュームをあげていった。
妊婦を脇から支えた神谷の姿が見えた。すぐうしろに葵が傘を持って付き添っていて、神谷は体の左半分が濡れていた。眼鏡までずぶ濡れで、前が見えているのかも怪しい。
「神谷さん、こっち」
結月に手を引かれた神谷が体を横に向け、妊婦を持ち上げるようにしながら通用口への段差をあがった。傘が邪魔になるので、葵が一歩、退いた。通路に入ってきた妊婦は苦しそうな表情を浮かべていた。
「大丈夫ですか? 救急車呼びましょうか?」
結月の問いかけに、佐知子は「大丈夫です」と答えた。しかし呼吸は一向に落ち着かなかった。
傘を閉じた葵が入ってきた直後、高校生グループが駆け込んできた。通路の奥にはまだ他のお客様が詰まっていた。佐知子が呻き声を漏らした。腹部をおさえ、もう立っていられないというふうに、啓太の支えもむなしく、床にくずれた。
「おい、佐知子、おい、大丈夫か」
「だめ」と佐知子は腹部に手をやって答えた。「痛い、すごく、痛い」
短い言葉をしぼりだすのが精一杯の妻を目の当たりにして、「あの、タクシーは」と啓太が聞く。その質問にいち早く反応したのは葵だった。
普段であれば御花の前にタクシーがいるだろうが、お祭りもあって人の流れは普段どおりとはいえない。まして突然の雨だ。こんな状態の佐知子を外まで連れていってタクシーがいない、なんてことになれば負担を上乗せするだけで、松濤館前にタクシーを呼ぶにしても、時間が読めない。救急車は、さっき近くを走っていた。柳川に何台が控えているかは知らないが、現場到着時間は平均で八分以上のはず。十分や十五分をここで待つより、最寄りの病院へ向かうほうが早い。そうしたいくつかの知識と経験とが、葵の背中を押した。
「わたしの車で! 原田さん、急ぎましょう!」

「すごい音」と芝生ガーデンのゴザに座っていた佐知子は、膨らんだお腹を守るようにさすって、空を見渡した。
ちょうど演舞を終えたところだった武将隊の面々も、ステージ上で空を見上げていたが、頭上はまだ水色だった。
「いやはや、大層な雷鳴だったのお」
「まこと、肝をつぶすとはこのことじゃ」
「なんじゃ、お主、雷が怖いのか。百戦錬磨の武将とは名ばかりじゃのう」
雷鳴まで演出のひとつだったかのように語る武将たちのおかげで、観客たちも安堵の笑い声をあげた。
「大丈夫ですか」と佐知子の隣に座っていた葵が声をかけた。
「はい。ちょっとびっくりして、お腹の中から蹴られました」
「元気だな」
佐知子の奥に並んで座る夫の啓太が笑った。
「じゃあ、葵さんも結婚式はここであげるんですか?」
お腹をさすりながら佐知子が質問した。
「え、私ですか? いや、まだそういう予定はないんですけど」
「いいですよ、絶対。って、差し出がましいこと言ってすみません。御花のことなら葵さんのほうが知ってますよね」
自嘲する佐知子に、葵は否定の言葉を返した。
「それがそうでもないんですよ。外で働いたら、御花のことわかってなかったなって思うことも多くて」
「なんかそれ、わかります」と啓太がうなずいた。「実家出てしばらくしたら、自分の家族とか違って見えますもんね」
「え、今のってそういう話?」
疑問を口にした佐知子の頬に、雨粒がひとつ、落ちてきた。
近くで誰かが、あめ、と声に出した。
佐知子は口を開けたまま空を見た。
灰色の雲が領土をひろげていた。真上はまだ明るいのに、それがほどなく終わることを予言するように、またひとつ、雨粒が落ちてきた。
「雨だ」
呑気なトーンで啓太が言った。
「雨も降ってきたのお」武将のひとりがつぶやいた。「皆の衆、くれぐれも風邪など召されぬようにな。ご老人やお子様方は日傘をさすなり、屋根のあるところへ避難されるなり」
そのとき、空が無音で明滅した。あ、という声がいくつかあがり、すこしの空白を挟んでから、雷鳴が鳴り響いた。強烈な鞭が振り下ろされたように、鋭くて、力強い音だった。
「佐知子さん、建物の中に行きましょうか」
葵が促し、啓太に支えられながら佐知子は立ち上がった。
空は早送りの映像みたいに雲に埋められていき、夕暮れ時の景色が不吉な色に染められていくなか、雨は着実に数を増していった。それでもまだ数十名の人々がどうすべきか戸惑うように、腰をあげられずにいた。
「中にお入りください!」
ひときわ大きな声が、屋台側から飛んできた。
波場だった。
メガホンがわりに手を口に添え、おなじ言葉を叫んだ。
「中にお入りください! 雷は危険です! 中にお入りください!」
さっと世界が白くなり、直後、稲光が空を裂いて、波場の避難勧告もあっけなく潰された。
「皆の者、建物へ避難されよ!」
武将のひとりが、マイク越しに伝えた。
スピーカーからの伝達が緊急性まで増幅させたのか、くつろいでいた人々も慌てて靴やサンダルを履いては、荷物を手に移動を開始した。さらに、どこからか聞こえてくる救急車のサイレンが、人々の避難行動に拍車をかけた。
いちはやく立ち上がった佐知子だったが、スニーカーを履く途中で腹部に違和感をおぼえ、その場にしゃがみこんでいた。小雨とはいえ、雨に濡れるのが妊婦にいいはずもなく、啓太は妻を抱きかかえて運ぶべきか思案顔になった。
「花澤! 傘!」
背後からの声に葵が振り返ると、ビニール傘をひろげた波場が立っていた。
「ありがとうございます」と葵がそれを受け取って、原田夫妻の上に持っていった。ビニール傘を叩く雨音が、まだまばらなくせに、いまいましく、立てずにいる佐知子の姿はもどかしかった。
そこへ、建物側から神谷が駆け寄ってきた。
「原田さん、大丈夫ですか」
空が光り、すこしの間をおいて、雷がまた鳴った。
佐知子の右側を啓太が、左側を神谷が支える格好で歩き出した。神谷の丸眼鏡は雨滴で濡れていたが、拭いている余裕もなく、葵はとにかく佐知子が濡れないよう傘を高く持ち上げた。
![]() 到着した花火師たちを控室に案内したところだった女将の宗高結月は、雷鳴を聞いて、松濤館裏口の通用口から外の状況をうかがおうとした。ドアを開けるや、お客様の列が雨の中、細い道を逃げ急いでいる光景が目に飛び込んできた。なにが起きているか把握できなかったものの、結月はすぐさま「こちらからどうぞ」と呼びかけた。
到着した花火師たちを控室に案内したところだった女将の宗高結月は、雷鳴を聞いて、松濤館裏口の通用口から外の状況をうかがおうとした。ドアを開けるや、お客様の列が雨の中、細い道を逃げ急いでいる光景が目に飛び込んできた。なにが起きているか把握できなかったものの、結月はすぐさま「こちらからどうぞ」と呼びかけた。
厨房前を通る職員用通路に逃げ込んだ人々の顔に安堵が浮かぶのが見てとれた。しかし、あとにまだ多くの人が続いているので、仕事着でもある和服が濡れるのも構わず、結月は重い扉を背中でおさえながら誘導の言葉を発した。
「先へお進みください。ロビーのほうまで、まっすぐ行って右へ曲がってください。先へお進みください」
わずかなあいだにも雨脚は強まり、小雨程度だったものがクレッシェンドの指示を受けたかのようにボリュームをあげていった。
妊婦を脇から支えた神谷の姿が見えた。すぐうしろに葵が傘を持って付き添っていて、神谷は体の左半分が濡れていた。眼鏡までずぶ濡れで、前が見えているのかも怪しい。
「神谷さん、こっち」
結月に手を引かれた神谷が体を横に向け、妊婦を持ち上げるようにしながら通用口への段差をあがった。傘が邪魔になるので、葵が一歩、退いた。通路に入ってきた妊婦は苦しそうな表情を浮かべていた。
「大丈夫ですか? 救急車呼びましょうか?」
結月の問いかけに、佐知子は「大丈夫です」と答えた。しかし呼吸は一向に落ち着かなかった。
傘を閉じた葵が入ってきた直後、高校生グループが駆け込んできた。通路の奥にはまだ他のお客様が詰まっていた。佐知子が呻き声を漏らした。腹部をおさえ、もう立っていられないというふうに、啓太の支えもむなしく、床にくずれた。
「おい、佐知子、おい、大丈夫か」
「だめ」と佐知子は腹部に手をやって答えた。「痛い、すごく、痛い」
短い言葉をしぼりだすのが精一杯の妻を目の当たりにして、「あの、タクシーは」と啓太が聞く。その質問にいち早く反応したのは葵だった。
普段であれば御花の前にタクシーがいるだろうが、お祭りもあって人の流れは普段どおりとはいえない。まして突然の雨だ。こんな状態の佐知子を外まで連れていってタクシーがいない、なんてことになれば負担を上乗せするだけで、松濤館前にタクシーを呼ぶにしても、時間が読めない。救急車は、さっき近くを走っていた。柳川に何台が控えているかは知らないが、現場到着時間は平均で八分以上のはず。十分や十五分をここで待つより、最寄りの病院へ向かうほうが早い。そうしたいくつかの知識と経験とが、葵の背中を押した。
「わたしの車で! 原田さん、急ぎましょう!」
