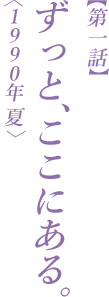
百畳敷きの総木曽檜造りだという大広間の隅に、田尻はひとり、黙って座っていた。
座敷わらしなんて本気で信じているのか?
そうです。信じています。だから出てきてください、あなたが、いまも、ここにいるのなら。
「順調ですか?」
突然の声に驚いて、田尻はあぐらを解いた。和服姿の女性が廊下からこちらを覗いている。座敷わらしにしては大きすぎるし、胸にネームプレートがあった。バイトかな、と田尻は推測する。化粧を薄くほどこしてはいるが、表情に幼いところがあって、高校生あたりかと見繕いながら、曖昧に返事をかえした。
「ええ、まあ」
頭を掻いて、なにかごまかすふうに立ち上がり、伸びをする。
「待ってるんですか?」女性は田尻の狙いを探るように、床に置いたカメラに視線を定めた。プロ仕様のもので、丸まった猫ていどのサイズだ。「もう一時間もそこにいらっしゃるから。あれですか、いい光を待ってるとか」
待っているという読みは正解だが、相手は自然光ではなく座敷わらしだ。腕時計を確かめると、思った以上に時間が過ぎている。光の具合ならば、もう午後も遅い時間で、ガイドブック向きの明朗な写真を撮るには手遅れだった。
「あの、おじゃまでなければ、お茶でもいかがですか?」
誘われるまま、田尻は喫茶室に移動した。
女性がコーヒーを持ってきたときにネームプレートを確かめた。「宗高千鶴」と書かれていて、田尻は「宗高さんって」と水を向けた。
「はい、ここの娘です。いま、夏休みで手伝いを。田尻さんは、本の取材でしたよね」
ええ、と答えてコーヒーに手をのばしながら、ふと彼は顔をあげた。
「あの、ひとつうかがいたいんですが」
「はい。私でよければ」
千鶴は背筋を正して凛々しい表情を作ったが、田尻はやや困ったように唇を舐めた。
「へんなこと、聞くんですけど、あの、ここって、座敷わらしが出る、なんて噂は」
「ありますよ」
砂糖の有無でも問われたふうに彼女はあっさりと肯定した。
「私は会ったことないんですけど、でも祖母が」
遮るように、田尻は告白した。
「僕も、見たんです」
「え?」
「前に、前にっていっても、もう、十年くらい前で」テーブルに語るみたいにうつむいたまま、彼はつづけた。「修学旅行でここに一度、来たことがあって、そのときに、さっきの、大広間で、着物を着たちいさな子を」
バスでやってきて、トイレを我慢していた田尻は担任の許可をもらってトイレに急行した。そのあとで通路を間違ったのか、でかい部屋に行き当たった。それが大広間だった。人がおらず、静かで、開かれた襖の向こうにはおおきな庭が広がっていた。すると、どこに隠れていたのか、部屋の中にひとりの子供がいるのに気づいた。地味な絣を着た、しかし肌が白く「珠のような」という表現がしっくりと来る子に、田尻は目を奪われた。その子は、制服姿の高校生など目に入っていないふうに大広間を横切っていった。幽霊にしては存在感が強く、観光で訪れた子というふうでもない。
そんなことを考えるあいだに、絣を着た子は縁側へ駆けていき、外に向かってジャンプした。次の瞬間には見えなくなっていた。高校生の田尻は前につんのめりそうになりながらスニーカーを脱いで、子供が消えたところへ小走りに近づいていった。庭には、誰もいなかった。空の高いところを、鳥たちが矢印めいた列を組んで飛んでいた。縁側の下を覗いてみたが、そのとき「おい、田尻!」とうしろから呼ばれた。振り返ると、担任が探しに来ていた。

百畳敷きの総木曽檜造りだという大広間の隅に、田尻はひとり、黙って座っていた。
座敷わらしなんて本気で信じているのか?
そうです。信じています。だから出てきてください、あなたが、いまも、ここにいるのなら。
「順調ですか?」
突然の声に驚いて、田尻はあぐらを解いた。和服姿の女性が廊下からこちらを覗いている。座敷わらしにしては大きすぎるし、胸にネームプレートがあった。バイトかな、と田尻は推測する。化粧を薄くほどこしてはいるが、表情に幼いところがあって、高校生あたりかと見繕いながら、曖昧に返事をかえした。
「ええ、まあ」
頭を掻いて、なにかごまかすふうに立ち上がり、伸びをする。
「待ってるんですか?」女性は田尻の狙いを探るように、床に置いたカメラに視線を定めた。プロ仕様のもので、丸まった猫ていどのサイズだ。「もう一時間もそこにいらっしゃるから。あれですか、いい光を待ってるとか」
待っているという読みは正解だが、相手は自然光ではなく座敷わらしだ。腕時計を確かめると、思った以上に時間が過ぎている。光の具合ならば、もう午後も遅い時間で、ガイドブック向きの明朗な写真を撮るには手遅れだった。
「あの、おじゃまでなければ、お茶でもいかがですか?」
誘われるまま、田尻は喫茶室に移動した。
女性がコーヒーを持ってきたときにネームプレートを確かめた。「宗高千鶴」と書かれていて、田尻は「宗高さんって」と水を向けた。
「はい、ここの娘です。いま、夏休みで手伝いを。田尻さんは、本の取材でしたよね」
ええ、と答えてコーヒーに手をのばしながら、ふと彼は顔をあげた。
「あの、ひとつうかがいたいんですが」
「はい。私でよければ」
千鶴は背筋を正して凛々しい表情を作ったが、田尻はやや困ったように唇を舐めた。
「へんなこと、聞くんですけど、あの、ここって、座敷わらしが出る、なんて噂は」
「ありますよ」
砂糖の有無でも問われたふうに彼女はあっさりと肯定した。
「私は会ったことないんですけど、でも祖母が」
遮るように、田尻は告白した。
「僕も、見たんです」
「え?」
「前に、前にっていっても、もう、十年くらい前で」テーブルに語るみたいにうつむいたまま、彼はつづけた。「修学旅行でここに一度、来たことがあって、そのときに、さっきの、大広間で、着物を着たちいさな子を」
バスでやってきて、トイレを我慢していた田尻は担任の許可をもらってトイレに急行した。そのあとで通路を間違ったのか、でかい部屋に行き当たった。それが大広間だった。人がおらず、静かで、開かれた襖の向こうにはおおきな庭が広がっていた。すると、どこに隠れていたのか、部屋の中にひとりの子供がいるのに気づいた。地味な絣を着た、しかし肌が白く「珠のような」という表現がしっくりと来る子に、田尻は目を奪われた。その子は、制服姿の高校生など目に入っていないふうに大広間を横切っていった。幽霊にしては存在感が強く、観光で訪れた子というふうでもない。
瞬間、田尻は、自分がタイムスリップして過去に迷い込んだ可能性を考えた。たしか、ここは、三百年も前からあるという話ではなかったか。
そんなことを考えるあいだに、絣を着た子は縁側へ駆けていき、外に向かってジャンプした。次の瞬間には見えなくなっていた。高校生の田尻は前につんのめりそうになりながらスニーカーを脱いで、子供が消えたところへ小走りに近づいていった。庭には、誰もいなかった。空の高いところを、鳥たちが矢印めいた列を組んで飛んでいた。縁側の下を覗いてみたが、そのとき「おい、田尻!」とうしろから呼ばれた。振り返ると、担任が探しに来ていた。
