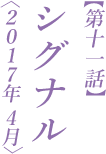
ほらね、やっぱり。
そんなふうに独り言を口にする夜が増えてきている。
地元でいちばんおおきな交差点で葵は、ブレーキペダルを踏んでいた。前方の信号は赤。車なんて他には一台も走っていない。人の姿もない。自分が聞き分けのいい飼い犬にでもなった気持ちになる。待て、と命じられて、おとなしく従う犬。でも、と葵はさらに考える。犬のほうがいい。おとなしく待っていれば、ご主人様が褒めてくれる。一介の信号機に「褒めて」なんて求めるわけにもいかない。信号の役割は、時間がきたら色を変える、それだけだ。
駅からのびる直線の道を走りだしたときから、信号に引っ掛かるのはわかっていた。すこしだけ強めにアクセルを踏んだものの、予想は的中した。
赤い光を見つめていると、思い返されるのは、その日の失態ばかり。たまに違う場面が蘇るが、それは昨日の失態、あるいは一昨日の。もしくは先週の。
たいした問題じゃない、と割り切ろうとするし、客観的に見ればたいした問題でないのもわかっている。わかっているが、俄か雨のように無視するわけにもいかなかった。
高校時代のアルバイトから始まって十年近く勤めた御花を、その年の始めに、辞めた。忙しい時期だったが、これを逃してはならないという焦りのほうが勝った。
二十六歳だった。
御花では、若い割にキャリアの長い人材として扱われていた。ずっとここで働くのだと、自分でもそう思っていた。なのに、突然、そうじゃなく思えた。だって自分は、御花しか知らない。その事実が、とつぜん、怖くなった。
こんなことで大丈夫だろうか。
自分は本当に貢献できているのだろうか。
女将をサポートできているのだろうか。
お客様への対応を間違ってはいないだろうか。
以前なら、自信満々とまでは言えないが、しっかりやっているという自負だって引っ張り出せてきた。なのにぜんぶがいっぺんに、遠い日になってしまった。季節はずれの五月病だと思い込もうとしたが、無駄に終わった。
あおい、という名前の由来を、幼いころから繰り返し、親に聞かされてきた。早産の可能性があって入院していた母から陣痛の連絡を受け、父が産院へ車でかけつけた。
「途中の信号がぜんぶ青だったんだ」
だから、あおい、という名前をもらった。
あの日の信号たちのように、人生に停滞がなく、順風満帆にすすんでいけますように。そんな願いが込められていた。
幼いころ、友達に絶交を申し渡されて大泣きした。友達とのあいだに通っていたはずの道が、赤信号で塞がれた気がした。ほかにも人並みに挫折は味わってきた。
葵という名前は、ただの名前だ。
信号が自分を特別視して、青色に変わってくれるわけではない。
神様が海を割ってくれるはずもない。
でも、ふとまわりを見渡せば、自分は順調に生きているように思えた。案外青信号ばかりじゃないかと。
バスケ部では身長の低さにもかかわらずレギュラーとして活躍した。将来の夢というのも特にはなくて、御花でアルバイトをしているときに社員にならないかと誘われて、はい、と返事をした。就職難で苦悩する友人たちに羨ましがられたりもした。
御花を辞める決心を固めると、次の職場を探した。全国に展開する、ウエディングのプロデュース会社に採用が決まり、天神店に配属された。御花でも披露宴の手伝いは日常業務のひとつであり、そうした経験が、面接で認められたのだと葵は理解した。
初めての転職で、険しい谷や山を進む覚悟だったのに、すんなりと次が決まったことが嬉しくもあり、拍子抜けでもあった。
新しい職場では、ドレスのレンタルに指輪の販売、披露宴会場の装飾や音楽面の演出、オーダーメイドのクラフトアイテムなど、ウエディングに関わるものならおよそなんでも対応可能で、お客様用のカタログの数も厚みも、御花のそれを超えていた。仕事の流れを覚えるだけでも頭がいっぱいになった。奮闘した。日に日に、心が固くなっていくようだった。知っていること、知らないこと、知っているつもりだったこと。それらを整理することもかなわず、十本の腕を操ろうとしているみたいに混乱した。帰り道、赤信号に引っ掛かることが増えた。
就職してひと月が過ぎたころ、ほかの新人とともに、研修のため東京出張を命じられた。
新宿本店で、五日間の日程だった。
初日、社長が新人と個別に面接をするというので、葵も順番を待った。社長室に呼ばれて入ると、ゆったりとした椅子に四十半ばの男性が腰掛けていた。顎髭を綺麗に揃え、浅黒い肌と薄いグレーのスーツがくっきりとしたコントラストを描いていた。
「福岡」と社長は低い声でつぶやいた。
「はい」
「どこ」
「大川、という町です」
「前職は?」
待ってました、と葵は口もとに微笑みを浮かべた。
「御花です」
社長は葵の目を見たまま、真顔で尋ねた。
「お花屋さん?」
「いえ、柳川の御花です」
「なんのお店?」
目の前でドアを閉じられた気がした。
御花について説明は試みたものの、社長の反応は芳しいものではなかった。それどころか、こうアドバイスされた。
「うちは新しいスタイルをどんどん採り入れているから」と。
似たようなことは、入社当時から、先輩や上司にも言われていた。「どんどん意見も言ってほしいし、良い提案なら採用してくれる職場だから」
その言葉に嘘はなかった。結婚式にまつわる情報は積極的に収集し、従業員専用のサイトで共有する。温故知新ではなく、「温今知新」という言葉を、社長が社員向けに発信していた。ふりがながなくて、なんと読むのか戸惑った。「おんこんちしん」だと、先輩社員にこっそり教わった。伝統も大切ですが、それ以上に「今の世の中」を知らなくては、最高のウエディングを届けることはできません。だから、ウエディングにまつわることだけではなく、世の中の動きのすべてに意識を閉ざさずにいましょう。

ほらね、やっぱり。
そんなふうに独り言を口にする夜が増えてきている。
地元でいちばんおおきな交差点で葵は、ブレーキペダルを踏んでいた。前方の信号は赤。車なんて他には一台も走っていない。人の姿もない。自分が聞き分けのいい飼い犬にでもなった気持ちになる。待て、と命じられて、おとなしく従う犬。でも、と葵はさらに考える。犬のほうがいい。おとなしく待っていれば、ご主人様が褒めてくれる。一介の信号機に「褒めて」なんて求めるわけにもいかない。信号の役割は、時間がきたら色を変える、それだけだ。
駅からのびる直線の道を走りだしたときから、信号に引っ掛かるのはわかっていた。すこしだけ強めにアクセルを踏んだものの、予想は的中した。
赤い光を見つめていると、思い返されるのは、その日の失態ばかり。たまに違う場面が蘇るが、それは昨日の失態、あるいは一昨日の。もしくは先週の。
たいした問題じゃない、と割り切ろうとするし、客観的に見ればたいした問題でないのもわかっている。わかっているが、俄か雨のように無視するわけにもいかなかった。
高校時代のアルバイトから始まって十年近く勤めた御花を、その年の始めに、辞めた。忙しい時期だったが、これを逃してはならないという焦りのほうが勝った。
二十六歳だった。
御花では、若い割にキャリアの長い人材として扱われていた。ずっとここで働くのだと、自分でもそう思っていた。なのに、突然、そうじゃなく思えた。だって自分は、御花しか知らない。その事実が、とつぜん、怖くなった。
こんなことで大丈夫だろうか。
自分は本当に貢献できているのだろうか。
女将をサポートできているのだろうか。
お客様への対応を間違ってはいないだろうか。
以前なら、自信満々とまでは言えないが、しっかりやっているという自負だって引っ張り出せてきた。なのにぜんぶがいっぺんに、遠い日になってしまった。季節はずれの五月病だと思い込もうとしたが、無駄に終わった。
あおい、という名前の由来を、幼いころから繰り返し、親に聞かされてきた。早産の可能性があって入院していた母から陣痛の連絡を受け、父が産院へ車でかけつけた。
「途中の信号がぜんぶ青だったんだ」
だから、あおい、という名前をもらった。
あの日の信号たちのように、人生に停滞がなく、順風満帆にすすんでいけますように。そんな願いが込められていた。
幼いころ、友達に絶交を申し渡されて大泣きした。友達とのあいだに通っていたはずの道が、赤信号で塞がれた気がした。ほかにも人並みに挫折は味わってきた。
葵という名前は、ただの名前だ。
信号が自分を特別視して、青色に変わってくれるわけではない。
神様が海を割ってくれるはずもない。
でも、ふとまわりを見渡せば、自分は順調に生きているように思えた。案外青信号ばかりじゃないかと。
バスケ部では身長の低さにもかかわらずレギュラーとして活躍した。将来の夢というのも特にはなくて、御花でアルバイトをしているときに社員にならないかと誘われて、はい、と返事をした。就職難で苦悩する友人たちに羨ましがられたりもした。
御花を辞める決心を固めると、次の職場を探した。全国に展開する、ウエディングのプロデュース会社に採用が決まり、天神店に配属された。御花でも披露宴の手伝いは日常業務のひとつであり、そうした経験が、面接で認められたのだと葵は理解した。
初めての転職で、険しい谷や山を進む覚悟だったのに、すんなりと次が決まったことが嬉しくもあり、拍子抜けでもあった。
新しい職場では、ドレスのレンタルに指輪の販売、披露宴会場の装飾や音楽面の演出、オーダーメイドのクラフトアイテムなど、ウエディングに関わるものならおよそなんでも対応可能で、お客様用のカタログの数も厚みも、御花のそれを超えていた。仕事の流れを覚えるだけでも頭がいっぱいになった。奮闘した。日に日に、心が固くなっていくようだった。知っていること、知らないこと、知っているつもりだったこと。それらを整理することもかなわず、十本の腕を操ろうとしているみたいに混乱した。帰り道、赤信号に引っ掛かることが増えた。
就職してひと月が過ぎたころ、ほかの新人とともに、研修のため東京出張を命じられた。
新宿本店で、五日間の日程だった。
初日、社長が新人と個別に面接をするというので、葵も順番を待った。社長室に呼ばれて入ると、ゆったりとした椅子に四十半ばの男性が腰掛けていた。顎髭を綺麗に揃え、浅黒い肌と薄いグレーのスーツがくっきりとしたコントラストを描いていた。
「福岡」と社長は低い声でつぶやいた。
「はい」
「どこ」
「大川、という町です」
「前職は?」
待ってました、と葵は口もとに微笑みを浮かべた。
「御花です」
社長は葵の目を見たまま、真顔で尋ねた。
「お花屋さん?」
「いえ、柳川の御花です」
「なんのお店?」
目の前でドアを閉じられた気がした。
御花について説明は試みたものの、社長の反応は芳しいものではなかった。それどころか、こうアドバイスされた。
「うちは新しいスタイルをどんどん採り入れているから」と。
似たようなことは、入社当時から、先輩や上司にも言われていた。「どんどん意見も言ってほしいし、良い提案なら採用してくれる職場だから」
その言葉に嘘はなかった。結婚式にまつわる情報は積極的に収集し、従業員専用のサイトで共有する。温故知新ではなく、「温今知新」という言葉を、社長が社員向けに発信していた。ふりがながなくて、なんと読むのか戸惑った。「おんこんちしん」だと、先輩社員にこっそり教わった。伝統も大切ですが、それ以上に「今の世の中」を知らなくては、最高のウエディングを届けることはできません。だから、ウエディングにまつわることだけではなく、世の中の動きのすべてに意識を閉ざさずにいましょう。
