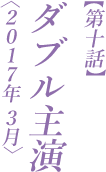
小川、と呼ばれても、反応できなかった。もう一度、さっきよりも近くから、「小川」と呼ばれて賢一郎は足をとめた。振り返ると、見覚えのある派手な男が傘を手に立っていた。
「太田」
「おう、反応おせえよ。人違いかって不安になったじゃねえか」
三月に入って間もない、しのつく雨の木曜の朝、十時。外での会議に出席した賢一郎は、商工会議所のメンバーに車で御花まで送ってもらったところだった。思わぬ再会に、顔のぜんぶで驚きと喜びを表しながら、賢一郎は旧友に近づいていった。
「いや、ほんとひさしぶりだな。いつ以来だ?」
雨音に負けないよう、つい、声が大きくなる。
「おまえの結婚の報告が最後だな」
賢一郎はすこし目線をあげて、旧友に一歩近づいた。太田は賢一郎よりずいぶん背が高い。ビニール傘にオレンジ色のスプリングコート、鮮やかな水色のショルダーバッグを斜めに掛けている。人の多い撮影現場でも一発で視認できるスタイリングは相変わらずだ。
「悪かったな、結婚式、せっかく招待してもらってたのに。あれ、何年前だ」
「六年、かな。なに今日は?」質問とともに、太田の背後にほかのスタッフがいないか確かめる。「仕事?」
「そう、仕事。ひとりだけどな」
「ずいぶん偉くなったんだろう?」
冷やかしにも似た質問に、太田はただ笑った。
「GM」と賢一郎を役職名で呼ぶ声がうしろから聞こえてきた。社長だった。紺のパンツスーツに明るい青空みたいな色の傘をさして、力強い足取りで近づいてくる。
「お知り合い?」
賢一郎の隣に立った社長が質問する。
「ああ、テレビ時代の同期で、太田。太田、こちらがうちの社長、宗高千鶴さん」
「はじめまして」
「はじめまして、太田です。社長ってことは、奥さん、ですよね」
「そうです。仕事中は社長とGMの間柄ですけど。あー、太田さん、思い出した、太田さん、ドラマのプロデューサーさんですよね。ご活躍、いつも、夫がテレビでチェックしてますよ。今日はお仕事ですか?」
「半分、そうですね、下見というか、まだどうなるかわからない案件があって。こちらに一泊させていただきます」
「あら、そうなんですね。どうぞ、隅から隅までご覧になっていってください。ちょっと大広間のほうとか、改修工事でご覧いただけないところもあるんですけど、きっちり、おもてなしさせていただきますから。あ、GM、わたし出かけるから」
「そうか、ラジオ」
「そう! ラジオ! もうね、緊張する、ほんと、しゃべりすぎたらどうしよう」
弱音さえ威勢よく話す様子に、賢一郎はおだやかな笑みを浮かべて、こう言った。
「だいじょうぶ。適当に」
「まあた適当とか言う。無理、無理よわたし、全力投球しかできないから。太田さん、また、戻ってから、お話しましょうね。じゃあ、行ってきます」
去っていく女性の背中を見送ってから、太田が口を開いた。
「あれがお姫様か」
賢一郎は広島の出身で、三人兄弟の長男坊だった。東京の大学を卒業後、テレビ番組の制作会社に就職した。父もサラリーマンで、継ぐべき家業もないので地元に戻るという選択肢は、最初からなかった。制作会社に四年勤めたのち、尊敬する放送作家の門を叩いて弟子入りした。企画の名のつくものであれば、どんな案件にも取り組んだ。帰省のたびに名刺や肩書が違っているので、親族から「賢一郎は定職に就いていないのか」と心配された。心配はそのうち、諦めにかわっていった。
「おまえがいつも楽しそうにしているから、心配するだけ無駄とわかった」
実家の父からそんなふうに言われたこともある。広島に戻ってこいとも言わないし、戻ってくるとも期待していない。ときどき元気な顔を見せてくれればそれでいい。ただし、もう駄目だとなったら、そのときは遠慮するな。
「おまえが不安そうな顔をしてたら、こんなふうには言わない。笑ってるから、大丈夫だと思えるから、言えるんだ」
父のその台詞を、賢一郎はノートにメモしている。ドラマ制作を離れて久しいが、人の言葉を収集する癖は抜けない。
婿入りする、という決断を伝えたときも、父は受け入れてくれた。さすがに反対されるのではと心配してはいたが、「おまえは本当におもしろい生き方をするんだな」と笑われた。
同じ頃、太田にも会った。当時、賢一郎はレストランのコンサルを担当しており、ロケに使えるレストランを探している太田から相談され、開業前の店でよければ好きなだけ撮影できるぞ、と担当店舗のひとつを紹介した。ドラマの放送とレストランのオープン時期が重なり、思いがけない宣伝材料になった。太田からも改めて感謝の言葉が届き、打ち上げと称して、二人で飲みに行った。
「縁だなあ」と太田はビールをがぶ飲みしては、つぶやいた。
「そういえば俺、結婚するんだ」と賢一郎が思い出したように報告した。
「マジか。やったな」
「なんだよ、やったな、って」
「だって小川、あちこち動き回ってそれどころじゃないって感じだったじゃないか」
「おまえに勝てるの、落ち着きのなさだけだもんな」
賢一郎の指摘に、太田は笑った。
「で、相手は?」
「ああ、お姫様」
「お姫様?」
「そう。お城に住んでる子がいるって最初に聞いてさ」
その物語に、太田はすぐさま食いついた。
「ここかあ」と御花の洋館を眺めながら太田は嘆息した。「小川もいまやお城の住人ってわけだ」
「馬鹿言え。自宅は別にある」
「改修工事ってのは?」
太田の目線がわずかにずれたのを賢一郎は見てとった。
「大広間で百年に一度の大改修をやっててさ。ああ、そうだ、宿泊するんなら荷物、先に預かっておこうか? どこかこのへん、見てまわるんだろ?」
「そうなんだけどな」
「案内してやりたいけど、今日、昼からひとつ打ち合わせが入っててさ」
しゃべりながら、松濤館へと太田を導いていった。道すがら、自分がウエディングプランナーを兼務しており、その日も、担当するカップルとの打ち合わせだと賢一郎は語った。フロントで太田を自分の旧友であると紹介したあと、賢一郎はいったん事務所へ戻った。

小川、と呼ばれても、反応できなかった。もう一度、さっきよりも近くから、「小川」と呼ばれて賢一郎は足をとめた。振り返ると、見覚えのある派手な男が傘を手に立っていた。
「太田」
「おう、反応おせえよ。人違いかって不安になったじゃねえか」
三月に入って間もない、しのつく雨の木曜の朝、十時。外での会議に出席した賢一郎は、商工会議所のメンバーに車で御花まで送ってもらったところだった。思わぬ再会に、顔のぜんぶで驚きと喜びを表しながら、賢一郎は旧友に近づいていった。
「いや、ほんとひさしぶりだな。いつ以来だ?」
雨音に負けないよう、つい、声が大きくなる。
「おまえの結婚の報告が最後だな」
賢一郎はすこし目線をあげて、旧友に一歩近づいた。太田は賢一郎よりずいぶん背が高い。ビニール傘にオレンジ色のスプリングコート、鮮やかな水色のショルダーバッグを斜めに掛けている。人の多い撮影現場でも一発で視認できるスタイリングは相変わらずだ。
「悪かったな、結婚式、せっかく招待してもらってたのに。あれ、何年前だ」
「六年、かな。なに今日は?」質問とともに、太田の背後にほかのスタッフがいないか確かめる。「仕事?」
「そう、仕事。ひとりだけどな」
「ずいぶん偉くなったんだろう?」
冷やかしにも似た質問に、太田はただ笑った。
「GM」と賢一郎を役職名で呼ぶ声がうしろから聞こえてきた。社長だった。紺のパンツスーツに明るい青空みたいな色の傘をさして、力強い足取りで近づいてくる。
「お知り合い?」
賢一郎の隣に立った社長が質問する。
「ああ、テレビ時代の同期で、太田。太田、こちらがうちの社長、宗高千鶴さん」
「はじめまして」
「はじめまして、太田です。社長ってことは、奥さん、ですよね」
「そうです。仕事中は社長とGMの間柄ですけど。あー、太田さん、思い出した、太田さん、ドラマのプロデューサーさんですよね。ご活躍、いつも、夫がテレビでチェックしてますよ。今日はお仕事ですか?」
「半分、そうですね、下見というか、まだどうなるかわからない案件があって。こちらに一泊させていただきます」
「あら、そうなんですね。どうぞ、隅から隅までご覧になっていってください。ちょっと大広間のほうとか、改修工事でご覧いただけないところもあるんですけど、きっちり、おもてなしさせていただきますから。あ、GM、わたし出かけるから」
「そうか、ラジオ」
「そう! ラジオ! もうね、緊張する、ほんと、しゃべりすぎたらどうしよう」
弱音さえ威勢よく話す様子に、賢一郎はおだやかな笑みを浮かべて、こう言った。
「だいじょうぶ。適当に」
「まあた適当とか言う。無理、無理よわたし、全力投球しかできないから。太田さん、また、戻ってから、お話しましょうね。じゃあ、行ってきます」
去っていく女性の背中を見送ってから、太田が口を開いた。
「あれがお姫様か」
賢一郎は広島の出身で、三人兄弟の長男坊だった。東京の大学を卒業後、テレビ番組の制作会社に就職した。父もサラリーマンで、継ぐべき家業もないので地元に戻るという選択肢は、最初からなかった。制作会社に四年勤めたのち、尊敬する放送作家の門を叩いて弟子入りした。企画の名のつくものであれば、どんな案件にも取り組んだ。帰省のたびに名刺や肩書が違っているので、親族から「賢一郎は定職に就いていないのか」と心配された。心配はそのうち、諦めにかわっていった。
「おまえがいつも楽しそうにしているから、心配するだけ無駄とわかった」
実家の父からそんなふうに言われたこともある。広島に戻ってこいとも言わないし、戻ってくるとも期待していない。ときどき元気な顔を見せてくれればそれでいい。ただし、もう駄目だとなったら、そのときは遠慮するな。
「おまえが不安そうな顔をしてたら、こんなふうには言わない。笑ってるから、大丈夫だと思えるから、言えるんだ」
父のその台詞を、賢一郎はノートにメモしている。ドラマ制作を離れて久しいが、人の言葉を収集する癖は抜けない。
婿入りする、という決断を伝えたときも、父は受け入れてくれた。さすがに反対されるのではと心配してはいたが、「おまえは本当におもしろい生き方をするんだな」と笑われた。
同じ頃、太田にも会った。当時、賢一郎はレストランのコンサルを担当しており、ロケに使えるレストランを探している太田から相談され、開業前の店でよければ好きなだけ撮影できるぞ、と担当店舗のひとつを紹介した。ドラマの放送とレストランのオープン時期が重なり、思いがけない宣伝材料になった。太田からも改めて感謝の言葉が届き、打ち上げと称して、二人で飲みに行った。
「縁だなあ」と太田はビールをがぶ飲みしては、つぶやいた。
「そういえば俺、結婚するんだ」と賢一郎が思い出したように報告した。
「マジか。やったな」
「なんだよ、やったな、って」
「だって小川、あちこち動き回ってそれどころじゃないって感じだったじゃないか」
「おまえに勝てるの、落ち着きのなさだけだもんな」
賢一郎の指摘に、太田は笑った。
「で、相手は?」
「ああ、お姫様」
「お姫様?」
「そう。お城に住んでる子がいるって最初に聞いてさ」
その物語に、太田はすぐさま食いついた。
「ここかあ」と御花の洋館を眺めながら太田は嘆息した。「小川もいまやお城の住人ってわけだ」
「馬鹿言え。自宅は別にある」
「改修工事ってのは?」
太田の目線がわずかにずれたのを賢一郎は見てとった。
「大広間で百年に一度の大改修をやっててさ。ああ、そうだ、宿泊するんなら荷物、先に預かっておこうか? どこかこのへん、見てまわるんだろ?」
「そうなんだけどな」
「案内してやりたいけど、今日、昼からひとつ打ち合わせが入っててさ」
しゃべりながら、松濤館へと太田を導いていった。道すがら、自分がウエディングプランナーを兼務しており、その日も、担当するカップルとの打ち合わせだと賢一郎は語った。フロントで太田を自分の旧友であると紹介したあと、賢一郎はいったん事務所へ戻った。
