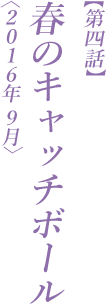
「このあいだ、酔っ払って帰ったときに、靴を脱がずに寝室まで行ったんですよ」
次の春に新郎となる男性が、恥ずかしそうに語り始めた。
「そしたら、すごく怒られました」
「そりゃ怒りますよ、だって、おかしいでしょ、せっかくの新居なのに土足であがるとか」
新婦となる女性の剣幕に、「そうですね」と神谷はうなずく。
「いや、だから、引っ越したばかりだからこそ、自宅だって思えなくて」
「片付けもしないからでしょう」と女性がまた怒りを募らせる。
その日は、来春の挙式披露宴に向けての打合せで、「最近なにかおもしろい出来事とかありましたか」と水を向けたところ、思わぬ方向に話題が転がり始めたのだった。
「まあ、まあ」
神谷は和やかな笑みを保ったまま、両手でふたりに落ち着いてもらおうとした。
「だって、この人、引っ越しの日も外で飲んでたんですよ」
「それは、前からの約束だったから」
「引っ越しだって前々から決めてたじゃない」
「だから、それは、ちゃんと次の日に手伝ったし、荷物はだいたい業者が運んでくれただろ」
「はあ? わたしがこまかいの運びましたけど」
新郎は弱りきった目になった。そのとき、助け舟が到着した。土曜日の午前中で、その日が挙式の新郎新婦御一行が神社から「花嫁舟」に乗って御花までやってきたのだ。舟着場で待機していた
人々の祝福の歓声が、館内の喫茶コーナーにまで聞こえてくる。
「ああ、今日、挙式の方々ですね。きっと、舟で入ってこられたところです」
何事かと振り返るふたりに神谷が説明すると、女性のほうが「見てきていいですか」と声をはずませながら席を立った。あとに残された未来の新郎は、男性同士の気安さからか、肩の力を抜いてコーヒーに手をつけた。神谷は縁無しの眼鏡を正した。
「すみません、恥ずかしいところ見せてしまって」
男性が、小さく頭を下げた。
「いえいえ。原田さんは、外の様子、ご覧にならなくてよろしかったですか?」
「あー、俺は、いいです」
遠慮する、というよりは、危険を避けるといった態度に、神谷には見受けられた。
「あの」と原田が声のトーンをさげる。「どうですか、プロの目から見て、俺たちみたいに、結婚前から喧嘩してるカップルって」
「そんな、喧嘩というほどのことはないですよ。それに、思ったことを口にできる関係っていうのは、これは、夫婦としては理想的な距離感だと私は思います」
「そうですかね……」
手持ち無沙汰に、原田はテーブルのパンフレットに指先を置いた。その日は二回目の打合せで、初回ではふたりの馴れ初めを入口に、なぜ御花での挙式を選ばれたのか、どんな時間で皆さんをもてなしたいのかといった概略を聞いていた。その際のメモを読み返しながら、神谷は聞いた。
「遠距離が、長かったんですよね」
「ええ。俺が大学院まで行ったから、六年。高校の卒業式の日に付き合い始めて、だけど大学ですぐ遠距離になって。離れてるときは、喧嘩らしい喧嘩もなかったんですけど……。やっぱ、ずっと近くにいると、笑ってばっかりでいられないですよね」
はは、と控えめな笑い声で神谷は返した。
沈黙が、ふたりの間にしばし居座ったが、表の歓声がそれを埋めた。
「実は、私も、遠距離だったんですよ」と神谷はつい口にした。
「え、そうなんですか?」
「ええ。もともと、九州には縁もゆかりもなかったんですけど」
神谷は埼玉県の出身で、家族旅行や修学旅行で東日本はほぼ制覇していたが、西の方面となると、大坂より下へ踏み入ったことがなかった。東京の大学に通い、そのまま中堅どころの家電メーカーへ就職。二年間を営業職で勤めたあと、提携先である家電量販店に出向の辞令を受けた。都内の店舗で販売業務のサポートにつき、なにがどうなったのか、福岡の店舗へ異動になった。二十代も折り返し点を過ぎた頃だった。とうぜん、不安に駆られた。案外、接客業も向いているのはわかってきたが、しかし、だからといって、九州への出向とは。上司を呼び出し、サシで飲みながら会社の内情を探ったが、詳しいところはわからなかった。いくつかの事情が絡まって、そういう流れになったのだという。「一年で出向が終わるよう調整する」と上司は約束してくれたが、しかし、神谷の疑念は払拭されなかった。
同じころ、学生時代の友人数名が転職を決めていた。景気の良い時代ではなかったので、誰もがステップアップというわけではなく、神谷の不透明な先行きを聞いて、転職組のひとりがこう言った。
「福岡って、それもう、転職レベルじゃん」
確かに、新天地での暮らしは生まれ育った関東のそれとまるで違った。人も、食も、時間の流れも、あまりに違いが多すぎて、なるほど日本も広いものだと痛感した。知り合いはひとりもなかったが、幸い、新しい職場や取引先の人々との交流の中で息苦しさを感じることはなかった。仕事の中身は都内店舗と似たり寄ったりなのだが、私生活があまりに変わってしまったので、転職というよりは生まれ変わりのようだと、神谷はそんなふうに思え、意識を切り替えた。
一年の福岡暮らしを楽しむべく、休日には近隣の観光地に足を伸ばした。同僚とは休みの都合があわせにくく、たいていは一人旅になったが、もてなし好きの県民性なのか、同僚たちは神谷の単独行を気にかけていて、福岡での生活が二ヶ月目に入ったころ、彼のために盛大な合コンがセッティングされた。
妻となる女性と知り合ったのは、その合コンでのことだった。男女七名ずつが参加した。ひとりだけ東京の言葉を話す神谷は賑やかな会話の中で浮いて見えたが、その様子を面白がってくれる女性がいた。名を、木下麻理恵といった。麻理恵は遠方に住んでいるといい、その夜も電車で帰り、降りた先から車を運転するのでお酒は飲まないと最初に明言していた。合コンには人数合わせで参加したのだとも言い「神谷さんもやろ?」と聞いてきた。同僚たちの流暢かつ手慣れた会話術に比べると、朴訥な神谷は乗り気というふうには見えないらしかった。しかし、率直なところ、麻理恵は彼の好みだった。一目惚れ、なんておとぎばなしだと認識していたが、その夜、神谷は自分の辞書の一部を書き換えることになった。一目惚れは、現実にあるのだと。
彼は素直に、麻理恵の連絡先を求めた。彼女はすんなりとそれを受け容れてくれた。「友達増えるの嬉しい」と笑いながら。
二次会組と別れて、神谷は麻理恵を駅まで送っていった。観光地をできるだけ多くめぐりたいのだと道すがらに語ると、じゃあ自分の車で行かないかと麻理恵が提案してくれた。天神で販売員として働く彼女もまた、週末ではなく平日の休みが多いとのことで、別れる前に、次に会う日取りまで決めてしまった。
改札で手を振り、彼女が電車に乗りこむのを見届けてから、神谷は近くのベンチに腰を下ろして、息を吐きながら小さく声に出した。
ふくおか、と。

「このあいだ、酔っ払って帰ったときに、靴を脱がずに寝室まで行ったんですよ」
次の春に新郎となる男性が、恥ずかしそうに語り始めた。
「そしたら、すごく怒られました」
「そりゃ怒りますよ、だって、おかしいでしょ、せっかくの新居なのに土足であがるとか」
新婦となる女性の剣幕に、「そうですね」と神谷はうなずく。
「いや、だから、引っ越したばかりだからこそ、自宅だって思えなくて」
「片付けもしないからでしょう」と女性がまた怒りを募らせる。
その日は、来春の挙式披露宴に向けての打合せで、「最近なにかおもしろい出来事とかありましたか」と水を向けたところ、思わぬ方向に話題が転がり始めたのだった。
「まあ、まあ」
神谷は和やかな笑みを保ったまま、両手でふたりに落ち着いてもらおうとした。
「だって、この人、引っ越しの日も外で飲んでたんですよ」
「それは、前からの約束だったから」
「引っ越しだって前々から決めてたじゃない」
「だから、それは、ちゃんと次の日に手伝ったし、荷物はだいたい業者が運んでくれただろ」
「はあ? わたしがこまかいの運びましたけど」
新郎は弱りきった目になった。そのとき、助け舟が到着した。土曜日の午前中で、その日が挙式の新郎新婦御一行が神社から「花嫁舟」に乗って御花までやってきたのだ。舟着場で待機していた
人々の祝福の歓声が、館内の喫茶コーナーにまで聞こえてくる。
「ああ、今日、挙式の方々ですね。きっと、舟で入ってこられたところです」
何事かと振り返るふたりに神谷が説明すると、女性のほうが「見てきていいですか」と声をはずませながら席を立った。あとに残された未来の新郎は、男性同士の気安さからか、肩の力を抜いてコーヒーに手をつけた。神谷は縁無しの眼鏡を正した。
「すみません、恥ずかしいところ見せてしまって」
男性が、小さく頭を下げた。
「いえいえ。原田さんは、外の様子、ご覧にならなくてよろしかったですか?」
「あー、俺は、いいです」
遠慮する、というよりは、危険を避けるといった態度に、神谷には見受けられた。
「あの」と原田が声のトーンをさげる。「どうですか、プロの目から見て、俺たちみたいに、結婚前から喧嘩してるカップルって」
「そんな、喧嘩というほどのことはないですよ。それに、思ったことを口にできる関係っていうのは、これは、夫婦としては理想的な距離感だと私は思います」
「そうですかね……」
手持ち無沙汰に、原田はテーブルのパンフレットに指先を置いた。その日は二回目の打合せで、初回ではふたりの馴れ初めを入口に、なぜ御花での挙式を選ばれたのか、どんな時間で皆さんをもてなしたいのかといった概略を聞いていた。その際のメモを読み返しながら、神谷は聞いた。
「遠距離が、長かったんですよね」
「ええ。俺が大学院まで行ったから、六年。高校の卒業式の日に付き合い始めて、だけど大学ですぐ遠距離になって。離れてるときは、喧嘩らしい喧嘩もなかったんですけど……。やっぱ、ずっと近くにいると、笑ってばっかりでいられないですよね」
はは、と控えめな笑い声で神谷は返した。
沈黙が、ふたりの間にしばし居座ったが、表の歓声がそれを埋めた。
「実は、私も、遠距離だったんですよ」と神谷はつい口にした。
「え、そうなんですか?」
「ええ。もともと、九州には縁もゆかりもなかったんですけど」
神谷は埼玉県の出身で、家族旅行や修学旅行で東日本はほぼ制覇していたが、西の方面となると、大坂より下へ踏み入ったことがなかった。東京の大学に通い、そのまま中堅どころの家電メーカーへ就職。二年間を営業職で勤めたあと、提携先である家電量販店に出向の辞令を受けた。都内の店舗で販売業務のサポートにつき、なにがどうなったのか、福岡の店舗へ異動になった。二十代も折り返し点を過ぎた頃だった。とうぜん、不安に駆られた。案外、接客業も向いているのはわかってきたが、しかし、だからといって、九州への出向とは。上司を呼び出し、サシで飲みながら会社の内情を探ったが、詳しいところはわからなかった。いくつかの事情が絡まって、そういう流れになったのだという。「一年で出向が終わるよう調整する」と上司は約束してくれたが、しかし、神谷の疑念は払拭されなかった。
同じころ、学生時代の友人数名が転職を決めていた。景気の良い時代ではなかったので、誰もがステップアップというわけではなく、神谷の不透明な先行きを聞いて、転職組のひとりがこう言った。
「福岡って、それもう、転職レベルじゃん」
確かに、新天地での暮らしは生まれ育った関東のそれとまるで違った。人も、食も、時間の流れも、あまりに違いが多すぎて、なるほど日本も広いものだと痛感した。知り合いはひとりもなかったが、幸い、新しい職場や取引先の人々との交流の中で息苦しさを感じることはなかった。仕事の中身は都内店舗と似たり寄ったりなのだが、私生活があまりに変わってしまったので、転職というよりは生まれ変わりのようだと、神谷はそんなふうに思え、意識を切り替えた。
一年の福岡暮らしを楽しむべく、休日には近隣の観光地に足を伸ばした。同僚とは休みの都合があわせにくく、たいていは一人旅になったが、もてなし好きの県民性なのか、同僚たちは神谷の単独行を気にかけていて、福岡での生活が二ヶ月目に入ったころ、彼のために盛大な合コンがセッティングされた。
妻となる女性と知り合ったのは、その合コンでのことだった。男女七名ずつが参加した。ひとりだけ東京の言葉を話す神谷は賑やかな会話の中で浮いて見えたが、その様子を面白がってくれる女性がいた。名を、木下麻理恵といった。麻理恵は遠方に住んでいるといい、その夜も電車で帰り、降りた先から車を運転するのでお酒は飲まないと最初に明言していた。合コンには人数合わせで参加したのだとも言い「神谷さんもやろ?」と聞いてきた。同僚たちの流暢かつ手慣れた会話術に比べると、朴訥な神谷は乗り気というふうには見えないらしかった。しかし、率直なところ、麻理恵は彼の好みだった。一目惚れ、なんておとぎばなしだと認識していたが、その夜、神谷は自分の辞書の一部を書き換えることになった。一目惚れは、現実にあるのだと。
彼は素直に、麻理恵の連絡先を求めた。彼女はすんなりとそれを受け容れてくれた。「友達増えるの嬉しい」と笑いながら。
二次会組と別れて、神谷は麻理恵を駅まで送っていった。観光地をできるだけ多くめぐりたいのだと道すがらに語ると、じゃあ自分の車で行かないかと麻理恵が提案してくれた。天神で販売員として働く彼女もまた、週末ではなく平日の休みが多いとのことで、別れる前に、次に会う日取りまで決めてしまった。
改札で手を振り、彼女が電車に乗りこむのを見届けてから、神谷は近くのベンチに腰を下ろして、息を吐きながら小さく声に出した。
ふくおか、と。
