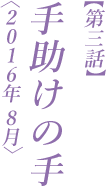
細田は頭を抱えた。
机には企画書が一部置かれており、表紙には〈100年先までのお得意様プラン!〉と、太字のうえに、虹色までほどこされたタイトルが踊っている。本当に踊りだしそうだ、と細田は眼鏡越しにその文字を睨みつけた。
「あ、おはようございます。細田さん、たいへんでしたね」
総務の藤野優実が出勤してきて、ねぎらいの言葉をかけた。
「ああ、おはよう」
「おばあさま、でしたっけ」
「そう、一〇〇歳。大往生だよ」
前日まで、細田は忌引をとっていた。母方の祖母が亡くなったためだ。享年一〇〇歳。いま四十一歳の細田が物心ついたときには、名実ともにおばあちゃんで、地元では産婆として有名で九十を過ぎても活動していた。後進の育成が仕事のほとんどを占めるようになっていたが、それでも、陣痛に苦しむ女性の背中を祖母がさすってあげると、不思議と痛みが和らぐと評判で、二十一世紀になってもまだ予約の依頼が絶えなかった。その神通力は一代限りのものなのかな、と通夜の席で従兄弟連中と話し合った。赤子を取りあげるどころか、オムツ替えもろくに経験の無い中年たちが、みな、酔っ払った目で、自分の掌を見つめていた。
「これ、おみやげ、ですか?」
優実が個包装の最中を手にとって尋ねる。
「そう。地元の銘菓だよ」
「わざわざすみません。たいへんだったでしょうに」
「いや、予測してたから」
今日か明日か、という連絡を受けるや、細田は仕事を片付け、あるいは引き継ぎを終え、地元に飛んだ。祖母と同居していた伯父が喪主だったが、葬儀屋との料金交渉などはすべて細田が引き受けた。無駄を省き、祖母を送り出すにふさわしいプランを万端整えた。葬儀帰りに土産など買わないだろう、という妻の意見を却下して、職場への土産を見繕った。それも最初から彼のプランに入っていた。
「あ、細田さん、戻ってたんですね!」
再会を喜ぶ旧友みたいに大きく朗らかな声で、営業部の波場が入ってきた。名前に合った幅広な体格で、いかにも体育会系。痩せ型で神経質そうと見られがちな細田とは対照的な男だ。
「やー、たいへんでしたね。復帰早々申し訳ないんですが、見ました? 僕の」
「見たよ」
「よかったー。それね、きょう、社長にプレゼンしようかと思ってるんですよ。だから御花の金庫番であり頭脳でもある細田さんの太鼓判をですね、こう、どーんといただけると、なんていうんですか、箔がつくっていうのかな」
「押さないよ」
「え?」
「太鼓判どころか、拇印でも断るね。あのさ、波場君もさ、これ、本気で書いてるっていうのは、どうかしてるよ。一〇〇年先まで利用できるプランなんて、人間向きじゃないだろう」
「いや、そこはほら、この先ね、医療だって発達するわけですよ。平均寿命も伸びるし、一〇〇歳を超えても元気な方もね、増えるんじゃないかなあ」
呑気な夢物語を主張する波場を前に、細田は深々と溜息をついた。
〈100年先までのお得意様プラン!〉は、個人を対象とした会員制プログラムで、入会すれば、一年ごと、五年ごと、十年ごとに特典が用意されており、一〇〇年先には柳川の街をあげての大祝賀会を催す予定になっていた。
生まれたその日に入会したとしても、大祝賀会までたどりつける人がどれだけいるというのか。常識的に考えればわかるはずだ。
「でも、あるじゃないですか、年会費永年無料みたいなやつ、あれ見て、思いついちゃったんですよね」
「根本的に違うじゃないか、永年無料と一〇〇年のプランじゃ」
「そう、そうなんですよ、わかってますって。なにもね、僕も本気で一〇〇年って言ってるわけじゃないですよ。なんていうか、そこはね、希望、希望ですよ。そういう楽しみが先に待ってるって思ったら、それをひとつの希望に、今日を生きていこうって思えるんじゃ、ないかなあ」
「はい、わかりました。いずれにしても、私は却下」
いたって冷静に、細田は企画書を波場に戻した。
「えー、なんでですか」と波場は幼気に顔をしかめる。「一〇〇年先の御花を見据えた計画って、社長命令なんだし、そしたらどうしたって、こういう話になるでしょう?」
「ああ、それも私は賛同してない」
その言葉を待っていたかのように、藤野優実が口を挟む。
「細田さんは二十四年先までしか保障しないんですよね」
「そうだよ」
「なんすか、二十四年って」
「私の定年。少なくともそこまでは、御花に存続していてもらわなくては困る」
「私利私欲じゃないですかあ」
波場は情けない声をあげた。
「公利私欲だよ。そもそも経営体制を見直すために私はここに呼ばれたのだし、二十四年といえばおよそ四半世紀、子供が成長して次の世代が生まれてもいいサイクルだ。そのあたりが、提供サービスを見据えるにあたっても適切な区切りだと思うけれどね」
その後も波場は食い下がったが、細田は反論のひとつひとつを丁寧かつ確実に潰していった。

細田は頭を抱えた。
机には企画書が一部置かれており、表紙には〈100年先までのお得意様プラン!〉と、太字のうえに、虹色までほどこされたタイトルが踊っている。本当に踊りだしそうだ、と細田は眼鏡越しにその文字を睨みつけた。
「あ、おはようございます。細田さん、たいへんでしたね」
総務の藤野優実が出勤してきて、ねぎらいの言葉をかけた。
「ああ、おはよう」
「おばあさま、でしたっけ」
「そう、一〇〇歳。大往生だよ」
前日まで、細田は忌引をとっていた。母方の祖母が亡くなったためだ。享年一〇〇歳。いま四十一歳の細田が物心ついたときには、名実ともにおばあちゃんで、地元では産婆として有名で九十を過ぎても活動していた。後進の育成が仕事のほとんどを占めるようになっていたが、それでも、陣痛に苦しむ女性の背中を祖母がさすってあげると、不思議と痛みが和らぐと評判で、二十一世紀になってもまだ予約の依頼が絶えなかった。その神通力は一代限りのものなのかな、と通夜の席で従兄弟連中と話し合った。赤子を取りあげるどころか、オムツ替えもろくに経験の無い中年たちが、みな、酔っ払った目で、自分の掌を見つめていた。
「これ、おみやげ、ですか?」
優実が個包装の最中を手にとって尋ねる。
「そう。地元の銘菓だよ」
「わざわざすみません。たいへんだったでしょうに」
「いや、予測してたから」
今日か明日か、という連絡を受けるや、細田は仕事を片付け、あるいは引き継ぎを終え、地元に飛んだ。祖母と同居していた伯父が喪主だったが、葬儀屋との料金交渉などはすべて細田が引き受けた。無駄を省き、祖母を送り出すにふさわしいプランを万端整えた。葬儀帰りに土産など買わないだろう、という妻の意見を却下して、職場への土産を見繕った。それも最初から彼のプランに入っていた。
「あ、細田さん、戻ってたんですね!」
再会を喜ぶ旧友みたいに大きく朗らかな声で、営業部の波場が入ってきた。名前に合った幅広な体格で、いかにも体育会系。痩せ型で神経質そうと見られがちな細田とは対照的な男だ。
「やー、たいへんでしたね。復帰早々申し訳ないんですが、見ました? 僕の」
「見たよ」
「よかったー。それね、きょう、社長にプレゼンしようかと思ってるんですよ。だから御花の金庫番であり頭脳でもある細田さんの太鼓判をですね、こう、どーんといただけると、なんていうんですか、箔がつくっていうのかな」
「押さないよ」
「え?」
「太鼓判どころか、拇印でも断るね。あのさ、波場君もさ、これ、本気で書いてるっていうのは、どうかしてるよ。一〇〇年先まで利用できるプランなんて、人間向きじゃないだろう」
「いや、そこはほら、この先ね、医療だって発達するわけですよ。平均寿命も伸びるし、一〇〇歳を超えても元気な方もね、増えるんじゃないかなあ」
呑気な夢物語を主張する波場を前に、細田は深々と溜息をついた。
〈100年先までのお得意様プラン!〉は、個人を対象とした会員制プログラムで、入会すれば、一年ごと、五年ごと、十年ごとに特典が用意されており、一〇〇年先には柳川の街をあげての大祝賀会を催す予定になっていた。
生まれたその日に入会したとしても、大祝賀会までたどりつける人がどれだけいるというのか。常識的に考えればわかるはずだ。
「でも、あるじゃないですか、年会費永年無料みたいなやつ、あれ見て、思いついちゃったんですよね」
「根本的に違うじゃないか、永年無料と一〇〇年のプランじゃ」
「そう、そうなんですよ、わかってますって。なにもね、僕も本気で一〇〇年って言ってるわけじゃないですよ。なんていうか、そこはね、希望、希望ですよ。そういう楽しみが先に待ってるって思ったら、それをひとつの希望に、今日を生きていこうって思えるんじゃ、ないかなあ」
「はい、わかりました。いずれにしても、私は却下」
いたって冷静に、細田は企画書を波場に戻した。
「えー、なんでですか」と波場は幼気に顔をしかめる。「一〇〇年先の御花を見据えた計画って、社長命令なんだし、そしたらどうしたって、こういう話になるでしょう?」
「ああ、それも私は賛同してない」
その言葉を待っていたかのように、藤野優実が口を挟む。
「細田さんは二十四年先までしか保障しないんですよね」
「そうだよ」
「なんすか、二十四年って」
「私の定年。少なくともそこまでは、御花に存続していてもらわなくては困る」
「私利私欲じゃないですかあ」
波場は情けない声をあげた。
「公利私欲だよ。そもそも経営体制を見直すために私はここに呼ばれたのだし、二十四年といえばおよそ四半世紀、子供が成長して次の世代が生まれてもいいサイクルだ。そのあたりが、提供サービスを見据えるにあたっても適切な区切りだと思うけれどね」
その後も波場は食い下がったが、細田は反論のひとつひとつを丁寧かつ確実に潰していった。
