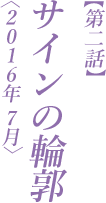
夜が明ける。
ひとりきりの事務所で、岡部は色紙をゴミ箱に突っ込んだ。ほかの従業員の目についてはいけないと頭では理解しているのだが、一度はゴミ箱に沈めてやりたかった。
そこにはサインがひとつ、書かれていた。ご丁寧に、前日の日付まで入れてある。
彼が十代のころから憧れていたミュージシャンが一昨日に御花を訪れ、家族で宿泊していった。プライベート旅行だ。ミュージシャンといっても一般的に有名ではない。もともとバンドでベースを弾いていたが、解散後は様々なアーティストのバックを務めている。業界で知らぬ人はいない実力派だが、スポットライトを浴びるのはライブでのメンバー紹介くらいだろう。しかし岡部は、知っていた。バンド時代から本名ではなく「ナビ」名義で活動していた彼の本名が「渡邊」であることも知っていた。同じベース弾きとして、憧れでもあり、神でもあった。
もちろん、お客様として来訪した人物に従業員がサインをねだるなど、やってはならない行為だ。仕事であれ、プライベートであれ、侵してはならない一線を引いておくこと。その規律を、きちんと守ってきた。オーラ全開の女優を間近に見たときでさえ、訓練の行き届いた笑顔しか出さないよう踏ん張った。
しかし相手がナビとなると、その戒律も、ゆるんでしまった。
ミュージシャンの道はとうに過去のものだが、ナビの演奏を耳にするたび、往時の高揚が蘇る。予約欄に彼の名を見たときには、「同姓同名だ、そうに決まっている」と自分に言い聞かせたが、休憩時間になるや、スマホに入れたナビの演奏に聴き入った。
誰にでも神様はいる、と岡部は思う。地上にだって神様はいる。人の運命を変えてしまう存在が。
休憩室に上司の宗高賢一郎が入ってきて、すっとんきょうな声をあげた。
「ああ、びっくりした、いるならいるって言ってよ」
イヤホンをつけているので何を言われたのか、明瞭には聞き取れなかったが、賢一郎の表情から驚かせてしまったのはわかった。
ひとまわりも年上だったが、賢一郎の物腰に岡部は、兄に接するような気安さをおぼえていた。東京から柳川に越してきて二年。前職は放送作家だったという。月に1000本の企画案を出していたという仕事柄、万事に精通している賢一郎は、ナビのことも知っていた。あれ、きっと、ナビさんなんですよ、と雑談の途中で岡部はつい口にした。憧れの人であること、一度でいいから握手してみたいこと、そんなことまで、気づけば打ち明けていた。
「じゃあぼくがサイン頼んでみようか」
カフェでおかわりでも頼むみたいな調子の賢一郎を見て、岡部は、感動とも尊敬ともつかない声をあげた。
「いいんですか?」
「サインだろ。そりゃ、ホテルマンとしては褒められた行為じゃないかもしれないが、でも岡部君、いままで我慢してきたんだろ。ポイントカードだったら、もう満点貯まってる。お好きな有名人のサインをひとつプレゼントだよ」
「でも」
「ははは、冗談だって」
それを岡部は、ポイントカードの比喩のみにかかった言葉だと理解した。サインをもらってくれるのは冗談ではないのだと。
「え、でも、ほんとにいいんですか、サイン、頼んでもらえますか?」
真顔で確かめる岡部に、賢一郎は頬を掻きながらこう返した。
「あ、ああ。でも、あれだろ、そのお客様が岡部君の神様かどうか、実際のとこ、わからないんだろ?」
宿泊に来たのは間違いなく、ナビその人だった。宿帳には奥さんが記入し、その間、ナビは十代の息子と仲良くおしゃべりを楽しんでいた。わあ、と、眼差しから声が漏れそうになるのを、フロントの内側で岡部は必死に抑えこんだ。
一時間後、賢一郎がふらりと姿を見せると、速足で近づいていって「ナビさんでした!」と弾む小声で耳打ちした。

夜が明ける。
ひとりきりの事務所で、岡部は色紙をゴミ箱に突っ込んだ。ほかの従業員の目についてはいけないと頭では理解しているのだが、一度はゴミ箱に沈めてやりたかった。
そこにはサインがひとつ、書かれていた。ご丁寧に、前日の日付まで入れてある。
彼が十代のころから憧れていたミュージシャンが一昨日に御花を訪れ、家族で宿泊していった。プライベート旅行だ。ミュージシャンといっても一般的に有名ではない。もともとバンドでベースを弾いていたが、解散後は様々なアーティストのバックを務めている。業界で知らぬ人はいない実力派だが、スポットライトを浴びるのはライブでのメンバー紹介くらいだろう。しかし岡部は、知っていた。バンド時代から本名ではなく「ナビ」名義で活動していた彼の本名が「渡邊」であることも知っていた。同じベース弾きとして、憧れでもあり、神でもあった。
もちろん、お客様として来訪した人物に従業員がサインをねだるなど、やってはならない行為だ。仕事であれ、プライベートであれ、侵してはならない一線を引いておくこと。その規律を、きちんと守ってきた。オーラ全開の女優を間近に見たときでさえ、訓練の行き届いた笑顔しか出さないよう踏ん張った。
しかし相手がナビとなると、その戒律も、ゆるんでしまった。
ミュージシャンの道はとうに過去のものだが、ナビの演奏を耳にするたび、往時の高揚が蘇る。予約欄に彼の名を見たときには、「同姓同名だ、そうに決まっている」と自分に言い聞かせたが、休憩時間になるや、スマホに入れたナビの演奏に聴き入った。
誰にでも神様はいる、と岡部は思う。地上にだって神様はいる。人の運命を変えてしまう存在が。
休憩室に上司の宗高賢一郎が入ってきて、すっとんきょうな声をあげた。
「ああ、びっくりした、いるならいるって言ってよ」
イヤホンをつけているので何を言われたのか、明瞭には聞き取れなかったが、賢一郎の表情から驚かせてしまったのはわかった。
ひとまわりも年上だったが、賢一郎の物腰に岡部は、兄に接するような気安さをおぼえていた。東京から柳川に越してきて二年。前職は放送作家だったという。月に1000本の企画案を出していたという仕事柄、万事に精通している賢一郎は、ナビのことも知っていた。あれ、きっと、ナビさんなんですよ、と雑談の途中で岡部はつい口にした。憧れの人であること、一度でいいから握手してみたいこと、そんなことまで、気づけば打ち明けていた。
「じゃあぼくがサイン頼んでみようか」
カフェでおかわりでも頼むみたいな調子の賢一郎を見て、岡部は、感動とも尊敬ともつかない声をあげた。
「いいんですか?」
「サインだろ。そりゃ、ホテルマンとしては褒められた行為じゃないかもしれないが、でも岡部君、いままで我慢してきたんだろ。ポイントカードだったら、もう満点貯まってる。お好きな有名人のサインをひとつプレゼントだよ」
「でも」
「ははは、冗談だって」
それを岡部は、ポイントカードの比喩のみにかかった言葉だと理解した。サインをもらってくれるのは冗談ではないのだと。
「え、でも、ほんとにいいんですか、サイン、頼んでもらえますか?」
真顔で確かめる岡部に、賢一郎は頬を掻きながらこう返した。
「あ、ああ。でも、あれだろ、そのお客様が岡部君の神様かどうか、実際のとこ、わからないんだろ?」
宿泊に来たのは間違いなく、ナビその人だった。宿帳には奥さんが記入し、その間、ナビは十代の息子と仲良くおしゃべりを楽しんでいた。わあ、と、眼差しから声が漏れそうになるのを、フロントの内側で岡部は必死に抑えこんだ。
一時間後、賢一郎がふらりと姿を見せると、速足で近づいていって「ナビさんでした!」と弾む小声で耳打ちした。
