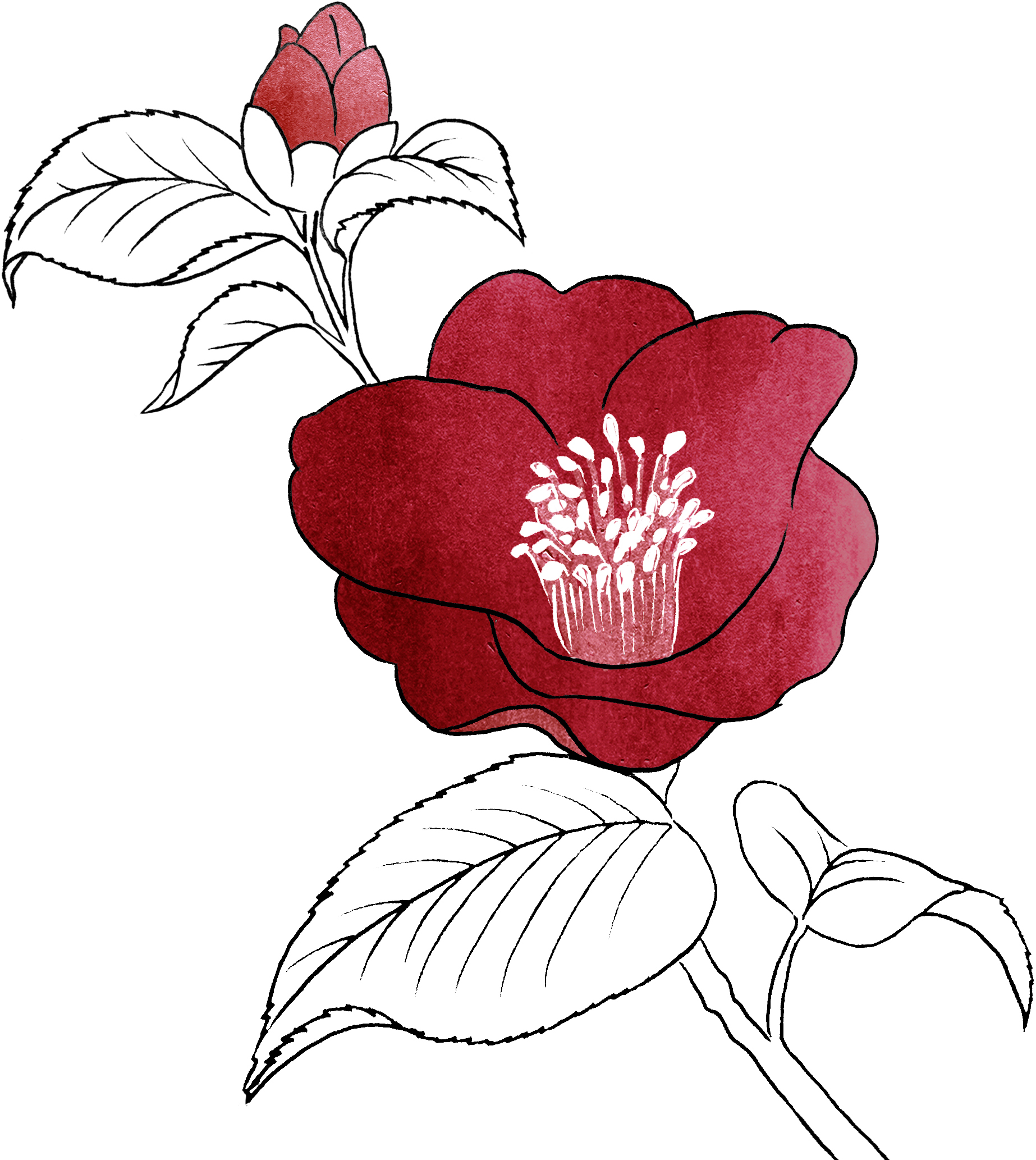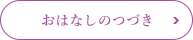ひととおり、マルシェを満喫するころにはお腹もすきはじめていて、葵はおすすめのレストランに藤野を案内した。料理を楽しみながら、午前中に見たこと、考えたことの意見交換もした。いまの職場のためにと思って観察していたつもりだったのに、藤野と話していると、御花でマルシェを開くなら、という観点から、いくらでもアイデアがわいてきた。どこまで行っても青信号の道をぐんぐんと突き進んでいくように、思いつきは途切れることがなかった。藤野はノートを取り出して、メモを取るのに一生懸命だった。
「よし、これで完璧。ありがとう葵ちゃん、ぜったい、ぜったい素敵なイベントにするね」
藤野がノートをとじると、葵は肩から力が抜けていくのを感じた。正午になったばかりなのに、もう、一日分の仕事を終えた気分だった。
「さて、じゃあ、葵ちゃんの話を聞かせてもらおうかな」
「いや、そんな、ないですよ、おもしろい話とか」
葵の反応をおだやかな笑顔で流してから、藤野は言った。
「新しい仕事は? 初めてでしょ、外で働くの」
家族に聞かれているみたいだ。葵は、すこし、照れくさくなった。
「そうですね、初めてだから、慣れるのに、すこし、手間取ってた気がします」
「うん」
「でも、もう大丈夫です。なんか、ピント、合った気がします」
テーブルの脇に置かれた藤野のカメラに、葵の視線が向いた。
「無理しないでね」
葵が具体的なことを話すつもりがないのだと悟って、藤野は、それだけ伝えた。
「んー、でも、無理しますね、私、そのために、外に出たんですし。あれです、筋肉って負荷をかけないと強くならないんです。だから、意味のある無理は、します」
頼もしいね、と藤野は返した。
それから数日が過ぎた。
仕事は忙しくなった。
忙しさに比例して、楽しさが増した。
社内で意見が衝突することもあったが、職場もマルシェのようなものだと考えると、不思議と気持ちが前を向いた。いろんな人がいる。いろんな考えがある。どうすれば調和に導けるのか、悩む価値があった。失敗と停滞がイコールではないことも学んだ。まだ、そのすべてを言葉や行動に置き換えることはできなかったものの、自分を鍛えるのだという目的は明快だった。
遅番のシフトを終えて帰路についた葵は、電車の中で御花のスタッフブログを開いた。
藤野がマルシェの告知を兼ねて、先日の視察について書いていた。
「御花の元スタッフで、いまでもかわいい妹分と、ひさしぶりに会ってきました」
そこでいろんなアイデアをもらったこと、御花を離れても御花のことを考えてくれることに、最大級の感謝の言葉も綴られていた。
「これからたくさんのタネをまいて、秋のマルシェではたくさんの魅力を咲かせます!」とブログは結ばれていた。
スマホをバッグに戻した葵は、空いた席に腰をおろして、暗い車窓を見るともなく見ていた。
頭に浮かぶのは、御花に勤めていた時代のことだ。
ときどき、以前に御花で働いていたという人物たちが訪ねてきた。訪ねる、というよりは、帰省するような雰囲気だった。千鶴社長をはじめとするスタッフたちと、離れていた時間をあっさり飛び越えて、会話に花を咲かせていた。御花を離れてわかったこと、気づいたこと、あるいは今の御花に対する厳しい意見も、皆、臆することなく、口にしていた。社長はそれを、ありがたいよね、と言って受けとめていた。
ずっと、ここにある。
いつか、社長がそんな話をしていた。
ずっと、ここにある。だから、変わっていける。
そんな話だった。どういう意味なのか、よくわからなかったけれど、夜の電車に揺られていると、なにか、つかめそうな気がした。わかるのは、これからどこへ行こうとも、御花での時間が自分の原点だということだった。原点で、だからこそ特別な場所。次に行く日はお客様でもある。お客様として、どんなことを期待するだろう。どんな御花であってほしいと願うだろう。
電車を降りて、いつもの暗い道を駐車場まで歩いた。
車に乗り込み、いつもの交差点でまた赤に引っかかった。
でも、昨日までとは心がすっかり違っていた。
ただ停まってるんじゃない。
これから、先へ進むんだ。
そう思った途端、信号が青にかわった。
ほらね、やっぱり。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。