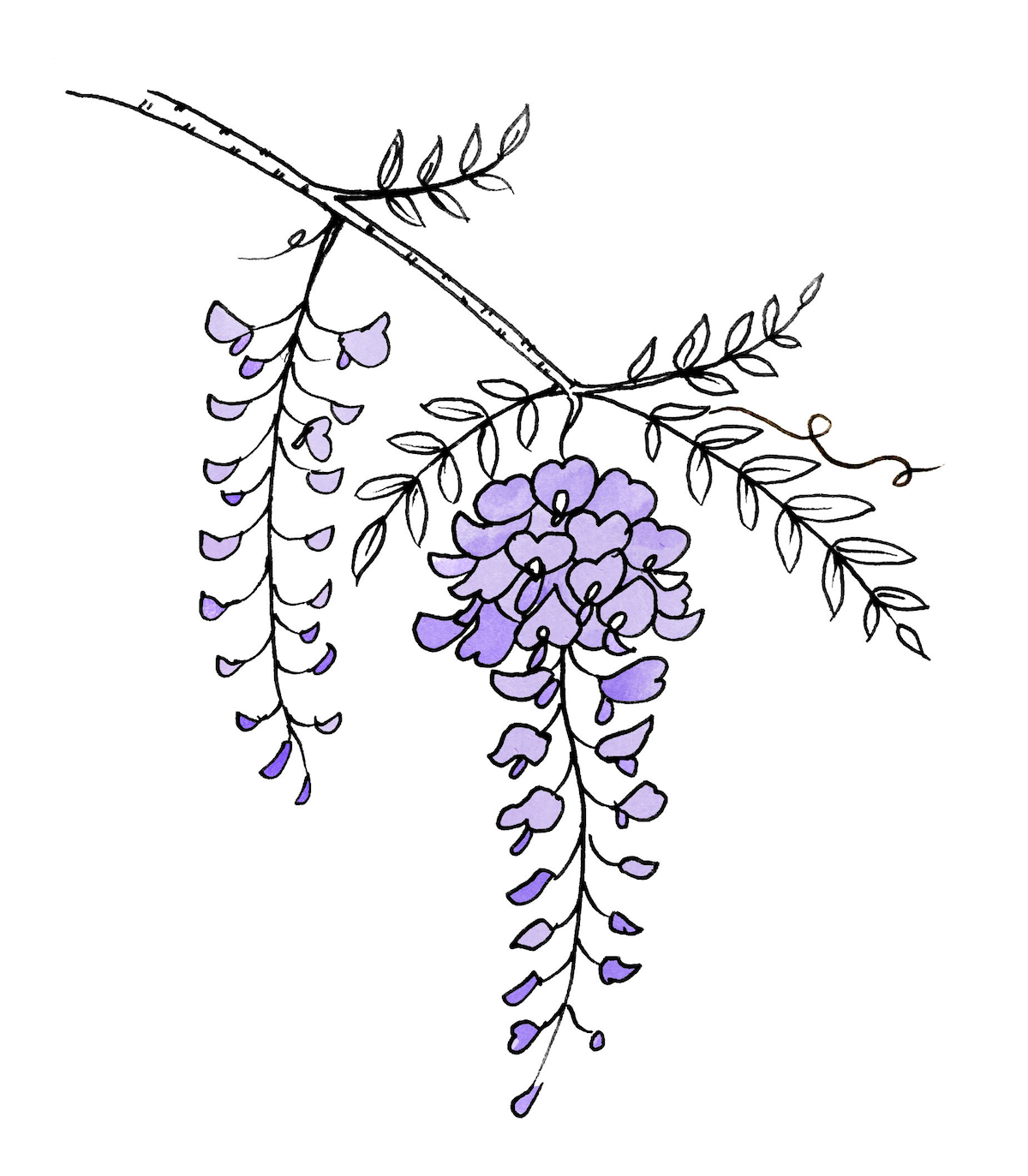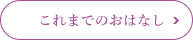帰京が迫った春のこと。よく晴れた休日を神谷は麻理恵とともに過ごしていた。市街地を歩いていると、卒業証書の筒を持って笑いあう高校生たちとすれ違い、神谷は理解した。自分の抱えている戸惑いは、卒業間近の感覚に似ているのだ、と。ほどなく離れてしまうのはわかっているのだから、せっかくの残り時間を悲しく過ごす必要なんてない。見て見ぬふりをして、楽しんだほうがいいじゃないか。
そこまでくっきりとした意図があったわけではないが、自分が選んだのはそういう道なのだと、広い公園を横切りながら神谷は考えた。でも、もう、潮時だ。
麻理恵とはさっき食べてきたスペイン料理について感想を語り合っているものの、その内容は耳から滑って入ってこない。それを察知してか、彼女はベンチで休まないかと言った。
遠距離恋愛についての答えを、その日、出すつもりでいた。しかし、まだ、結論は出せていない。
東京に戻れば仕事だって忙しくなる。麻理恵の事情を考えると、会いたいとなれば自分が福岡に飛んでくるしかない。年に一度か、せいぜい二度。会えない時間、麻理恵が誰とどんな時間を過ごしているのか、想像して苦しくなるかもしれない。お互いを憎しみあって別れる可能性だって、おおいにある。人の心に五年保障はつけられない。
眼前に広がる公園の芝生では、たくさんの人がボール遊びやフリスビー、バドミントンなどに興じていた。風が吹けば、底にまだ冬の冷たさがくっついているが、陽射しはまぶしいほどで、遠景に見えるビル群もどこかしゃんとして立って見える。世界全体が、自分だけを置いてけぼりに春へ突き進んでいる気がした。
と、そこへボールがひとつ転がってきた。
制服姿の高校生グループがこちらを見ていた。背の高い、自分と似たようなメガネをかけた男子が「すみませーん」と手を振った。しまったな、と神谷は横を向いた。芝生の中には大勢がいるというのに、自分たちの座るベンチのあたりにはほかに誰もおらず、転がり続けるボールは野球用の硬球で、手懐けたペットのように神谷目がけて近づいてくる。スポーツは観る専門だった。体育の授業や校内の大会で活躍した経験もない。しかし、このまま無視するわけにもいかないだろう。
神谷は、腹をくくった。
ちょうどいいじゃないか。
ボールを拾う。そして高校生に投げ返してやる。距離は、ざっと三十メートル。きちんと彼の手にボールが届いたなら、遠距離を申し込もう。駄目だったら? 無様な姿を見せて、すごすご東京へ逃げるだけだ。
ベンチから離れた神谷は、回転をゆるめはじめた硬球を拾おうとした。しかし、うまくタイミングがあわず、指ではじいてしまった。ボールはベンチのほうへ転がって麻理恵のパンプスにぶつかり、彼女がそれを拾った。
「はい」と麻理恵は神谷にボールを託した。
その笑顔に愛しさが募り、彼女を失わずに済む方法を頭が練り始めた。ボールを受け取って、そのまま高校生男子のもとへ駆けていき、彼の手にしっかり握らせる。そうすれば確実にボールは届くし、麻理恵との関係も延命できる、と。しかし、ズルも性に合わなかった。難儀な性格だとは思うが、どうしようもない。ボールを見ると、「祝!卒業」と赤い文字で書かれていた。ああ、野球部の子か、と神谷は推測し、下手でごめんな、と先に心の内で謝った。
振り返ると、さっきの男子がすこしこちらに近づいてくれているのがわかった。三メートルばかり縮んだだろう。それでもまだかなりの距離だ。失敗のイメージしか浮かんでこない。
とやかく考えることをやめて、投球のフォームに入る。
男子高校生が右手を掲げていた。その一点を見つめながら、神谷はボールを投げた。
音が消え、時間が間延びした。
いつまでも、いつまでも、白球は空にとどまっているような気がしたが、やがてボールは、すとん、と、男子の手のひらに落ちた。
夢のようとは、まさにそのシーンだった。
制服姿の男子がその場で飛び上がり、「ありがとうございます!」と感激するふうに言って、グループの端で様子を見ていた女子のもとへと駆け寄っていった。
神谷もすぐにベンチを振り返り、麻理恵に言った。
「結婚、してください」
突然の展開に麻理恵も驚きを隠せない様子で、いささか事務的な口調で返した。
「あ、はい」
ついさっき、ベンチのそばに誰もいないことを恨んだばかりなのに、いまはもう、その状況にまで感謝したい気持ちだった。予定外のプロポーズを、他の誰かに聞かれたら、恥ずかしさで気を失っただろう。でも、彼の言葉は、白く小さなボールのように、たった一人を目掛けて放たれた。
「それで、いったんは東京に戻ったんですけど、最初の週末に福岡に戻ってきて、彼女の実家に挨拶に行って、週末のうちに籍だけ入れたんです」
語りながら、当時の場面がずらずらと蘇ってくる。いま、語っているそのままに、ダイジェスト版めいた成り行きだった。会社を辞めて福岡に越してくるつもりだったが、上司の尽力を思うと、一週間や一ヶ月で退職するわけにもいかず、結局、その後、二年近くを東京と福岡とに離れて暮らすことになった。
「だから、まあ、遠距離恋愛は一週間だけ、なんですよね。あとは……遠距離夫婦で」
照れくさそうに語りながら、神谷は眼鏡をまた外して、ハンカチで拭いた。
「あの」と原田が身を乗り出しながら聞いた。
「いまの、いまのですよ、その、ボールの話、プロポーズの」
「ああ、はい」
「それっていつですか?」
「えーっと、八年くらい前ですよ」
「あそこですよね、公園って」
原田は、ほら、あの、ともどかしそうに口ごもったあとでひとつの公園の名を出した。まさしく、神谷がプロポーズを行った公園だった。
「それ、俺です!」
「え?」
「いまの、キャッチボールの話! 俺ですよ!」
高校の卒業式のあと、仲良しグループで近くの公園に行き、そこで野球部の友人を中心にボールを投げあっていた。球技の苦手な原田は友人の投球を取りこぼしてしまい、ベンチに座っていた男性に投げ返してもらった。そのとき、原田は自分に誓っていた。あの人の投げた球をキャッチできたら、告白しよう、と。もしもその男性が暴投したら、そのときは、そのときだ。何も言わず、友達のまま、東京の大学へ行こう。そう決めた。
「ねえ、わたしもやっぱり、花嫁舟やりたい!」
舟着場からの新郎新婦の入場を見てきたばかりの新婦は、出ていったときの倍も声をはずませながら喫茶室に戻ってきたが、夫となる男性とウエディングプランナーが手を取り合って泣いている場面に肝をつぶした。
「え、え、なに、どうしたの? え? ごめん、なに、わたし、席外したらダメだった?」
「恩人だった!」と原田が涙声で伝える。
「それはこちらの台詞ですよ」と神谷もぼろぼろと涙をこぼしながら頭をさげる。
「え? なにが? え? なに?」
落ち着いたあとで真相を知った新婦も神谷に感謝の言葉を述べたが、その一言で神谷は再び泣き出して、打合せは予定を大幅に超過することになった。その日、決まったのは、舟着場からの入場という一点のみだった。
作:中山 智幸
※この物語はフィクションです。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。
ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。
実在の人物・出来事によく似ていますが、この物語はフィクションであり、人物名はすべて架空のものです。ただし、御花を愛する心と、お越しいただく皆様への思いは、現実と変わりありません。