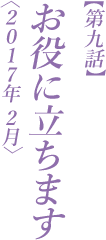
「岡本といいます。よろしくお願いします」
高校の制服の上からダッフルコートを着て、ショルダーバッグを斜めがけにした少年が、松濤館一階のスペースで挨拶をした。向かいに立つ男は、背中をすっと伸ばして、気さくな笑顔を見せた。
「おう、よろしくよろしく。僕は波場です。四十六歳。シニアマネージャーと言って、ま、ひとことでいえば、何でも屋かな。宴会場とか、観光とか、売店とか、掃除とか、調整ごととか、ぜんぶやってます。重要な仕事でいうと、外と中とのつながりを作る仕事もあるし、あとは、従業員が働いているなかで困ったことがあったら、そこをフォローしていくのも、これ重要。ん、どうした?」
「あの、今日って、僕は売店のお手伝いじゃないんですよね?」と少年は戸惑いながら質問した。
「ああ、売店ね、売店、まだオープンしてないんだよ。あとで案内するから、ほかのこともやってみよう。せっかくの職場体験なんだから。えっと、岡本君は高校一年生だよね。ということは、十六歳? 十五歳? いいねえ、若者。昨日が全体の見学で、今日が実務の体験、で合ってる? 合ってるよな、よし」
波場の言葉を聞きながら、岡本はすこし離れた場所でレクチャーを受ける同級生たちを横目に見た。二日目は売店での接客業がメインになる予定だったが、担任から突然の指示を受け、ひとり別枠での行動となった。なにをするのか聞かされないまま。
「さっそくだけど出かけようか。車酔いしない? 運転には自信あるんだけど、もしあれだったら酔い止めもあるし」
「大丈夫です」
「そう。じゃあ行こう」
返事を待たずに波場は歩き出した。建物の外に出ると、冷たい風が耳を切るように鋭く吹いてきた。どこに行くのかを聞こうと岡本が口を開きかけたところで、波場がしゃべりだした。
「これから商工会議所に企画提案書を持っていきます。来年、再来年のロードマップを作るっていう案件でね。ほら、オリンピック、来るでしょ、東京、2020年。日本も広いけど、ぜんぜん、ぜんぜん柳川も観光の候補にあがるわけで、海外からお越しになる皆さんをどうやってお招きして、どんなふうにおもてなしするか、その仕込みっていうか。燃えるよね、世界相手。岡本君は世界にいくつの国があるか知ってる? あ、ちょっと待って」
車のドアに手をかけたかと思ったら、波場はとつぜん、御花の正門に向かって走り出した。岡本もあとについて走ったが、ダッフルコートが重くて、あっという間に波場が遠ざかっていった。
その日はこの冬いちばんの冷え込みになると、天気予報アプリが告げていた。職場体験というだけでも面倒に感じていた岡本は、仮病で休もうかと真剣に悩んだ。もともと、人見知りが強く、接客に向かない性格だと自覚していた。これもひとつの体験だから、と担任の勧めに従って御花を選びはしたものの、一日目の見学では、自分にとっての必要性が見えてこなかった。岡本の父は家具調度品のメーカーを経営しており、将来はそこを継ぐ予定だった。営業的な活動は必要だろうが、自ら接客をすることは考えにくい。だから、疑問だった。
こんな経験が何の役に立つのだろう?
「ほら! ごみ!」
父とそうかわらない年齢の男が、正門を出たところに落ちているペットボトルを拾って、宝物を見つけたみたいに声をあげている。
「もうさ、ごみとか駄目だよ、道はごみ箱じゃないんだから。こういうのね、気がついたらさっと拾って、しかるべき場所に捨てておかないと、まっさらなTシャツでカレーうどん食べてはねることあるじゃない、あ、ごみ箱あっちにあるから、で、なんだっけ。そう、カレーうどん、知ってる? うまい店があるんだよ。これ捨ててくるから、ちょっと待ってて」
コートを着ていない波場はスーツのジャケットをはためかせながら、自販機横のごみ箱へ走っていった。岡本はちいさな肩をさらにせばめながら、ポケットに手をつっこんで待っていた。
商工会議所へ向かう車の中でも、波場のおしゃべりは続いた。
2020年に向けて、あるいは100年後に向けて、御花がなにをできるのか、考えることが沢山あるんだよね、と彼が語る言葉は、コンパクトカーからはみだしそうなほど壮大に響いた。
「でもね、いまいちばん頭を悩ませてるのは、今年の夏のことなんだよ。こう寒いとなかなか実感わかないけど、夏、夏にね、御花でさ、毎年夏祭りやってるんだ。七福神まつりっていうの。知ってる? 手作りの、わきあいあいとした空気で、岡本君も来るといいよ、楽しいから」
「あ、それ、多分、参加します」
助手席で初めて発した言葉だった。
「え? 参加するの?」
「はい。出店の体験みたいなこと、やる予定だって、担任の先生から聞いてます」
「ああ! はいはい、それね、それ、俺が企画したんだった!」
は、と疑問形の小さな声が岡本の口から漏れた。
「そう! 岡本君もやるんだ! なにやる? 綿菓子? たこ焼き? りんご飴?」
それはまだわからない、という返答に続けて、岡本は尋ねた。
「波場さんが企画したんですか?」
「うん、まあ、言い出したのは別のね、うちの瀬ノ本ってスタッフで、アルバイトの面倒をすげえしっかり見てくれてるんだけど、若い人間にどんどんチャンス与えたいって考えてて、その会話の流れで出てきた案をいくつか企画書にしてね、そのうちのひとつだったんじゃないかな」
はっきりしない返答に、岡本は話題を変えた。
「メールじゃ駄目なんですか?」
「ん?」
思いがけない問いかけだったのか、波場が返事を保留した。
「企画書、いまから届けに行くんですよね」
「ああ、メールもいいよね、メールのおかげで世界が広がってるもんな。僕もね、上手に書ければっていつも思うよ、メール。僕が書くと、なんでか大長編になるから」
でしょうね、と岡本は声に出さずに思った。
それからしばらくのあいだ、波場は柳川の町並みを指や目線で示しながら、歴史についてのレクチャーを重ねていった。柳川に生きるひとりの人間として、岡本も多少の知識は持っているつもりでいたが、波場の情報量には圧倒されたし、知っていることでも、波場の口から聞くと、興味と想像を掻き立てられた。営業で培ったトークスキルなのだろうかと、岡本は推測した。
商工会議所に到着し、いっしょに車を降りた岡本は、会う人ごとに快活に挨拶を交わしていく波場のうしろを静かについていった。
「ツアーガイドもやってたんですか?」と帰りの車中で岡本は聞いた。
「専門ではやってないけど、似たようなことはやるよ。営業に所属してたときには旅行代理店の方々を遠方から招いて、柳川の魅力をね、しっかり伝えて、持ち帰ってもらわなくちゃいけなかったから、余すところなく紹介して、それまではね、そんなに興味があったわけじゃないよ、あ、ほらあそこがカレーうどんのうまい店。で、歴史とかも、へえ、おもしろいですね、くらいのものだったんだけど。ちょうど今、さげもんの季節だけど、前はさ、きれいだなーくらいにしか思ってなかったけど、さげもんの数に込められた意味とかを知って、実際に作ってらっしゃる方に会ったりすると、見え方って、がらっと変わるんだよね。そういう意味では、役に立たない情報なんてないよね」
〈一を聞いて十を知る〉という言葉を学校で教わったが、この人は〈一を聞いて十を返す〉だな、と岡本は思った。

「岡本といいます。よろしくお願いします」
高校の制服の上からダッフルコートを着て、ショルダーバッグを斜めがけにした少年が、松濤館一階のスペースで挨拶をした。向かいに立つ男は、背中をすっと伸ばして、気さくな笑顔を見せた。
「おう、よろしくよろしく。僕は波場です。四十六歳。シニアマネージャーと言って、ま、ひとことでいえば、何でも屋かな。宴会場とか、観光とか、売店とか、掃除とか、調整ごととか、ぜんぶやってます。重要な仕事でいうと、外と中とのつながりを作る仕事もあるし、あとは、従業員が働いているなかで困ったことがあったら、そこをフォローしていくのも、これ重要。ん、どうした?」
「あの、今日って、僕は売店のお手伝いじゃないんですよね?」と少年は戸惑いながら質問した。
「ああ、売店ね、売店、まだオープンしてないんだよ。あとで案内するから、ほかのこともやってみよう。せっかくの職場体験なんだから。えっと、岡本君は高校一年生だよね。ということは、十六歳? 十五歳? いいねえ、若者。昨日が全体の見学で、今日が実務の体験、で合ってる? 合ってるよな、よし」
波場の言葉を聞きながら、岡本はすこし離れた場所でレクチャーを受ける同級生たちを横目に見た。二日目は売店での接客業がメインになる予定だったが、担任から突然の指示を受け、ひとり別枠での行動となった。なにをするのか聞かされないまま。
「さっそくだけど出かけようか。車酔いしない? 運転には自信あるんだけど、もしあれだったら酔い止めもあるし」
「大丈夫です」
「そう。じゃあ行こう」
返事を待たずに波場は歩き出した。建物の外に出ると、冷たい風が耳を切るように鋭く吹いてきた。どこに行くのかを聞こうと岡本が口を開きかけたところで、波場がしゃべりだした。
「これから商工会議所に企画提案書を持っていきます。来年、再来年のロードマップを作るっていう案件でね。ほら、オリンピック、来るでしょ、東京、2020年。日本も広いけど、ぜんぜん、ぜんぜん柳川も観光の候補にあがるわけで、海外からお越しになる皆さんをどうやってお招きして、どんなふうにおもてなしするか、その仕込みっていうか。燃えるよね、世界相手。岡本君は世界にいくつの国があるか知ってる? あ、ちょっと待って」
車のドアに手をかけたかと思ったら、波場はとつぜん、御花の正門に向かって走り出した。岡本もあとについて走ったが、ダッフルコートが重くて、あっという間に波場が遠ざかっていった。
その日はこの冬いちばんの冷え込みになると、天気予報アプリが告げていた。職場体験というだけでも面倒に感じていた岡本は、仮病で休もうかと真剣に悩んだ。もともと、人見知りが強く、接客に向かない性格だと自覚していた。これもひとつの体験だから、と担任の勧めに従って御花を選びはしたものの、一日目の見学では、自分にとっての必要性が見えてこなかった。岡本の父は家具調度品のメーカーを経営しており、将来はそこを継ぐ予定だった。営業的な活動は必要だろうが、自ら接客をすることは考えにくい。だから、疑問だった。
こんな経験が何の役に立つのだろう?
「ほら! ごみ!」
父とそうかわらない年齢の男が、正門を出たところに落ちているペットボトルを拾って、宝物を見つけたみたいに声をあげている。
「もうさ、ごみとか駄目だよ、道はごみ箱じゃないんだから。こういうのね、気がついたらさっと拾って、しかるべき場所に捨てておかないと、まっさらなTシャツでカレーうどん食べてはねることあるじゃない、あ、ごみ箱あっちにあるから、で、なんだっけ。そう、カレーうどん、知ってる? うまい店があるんだよ。これ捨ててくるから、ちょっと待ってて」
コートを着ていない波場はスーツのジャケットをはためかせながら、自販機横のごみ箱へ走っていった。岡本はちいさな肩をさらにせばめながら、ポケットに手をつっこんで待っていた。
商工会議所へ向かう車の中でも、波場のおしゃべりは続いた。
2020年に向けて、あるいは一〇〇年後に向けて、御花がなにをできるのか、考えることが沢山あるんだよね、と彼が語る言葉は、コンパクトカーからはみだしそうなほど壮大に響いた。
「でもね、いまいちばん頭を悩ませてるのは、今年の夏のことなんだよ。こう寒いとなかなか実感わかないけど、夏、夏にね、御花でさ、毎年夏祭りやってるんだ。七福神まつりっていうの。知ってる? 手作りの、わきあいあいとした空気で、岡本君も来るといいよ、楽しいから」
「あ、それ、多分、参加します」
助手席で初めて発した言葉だった。
「え? 参加するの?」
「はい。出店の体験みたいなこと、やる予定だって、担任の先生から聞いてます」
「ああ! はいはい、それね、それ、俺が企画したんだった!」
は、と疑問形の小さな声が岡本の口から漏れた。
「そう! 岡本君もやるんだ! なにやる? 綿菓子? たこ焼き? りんご飴?」
それはまだわからない、という返答に続けて、岡本は尋ねた。
「波場さんが企画したんですか?」
「うん、まあ、言い出したのは別のね、うちの瀬ノ本ってスタッフで、アルバイトの面倒をすげえしっかり見てくれてるんだけど、若い人間にどんどんチャンス与えたいって考えてて、その会話の流れで出てきた案をいくつか企画書にしてね、そのうちのひとつだったんじゃないかな」
はっきりしない返答に、岡本は話題を変えた。
「メールじゃ駄目なんですか?」
「ん?」
思いがけない問いかけだったのか、波場が返事を保留した。
「企画書、いまから届けに行くんですよね」
「ああ、メールもいいよね、メールのおかげで世界が広がってるもんな。僕もね、上手に書ければっていつも思うよ、メール。僕が書くと、なんでか大長編になるから」
でしょうね、と岡本は声に出さずに思った。
それからしばらくのあいだ、波場は柳川の町並みを指や目線で示しながら、歴史についてのレクチャーを重ねていった。柳川に生きるひとりの人間として、岡本も多少の知識は持っているつもりでいたが、波場の情報量には圧倒されたし、知っていることでも、波場の口から聞くと、興味と想像を掻き立てられた。営業で培ったトークスキルなのだろうかと、岡本は推測した。
商工会議所に到着し、いっしょに車を降りた岡本は、会う人ごとに快活に挨拶を交わしていく波場のうしろを静かについていった。
「ツアーガイドもやってたんですか?」と帰りの車中で岡本は聞いた。
「専門ではやってないけど、似たようなことはやるよ。営業に所属してたときには旅行代理店の方々を遠方から招いて、柳川の魅力をね、しっかり伝えて、持ち帰ってもらわなくちゃいけなかったから、余すところなく紹介して、それまではね、そんなに興味があったわけじゃないよ、あ、ほらあそこがカレーうどんのうまい店。で、歴史とかも、へえ、おもしろいですね、くらいのものだったんだけど。ちょうど今、さげもんの季節だけど、前はさ、きれいだなーくらいにしか思ってなかったけど、さげもんの数に込められた意味とかを知って、実際に作ってらっしゃる方に会ったりすると、見え方って、がらっと変わるんだよね。そういう意味では、役に立たない情報なんてないよね」
〈一を聞いて十を知る〉という言葉を学校で教わったが、この人は〈一を聞いて十を返す〉だな、と岡本は思った。
