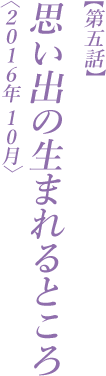
人の顔を覚えるのは得意なほうではないので、同僚たちの記憶力の良さを目の当たりにするたび、裏方でよかったな、と、藤野優実は安堵の息を洩らす。
「まあ、藤野さんは人当たりがいいからさ、客商売に向いてないってことではないよ」と、向かいの席の細田は言う。気遣いなのか、本心なのか、神経質そうな風貌からは判断が難しいところだ。
「そう言っていただけると、ほっとします。それで細田さん、この子、見覚えありませんか?」
藤野はプリントアウトしたA4紙を、向かいの席の細田に渡した。
そこにはオレンジがかった写真が一枚、印刷されていた。
御花の日本庭園である松濤園を背景に、テラスのような場所で幼い子がひとり、椅子に腰掛けている。三歳か四歳くらいだろうか。ワンピースに麦わら帽子なので、季節は夏だろう。顔からはみだしそうなほどの笑みで、上半身をのけぞらせている。時刻は昼間か、あるいは夕方か。
「これ、いつの」と細田が眉間にしわを寄せる。
「三十年くらい前ですね」
自分の端末を操作しながら、藤野が答えた。
「あのね、藤野さん、僕、ここで働きはじめて五年だから、そんなね、三十年も前のことを知るわけがないじゃない。社長にでも聞いてくださいよ」
「ですよね」
笑って答えてから、でもなんか見覚えあるんだけど、と胸の内でつぶやいた。
事務と広報を兼務する藤野は、スタッフブログの執筆も担当しているため、ネタを見つけるためにもときどき過去の資料を掘り返している。膨大な量だが、数年かけてデジタル化したおかげで、閲覧はずいぶん楽になった。
ガイドブックや新聞に掲載されたもの、映画やドラマの撮影に使用された際のメイキング写真や、往時のスタッフが撮影したものなどに混じって、訪れたお客様から送っていただいた写真も数多い。このごろは少なくなってきたが、以前は、御花でのひとときについて感想を綴ってくださる方もいらして、写真が同封されることも珍しくなかった。そう、宗高社長に聞いたことがある。
「思い出のおすそわけ」と社長が何気なく口にした言葉を、藤野も胸にとどめている。ブログにも、そんな作用があれば、と願いながら、執筆にはいつも頭を悩ませていた。
「でもさ、これ、いまと随分、見え方が違うね」
ふと、細田が言った。
「え?」
「対月館のテラスから撮ったものだろうけど、でも、ほら、松濤館がない」
藤野は席を離れて、細田の隣にまわった。
「あ、ほんとですね」
女の子にばかり注意が向いて、背景が見えていなかったことに藤野は気づいた。言われてみれば、自分たちの職場でもある松濤館がない。気になることは細大漏らさず追及する性格で、経理には向いているが、一方で、心に引っかからないことには、とんと無頓着でもある。
「ここが建ったのが1984年だから」と細田が宙を見つめながら言った。さすがだ。細田の記憶力に藤野はまたも感心する。それはお客様からいただいた写真を収めたフォルダから発掘した一枚だった。年代別に区分されたフォルダ名には、[80年代2]と記されていた。
「それより前、ってことですね。これ、昔あったっていう、お蔵ですか?」
藤野が指したところには、大きな蔵が立っていた。現在は芝生が広がっているその場所に、蔵など跡形もない。細田は興味を持てないのか、別の視点から写真を読み解いていく。
「対月館のテラスにしては、ずいぶん、池が近いというか、これ、一階かな」
「あ、ほんとですね」
藤野は壁に額装されている写真を振り返った。前の年にプロカメラマンが撮ったもので、対月館のテラスから池を見下ろすような角度になっている。一方の古い写真は、すぐそこが池庭だ。
「すごいですね細田さん、一目でそんなことまで気づくなんて、名探偵ですね」
いやあ、と細田が表情を崩す。照れているのか、藤野の褒め方に戸惑っているのか、どちらともつかない笑顔だ。
「たとえ名探偵でも、この子の正体までは、つかみかねるね」
「ですよね」
紙を藤野に返すと、細田は仕事に戻った。藤野も自分の席に戻り、東京のカメラマンから届いた写真データの整理に取り掛かった。
作業に一段落ついたところで、藤野は立花家史料館に用があったことを思い出し、席を離れた。ポケットにはさっきの紙を折りたたんで入れてある。史料館へ赴くついでに、対月館にもまわるつもりだった。
建物を出て、振り返る。そこは、ホテル兼宴会場である松濤館で、彼女の働く事務所も入っていた。いまや生活のほとんどを過ごしている建物が、自分よりも年下だなどと、意識したことはなかった。
いま、あらためてその事実と向き合ってみたところで、堂々とした風格の松濤館に向かって、「あんた若いね」とも思えない。
御花で働く前には大学の事務職に就いて、体育館の管理業務に従事していた。そこでは十代の子の声を聞いただけでも、隔たりを感じた。老いた、とまでは言わないものの、「時間が巻き戻せない」事実を味わうには十分な距離を聞き取れた。
その点、御花という場所は、いまや、地球上の誰よりも長く生きているわけで、その歴史に思いを馳せるだけでも、広くて深い懐に抱かれているような心地よさを感じられる。
「まさかここに入れる日が来るなんて思いもよらなかったわ」
近隣に暮らす高齢の人々は、そう口をそろえる。かつての御花が「伯爵家の別邸」で、一般の人間が足を踏み入れることのかなわない領域でもあったためだ。いまとなっては(と藤野は当時を知っているふうに考えてしまう)そんな時代のことのほうが不思議に思えるくらい、気軽に入ることができる。
駐車場にさしかかると、西洋館の前で「あの」と男性が声をかけてきた。ツイードのジャケットを着た初老の人物で、彼のそばには同年輩の男性が五人、西洋館を背にして立っている。
「シャッター、押していただけませんか」
彼の手にはずっしりと重たげな一眼レフカメラが握られていて、藤野は一瞬、たじろいだ。
フィルムかな、という推測のせいだ。しかし、渡されたカメラはディスプレイ付きのデジタル一眼で、ほっとする。
観光地という場所柄、撮影係を頼まれる機会は少なくない。お客様からわけていただく写真が「思い出の、おすそわけ」と呼べるのは、ここでの時間を楽しんでいただけたことが写真から伝わってくるからだ。視点を変えるならば、撮影係を務めるのは、思い出づくりに参加させていただくことでもある。
御花で働きはじめたころは、撮影を頼まれるうちの多くがフィルムカメラだった。スマホだってまだ主流ではなく、それがあっという間に写真機器の勢力図が変わってしまった。フィルムだと緊張するんだよな、と、往時を思い出すたび、肩のこわばりまで蘇る。
ジャケットの男性は横一列に並ぶ仲間の端に加わった。
ジーンズに長袖のポロシャツを着た人。トレンチコートをまとった人。ゆったりしたスーツ姿の人。六人は服装も体型もばらばらで、とはいえ、漂う雰囲気はまず確実に友人同士のそれで、笑顔になるよう頼まなくても、実にリラックスした表情を浮かべている。西洋館の屋根までを入れながら、藤野は構図を決めようと、カメラの背面のディスプレイとにらめっこしていた。
「ご旅行ですか」と、そのあいだに話しかける。ええ、とか、はい、とか、複数の返事が聞こえ、あちら側で男性陣の照れるような苦笑が空気を揺らした。

人の顔を覚えるのは得意なほうではないので、同僚たちの記憶力の良さを目の当たりにするたび、裏方でよかったな、と、藤野優実は安堵の息を洩らす。
「まあ、藤野さんは人当たりがいいからさ、客商売に向いてないってことではないよ」と、向かいの席の細田は言う。気遣いなのか、本心なのか、神経質そうな風貌からは判断が難しいところだ。
「そう言っていただけると、ほっとします。それで細田さん、この子、見覚えありませんか?」
藤野はプリントアウトしたA4紙を、向かいの席の細田に渡した。
そこにはオレンジがかった写真が一枚、印刷されていた。
御花の日本庭園である松濤園を背景に、テラスのような場所で幼い子がひとり、椅子に腰掛けている。三歳か四歳くらいだろうか。ワンピースに麦わら帽子なので、季節は夏だろう。顔からはみだしそうなほどの笑みで、上半身をのけぞらせている。時刻は昼間か、あるいは夕方か。
「これ、いつの」と細田が眉間にしわを寄せる。
「三十年くらい前ですね」
自分の端末を操作しながら、藤野が答えた。
「あのね、藤野さん、僕、ここで働きはじめて五年だから、そんなね、三十年も前のことを知るわけがないじゃない。社長にでも聞いてくださいよ」
「ですよね」
笑って答えてから、でもなんか見覚えあるんだけど、と胸の内でつぶやいた。
事務と広報を兼務する藤野は、スタッフブログの執筆も担当しているため、ネタを見つけるためにもときどき過去の資料を掘り返している。膨大な量だが、数年かけてデジタル化したおかげで、閲覧はずいぶん楽になった。
ガイドブックや新聞に掲載されたもの、映画やドラマの撮影に使用された際のメイキング写真や、往時のスタッフが撮影したものなどに混じって、訪れたお客様から送っていただいた写真も数多い。このごろは少なくなってきたが、以前は、御花でのひとときについて感想を綴ってくださる方もいらして、写真が同封されることも珍しくなかった。そう、宗高社長に聞いたことがある。
「思い出のおすそわけ」と社長が何気なく口にした言葉を、藤野も胸にとどめている。ブログにも、そんな作用があれば、と願いながら、執筆にはいつも頭を悩ませていた。
「でもさ、これ、いまと随分、見え方が違うね」
ふと、細田が言った。
「え?」
「対月館のテラスから撮ったものだろうけど、でも、ほら、松濤館がない」
藤野は席を離れて、細田の隣にまわった。
「あ、ほんとですね」
女の子にばかり注意が向いて、背景が見えていなかったことに藤野は気づいた。言われてみれば、自分たちの職場でもある松濤館がない。気になることは細大漏らさず追及する性格で、経理には向いているが、一方で、心に引っかからないことには、とんと無頓着でもある。
「ここが建ったのが1984年だから」と細田が宙を見つめながら言った。さすがだ。細田の記憶力に藤野はまたも感心する。それはお客様からいただいた写真を収めたフォルダから発掘した一枚だった。年代別に区分されたフォルダ名には、[80年代2]と記されていた。
「それより前、ってことですね。これ、昔あったっていう、お蔵ですか?」
藤野が指したところには、大きな蔵が立っていた。現在は芝生が広がっているその場所に、蔵など跡形もない。細田は興味を持てないのか、別の視点から写真を読み解いていく。
「対月館のテラスにしては、ずいぶん、池が近いというか、これ、一階かな」
「あ、ほんとですね」
藤野は壁に額装されている写真を振り返った。前の年にプロカメラマンが撮ったもので、対月館のテラスから池を見下ろすような角度になっている。一方の古い写真は、すぐそこが池庭だ。
「すごいですね細田さん、一目でそんなことまで気づくなんて、名探偵ですね」
いやあ、と細田が表情を崩す。照れているのか、藤野の褒め方に戸惑っているのか、どちらともつかない笑顔だ。
「たとえ名探偵でも、この子の正体までは、つかみかねるね」
「ですよね」
紙を藤野に返すと、細田は仕事に戻った。藤野も自分の席に戻り、東京のカメラマンから届いた写真データの整理に取り掛かった。
作業に一段落ついたところで、藤野は立花家史料館に用があったことを思い出し、席を離れた。ポケットにはさっきの紙を折りたたんで入れてある。史料館へ赴くついでに、対月館にもまわるつもりだった。
建物を出て、振り返る。そこは、ホテル兼宴会場である松濤館で、彼女の働く事務所も入っていた。いまや生活のほとんどを過ごしている建物が、自分よりも年下だなどと、意識したことはなかった。
いま、あらためてその事実と向き合ってみたところで、堂々とした風格の松濤館に向かって、「あんた若いね」とも思えない。
御花で働く前には大学の事務職に就いて、体育館の管理業務に従事していた。そこでは十代の子の声を聞いただけでも、隔たりを感じた。老いた、とまでは言わないものの、「時間が巻き戻せない」事実を味わうには十分な距離を聞き取れた。
その点、御花という場所は、いまや、地球上の誰よりも長く生きているわけで、その歴史に思いを馳せるだけでも、広くて深い懐に抱かれているような心地よさを感じられる。
「まさかここに入れる日が来るなんて思いもよらなかったわ」
近隣に暮らす高齢の人々は、そう口をそろえる。かつての御花が「伯爵家の別邸」で、一般の人間が足を踏み入れることのかなわない領域でもあったためだ。いまとなっては(と藤野は当時を知っているふうに考えてしまう)そんな時代のことのほうが不思議に思えるくらい、気軽に入ることができる。
駐車場にさしかかると、西洋館の前で「あの」と男性が声をかけてきた。ツイードのジャケットを着た初老の人物で、彼のそばには同年輩の男性が五人、西洋館を背にして立っている。
「シャッター、押していただけませんか」
彼の手にはずっしりと重たげな一眼レフカメラが握られていて、藤野は一瞬、たじろいだ。
フィルムかな、という推測のせいだ。しかし、渡されたカメラはディスプレイ付きのデジタル一眼で、ほっとする。
観光地という場所柄、撮影係を頼まれる機会は少なくない。お客様からわけていただく写真が「思い出の、おすそわけ」と呼べるのは、ここでの時間を楽しんでいただけたことが写真から伝わってくるからだ。視点を変えるならば、撮影係を務めるのは、思い出づくりに参加させていただくことでもある。
御花で働きはじめたころは、撮影を頼まれるうちの多くがフィルムカメラだった。スマホだってまだ主流ではなく、それがあっという間に写真機器の勢力図が変わってしまった。フィルムだと緊張するんだよな、と、往時を思い出すたび、肩のこわばりまで蘇る。
ジャケットの男性は横一列に並ぶ仲間の端に加わった。
ジーンズに長袖のポロシャツを着た人。トレンチコートをまとった人。ゆったりしたスーツ姿の人。六人は服装も体型もばらばらで、とはいえ、漂う雰囲気はまず確実に友人同士のそれで、笑顔になるよう頼まなくても、実にリラックスした表情を浮かべている。西洋館の屋根までを入れながら、藤野は構図を決めようと、カメラの背面のディスプレイとにらめっこしていた。
「ご旅行ですか」と、そのあいだに話しかける。ええ、とか、はい、とか、複数の返事が聞こえ、あちら側で男性陣の照れるような苦笑が空気を揺らした。
